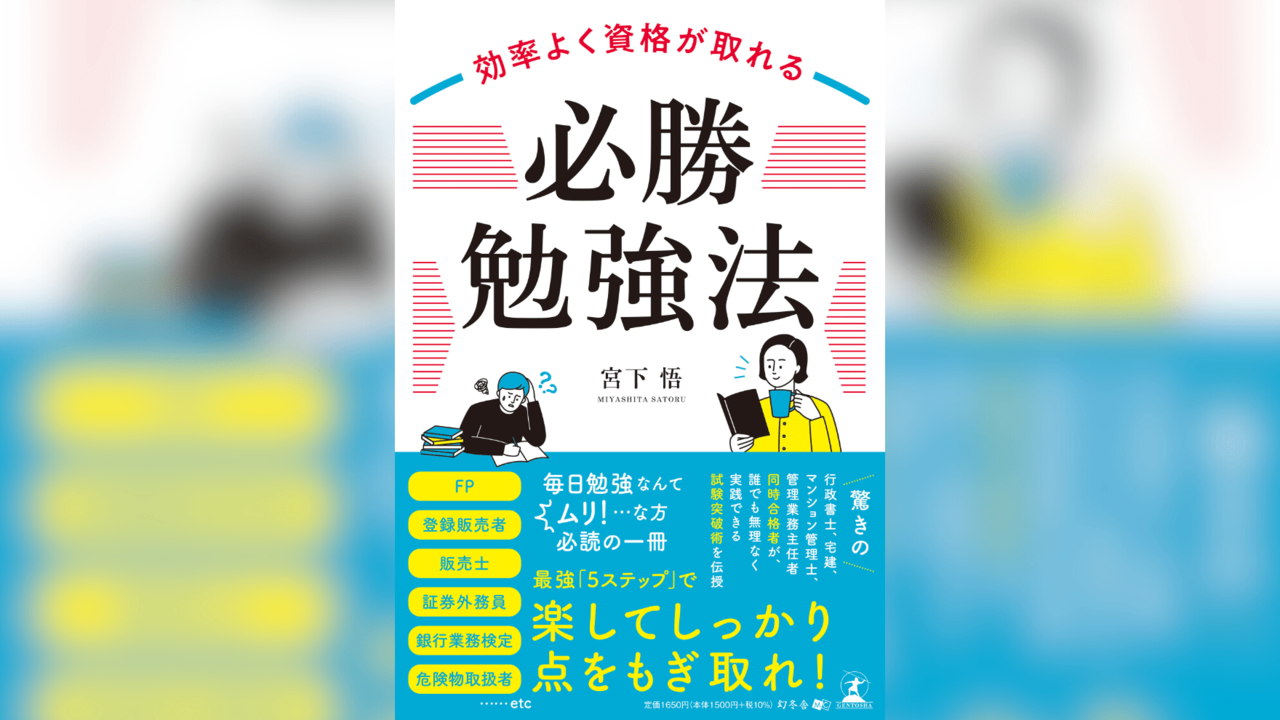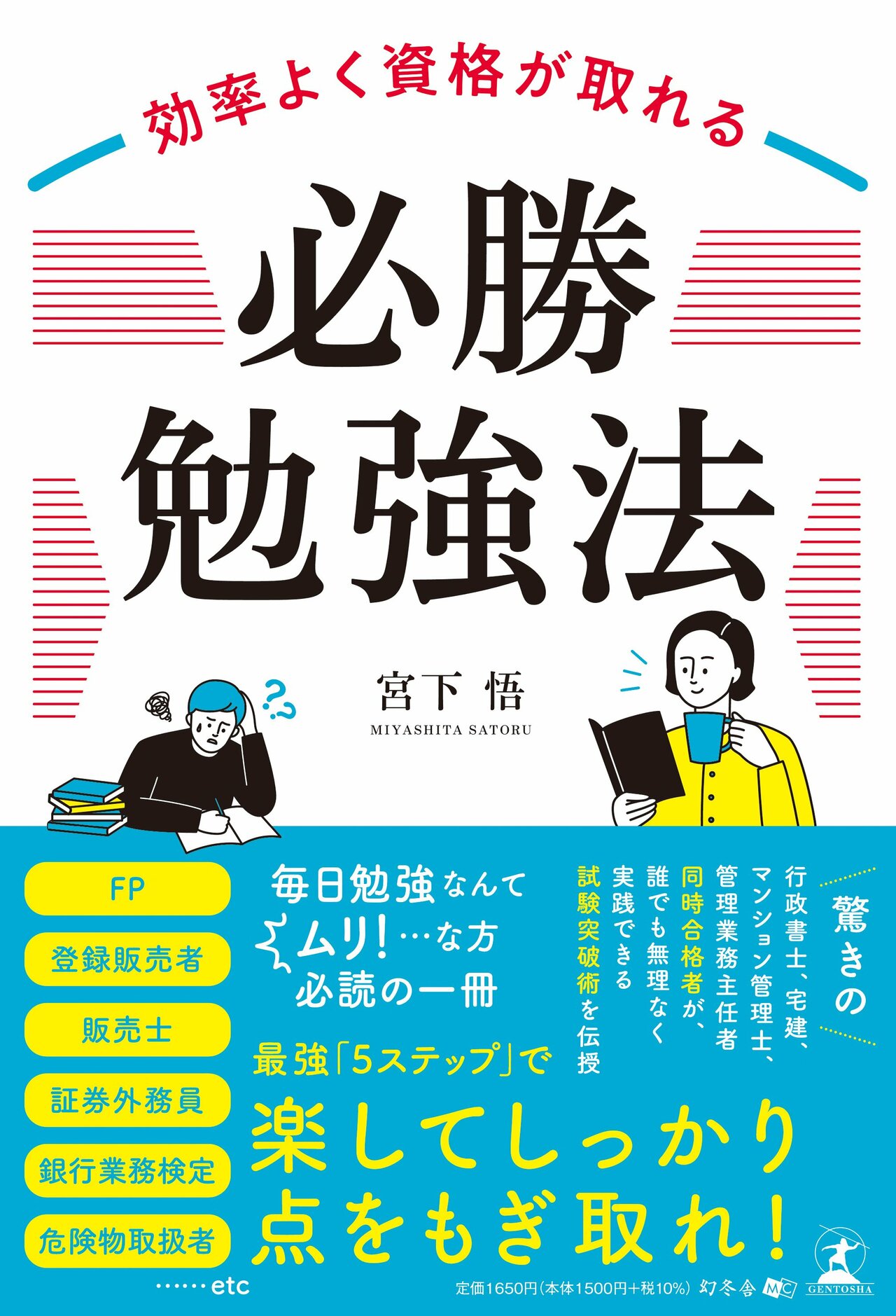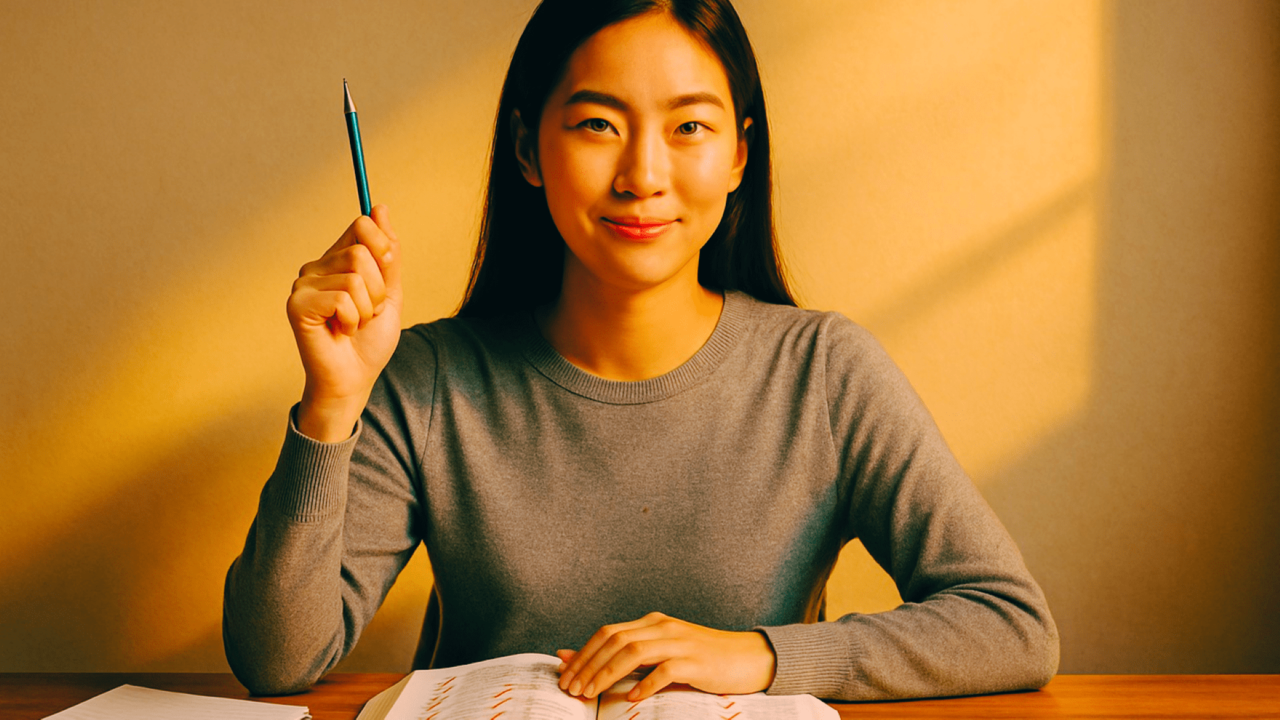【前回の記事を読む】知らないと損! ガソリンスタンドで役立つ危険物取扱者の力とは
第3章 具体的な勉強方法
1 一回目:過去問をサラッと勉強する
私が提案する勉強法は、繰り返しになるが、「過去問を解くことを通じて、『合格力』を身につける」ことを前提としている。そして、その「合格力」を身につけるには、「五年分の過去問を五回解く」ことが基本になる。過去問を繰り返すうちに、自分が得意な分野、不得意な分野が浮き彫りになってくる。
だが、単純に過去問を繰り返し勉強すればよい、というものではない。効率よく覚えるには、各回ごとに過去問への「アプローチ法」は異なるし、勉強してから再度復習する時期、すなわち「タイミング」も重要である。
その点を踏まえた上で、勉強法を習得していただきたい。
まず、一回目の勉強は、過去問の選択肢を読み、読み終わった後すぐに、選択肢の解答と解説を読む。例えば、四肢択一問題であれば、最初の選択肢①を読み、すぐにその選択肢の解答・解説を読む。それを選択肢①から④まで繰り返す。
なお、一回(一セット)に取り組む過去問の問題数は、四~六問程度がよい。分野別に分かれている五年分の過去問であれば、この問題数で一分野の中の一項目をカバーする程度になるだろう(なお、大きなグループ分け・章を「分野」、その中の小さなグループ分け・節を「項目」とする)。
この分量であれば、時間にして三十分から一時間程度でできるのではないか。「その量では少ないのでは?」との声もあろう。その点については、「勉強休み」を作ることや、勉強に対するモチベーションを維持する、ということにつながる。
当然、テキストを読んでいないまま過去問に接するのであるから、内容がほとんど理解できないのも当然である。だが、それは初めてテキストを読むときと変わらない。むしろ、ここではまず「どういう形で問題が出るのか」や「こういう用語があるんだ」ということを認識することに意味がある。
よって、「一回目から内容を完全に理解しよう」なんて、決して考えないほうがよい。
私が提案する勉強法は、「得た知識を上塗りし、定着させる」ことがベースにある。復習を重ねることにより、蓄えられる知識が増え、結果的に「合格力」が身につくというものである。だからこそ、最初から欲張って広範囲にわたり勉強することや、焦って無理に覚えようとすることは禁物であることを肝に銘じよう。