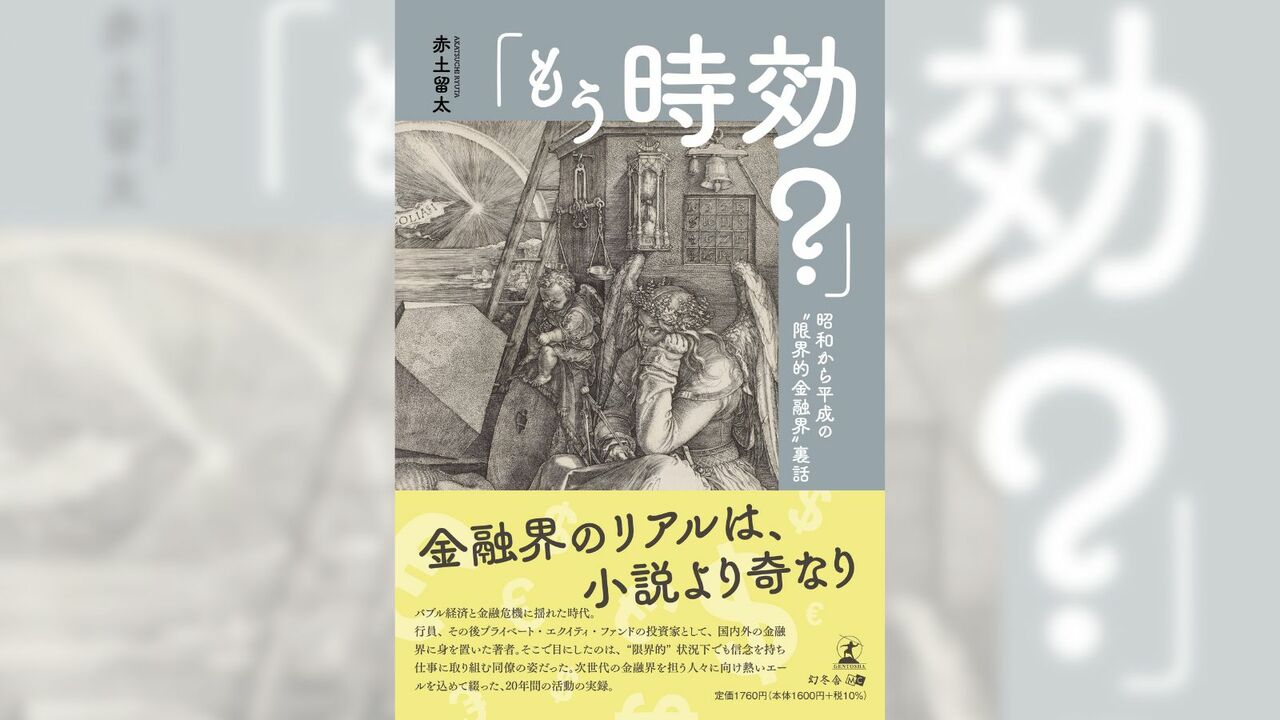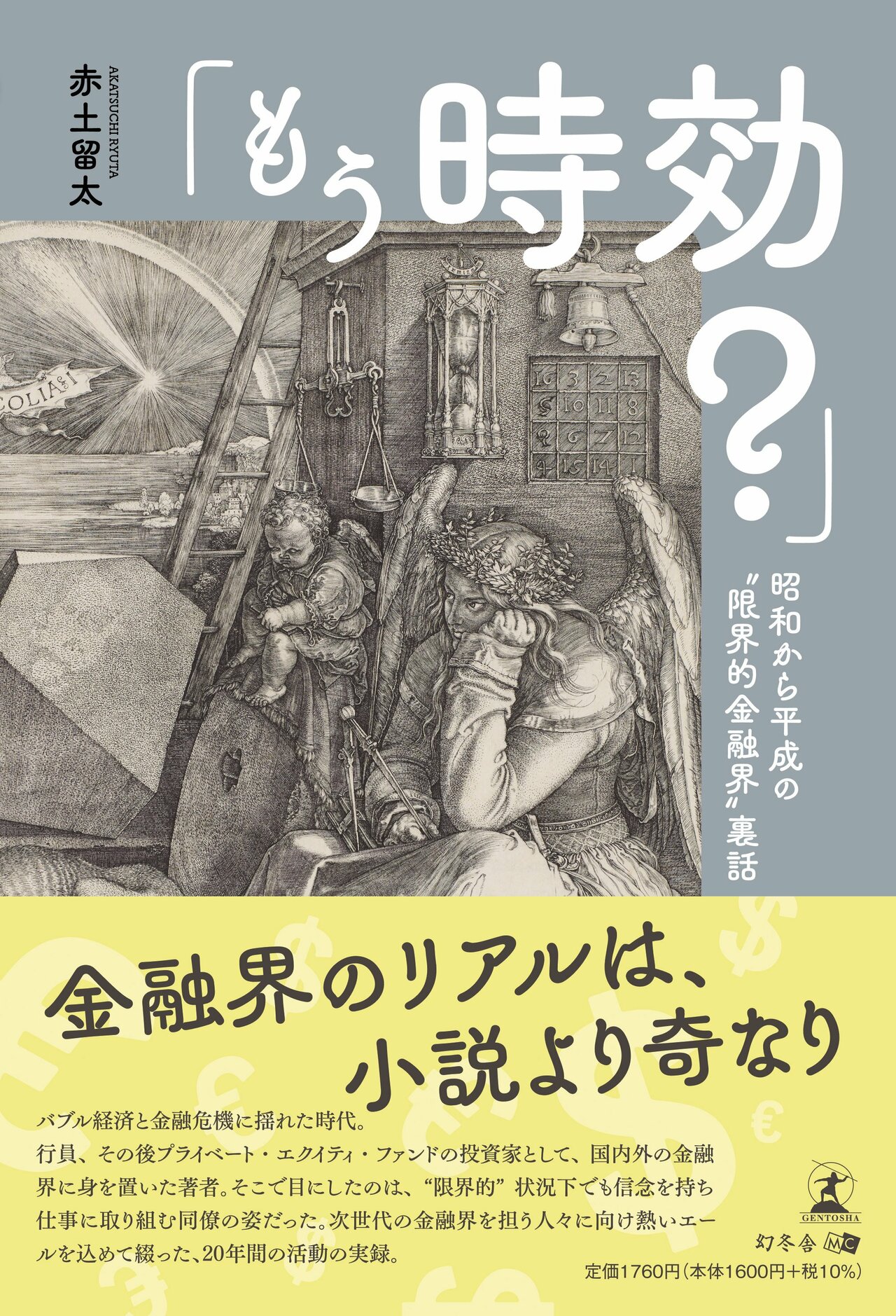【前回記事を読む】「もう時効?」昭和平成 “限界的金融界” 裏話:銀行はリース業務禁止のため、そこに当行の名は一切出ない。ただし…
はじめに
1.Lloyds Bank 劣後債案件
さて、③の問題である。証取法 65 条のせいもあって、銀行内でも、資本市場部門と一般ファイナンス部門はチャイナウォールで仕切られていて、部門間の競争意識も高かった。
関係する部門が多く、行外の関連会社迄含めるとあちこち調整し、その都度合意を得て進めて行かなくてはならなかったので、最悪外部の UBS に引受業務を委託すれば良いか、とのコンセンサスで、営業企画部の入行同期の担当者と馬を合わせ、先の関連事業部次長、審査部の審査役の大いなるバックアップを得て、詰められるところ迄詰めた。
与信案件が申請される前に、“このリース会社には幾ら与信余力があって、取引採算がこれだけ改善するから○○円のローンを○○の条件で出せる” 等という基準が事前に審査担当部より営業担当部へ出されること自体、異例であったし、関係者全員のwin-winベースになる(全ての当事者にメリットになる)本来の銀行の審査機能を発揮すべき姿であると、大いに感激したことを覚えている。
シンジゲート団の組成に目途が付き、発行体の Agent である UBS を通じ Lloyds Bank とも条件の折合が付き、スキーム全体についても外部弁護士による Legal Opinion(法律意見書)で go サインが出たのを見計らって、証券業務を統括する資本市場部を、案件の説明と、ロンドンの証券子会社による劣後債引受業務を行う意志と能力があるか確認のために、営業企画部の同期と 2 人で訪れた。
対応に出た入行年次が数年上の調査役は喜んで、「設立間もなく実績のない英国子会社にとって好機なので、体制を整える様に部内を説得する」と即答してくれ、その時は良い雰囲気で面談を終えた。
席に戻って 30 分程した頃、上司の部長のところに電話があって、「一緒に4階に下りて来い !!」(資本市場部は4階、我々の部は7階にあった)とのことだった。