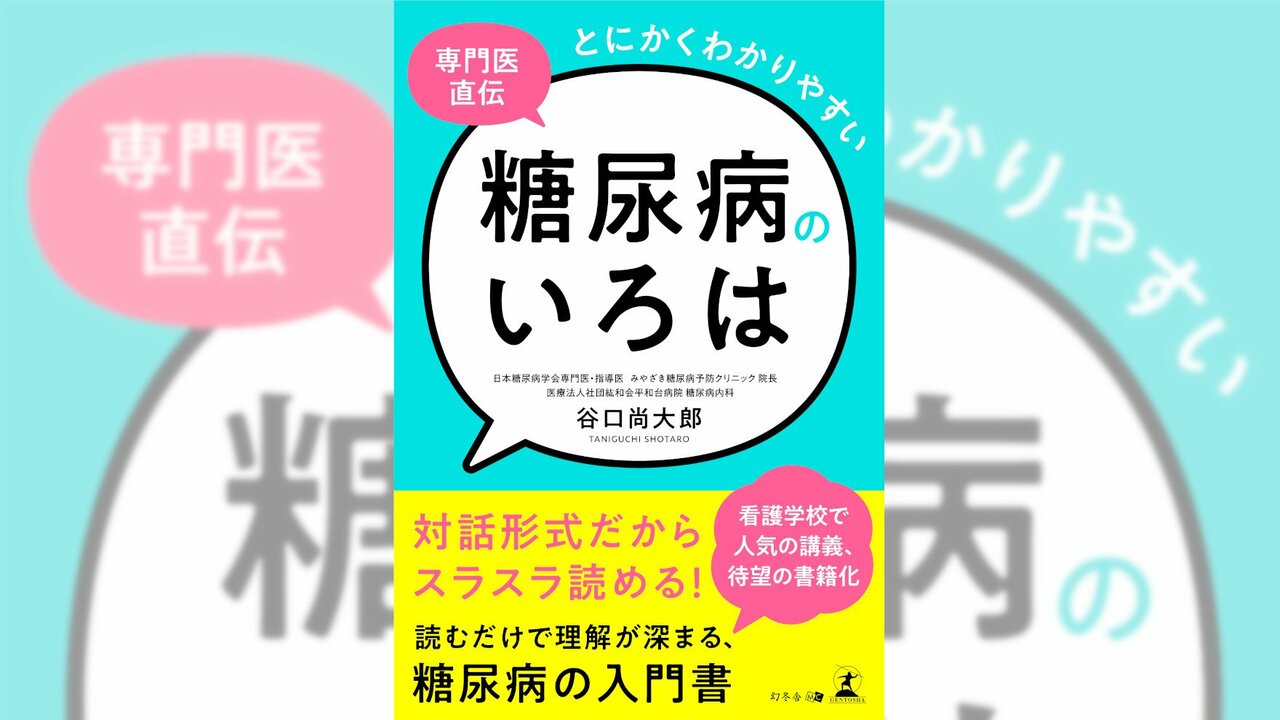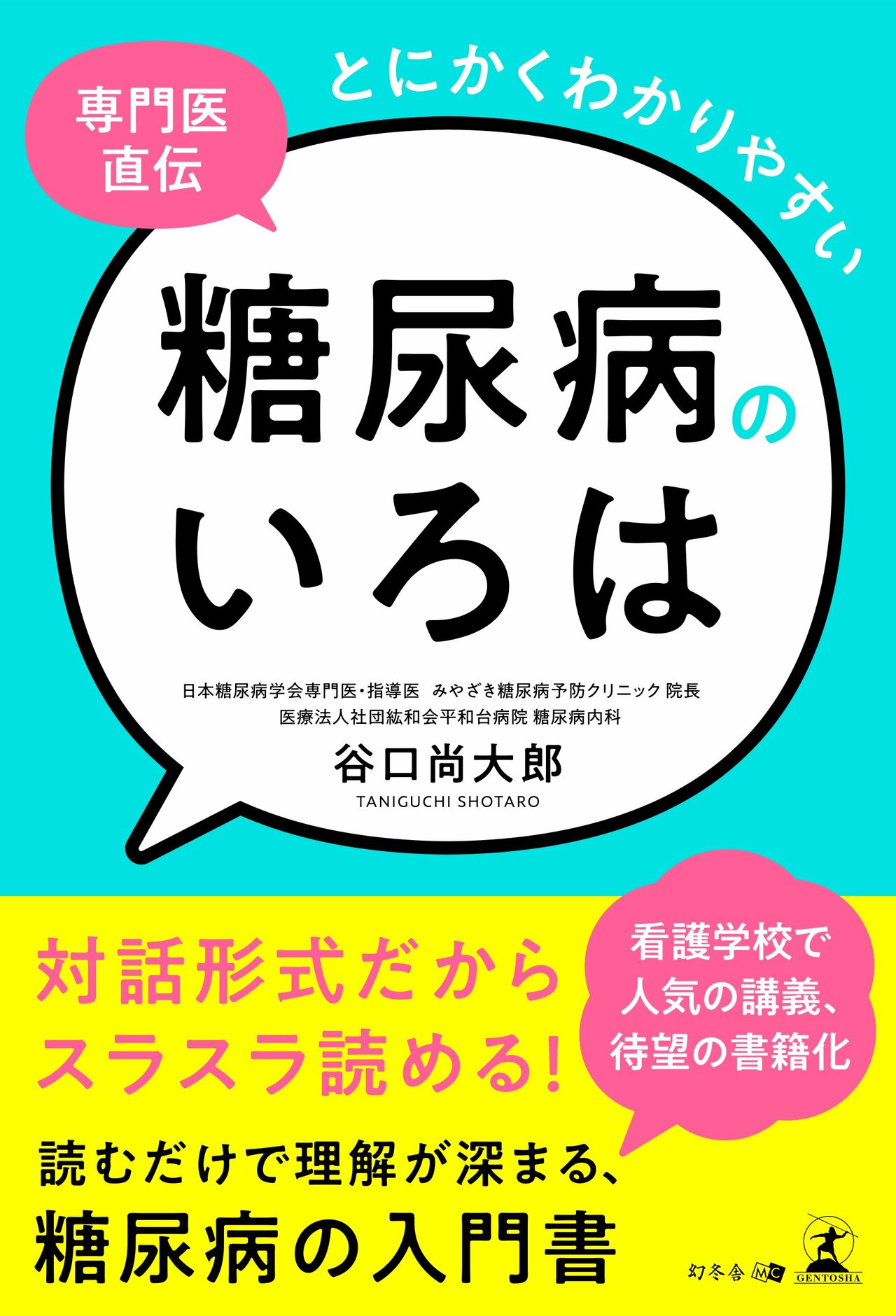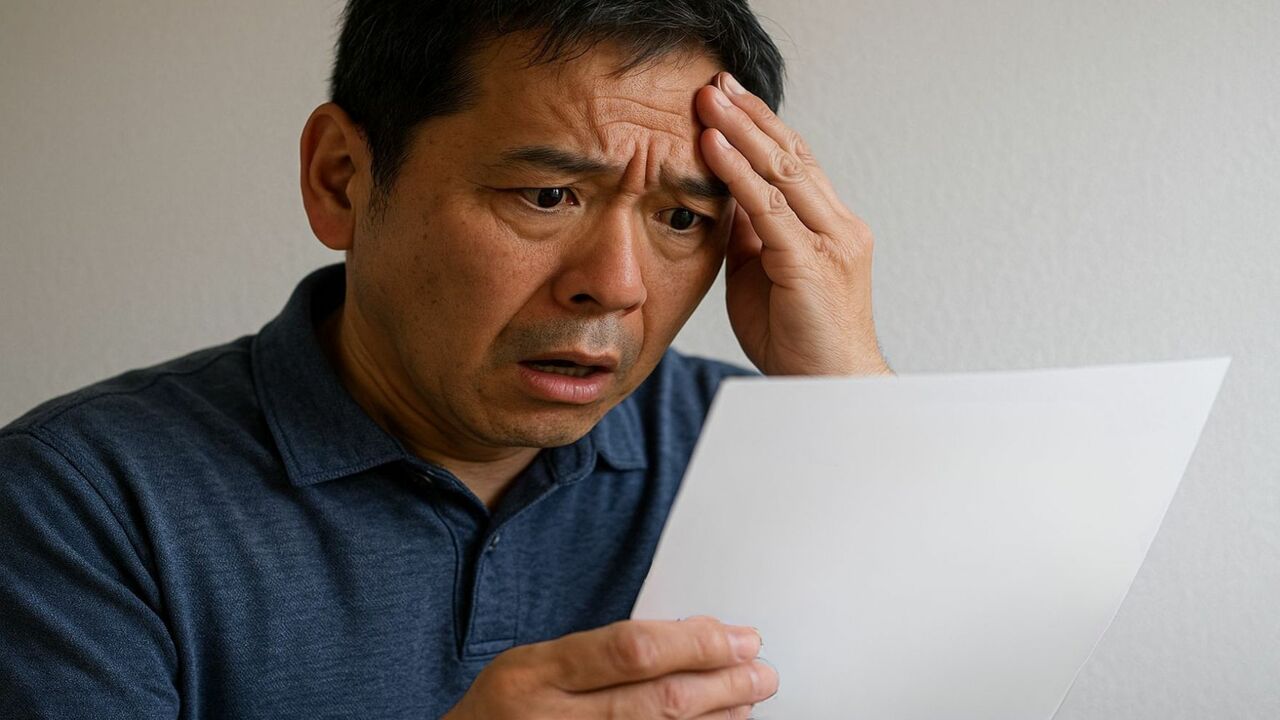【前回の記事を読む】現在の基本治療はインスリン注射だが将来は注射以外の選択肢も……?
第1章:糖尿病の病態・疫学
15. 糖尿病を一文で表現すると
M: 糖尿病の病態をお話ししていこうと思います。病態を一文でシンプルに表現すると「インスリンの働きが悪くて血糖値が高くなる病気」となります。
A: インスリンがしっかり働いてくれないから、血糖値が高くなる。何となく分かるのですが、インスリンの働きが悪いという表現がピンときません。
M: インスリンの働きが悪くなる理由は、大きく2つに分けられます。1つはインスリンの量が足りないから、もう1つはインスリンの質が悪いからです。
A: インスリンの量は何となく分かるのですが、インスリンの質というのは初めて聞く言葉です。インスリンにはA級品とかB級品とか、質があるのですか?
M: すごくユニークな発想ですが、実はインスリンそのものの質が悪いのではなく、インスリンをキャッチする受容体の質が悪くなるんです。
A: インスリンの受容体……、受容体って何でしょう(涙)。
M: 急に話が難しくなってしまいました! それでは理解を深めるために、インスリン作用の仕組みからお話ししましょう。
16. インスリン作用の仕組み
M: 糖尿病の病態への理解を深めるために、インスリン作用のメカニズムを説明したいと思います。まず、血糖値が上昇すると、膵臓のβ細胞がインスリンを分泌します。ピッチャーが球を投げた状態をイメージしてください。分泌されたインスリンは血液を介して全身に供給されます。
A: 膵臓というピッチャーが血液中にインスリンという球を投げた感じですね。そうなると、どこかにインスリンのキャッチャーがいるわけですね。
M: 鋭いコメント、ありがとうございます。そのとおり、キャッチャーがいます。キャッチャーのグローブが受容体だと考えてください。受容体を持っている細胞に対して、インスリンが作用します。
A: インスリンはすべての細胞に作用するわけではなく、受容体を持っている細胞に作用するわけですね!