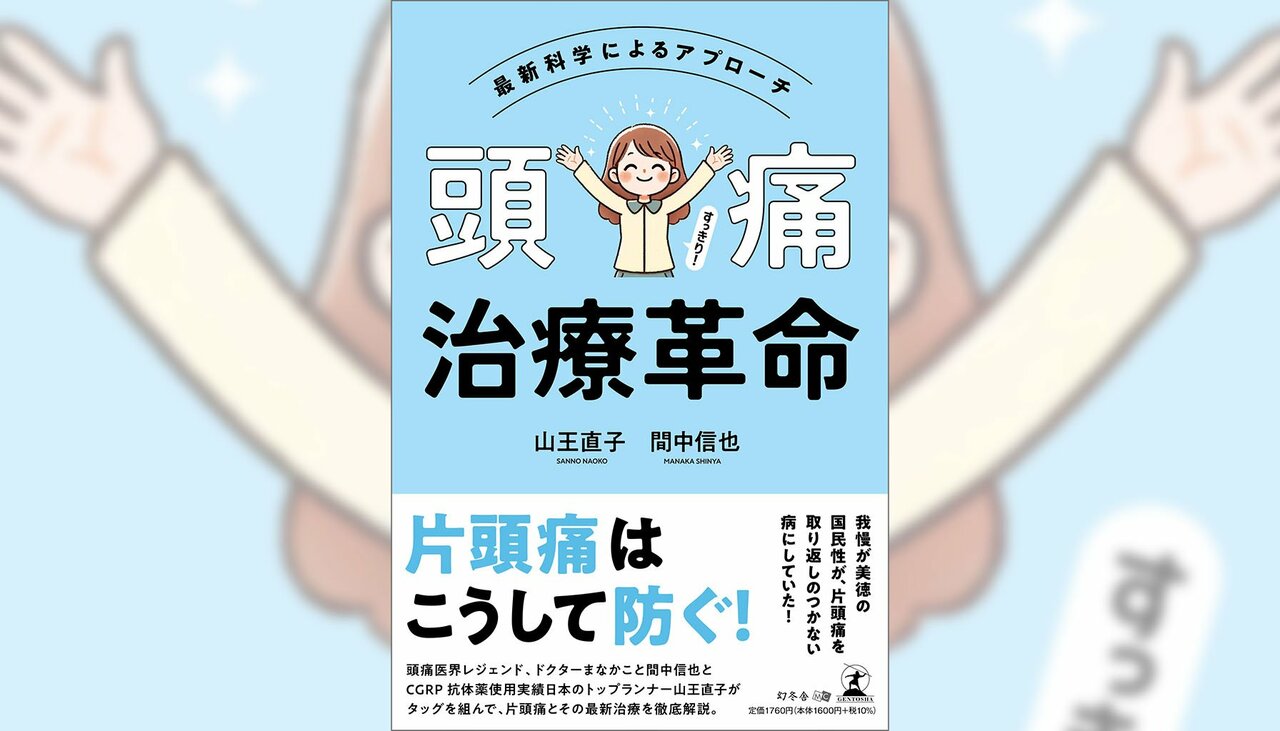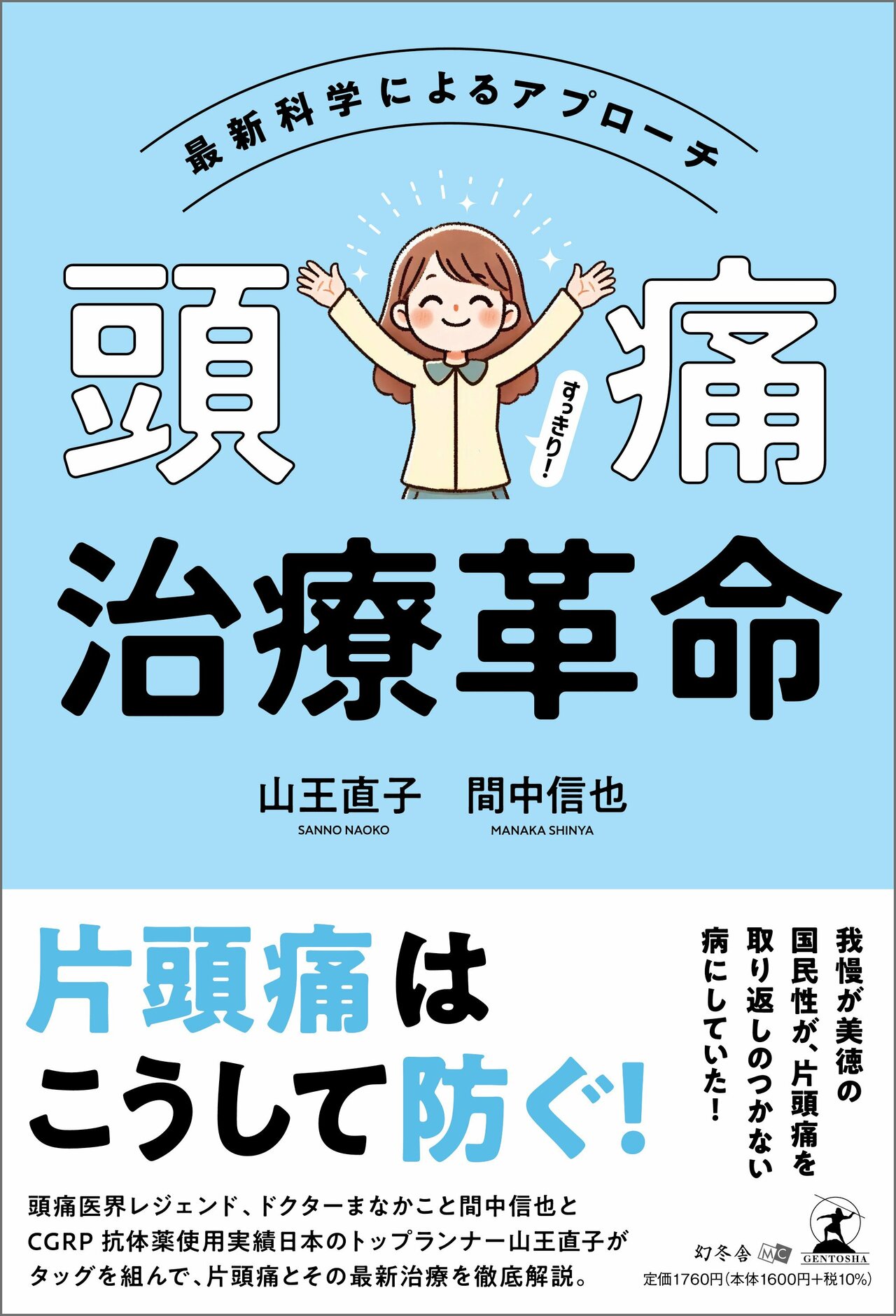【前回の記事を読む】繰り返す頭痛でつらいなと思った時が受診のタイミング!CGRP関連抗体薬の治療を受けるまでの流れを解説
第三章 片頭痛を克服するために~その対処法と実際
10 CGRP関連抗体薬治療を受けるまでの流れ
④予防治療が必要となったらまずは内服の予防薬を服用
抗てんかん薬、抗うつ薬、β遮断薬、カルシウム拮抗薬が内服予防薬として認可されています。
予防治療を開始する目安は、1か月に2回以上、あるいは生活に支障をきたす頭痛が月4日以上で予防治療を検討することが『頭痛診療ガイドライン2021』に記載されています。
頭痛ダイアリーをしっかりと記載しておきますと、予防治療薬が効いているか効いていないかわかってきます。
⑤CGRP関連抗体薬の注射
内服の予防治療薬が無効、効果が不十分、あるいは副作用のため服用が継続できない、体に合わない、という方が対象となります。
3種類ある注射薬のどれを選ぶかは、担当の先生とよく相談して決めましょう。
我が国では、厚生労働省の最適使用推進ガイドラインがあり、以上のようなステップを踏んで注射を行うことが決められています。
⑥抗体薬の注射4週間(1か月)後に必ず受診
注射後に副作用と思われる症状や体調に変化があった場合は、すぐに受診するか電話で相談しましょう。
1か月後の受診では副作用があったかどうか、いつから効いてきたか、頭痛の程度の変化、頭痛に伴う症状の変化、急性期治療薬(消炎鎮痛薬、トリプタン、ジタン)の使用回数などをチェックします。
直近4週間の頭痛日数、頭痛はないがスッキリしない日、スッキリしている日、と共に頭痛の重症度を見る頭痛インパクトテスト(HIT−6)や頭痛がないときの支障を評価するMIBS−4というチェックシートがあります。これをつけていただくことで客観的に評価します。