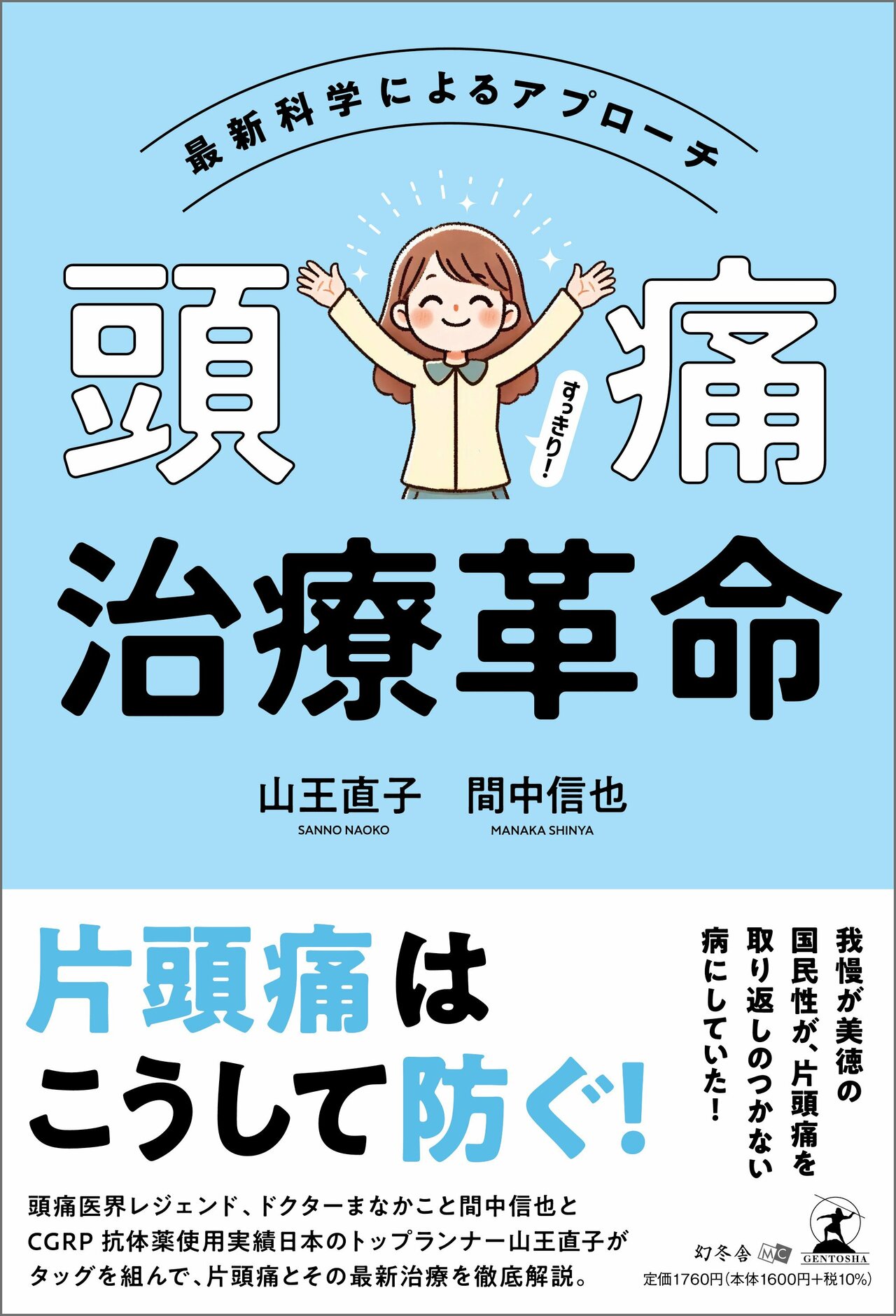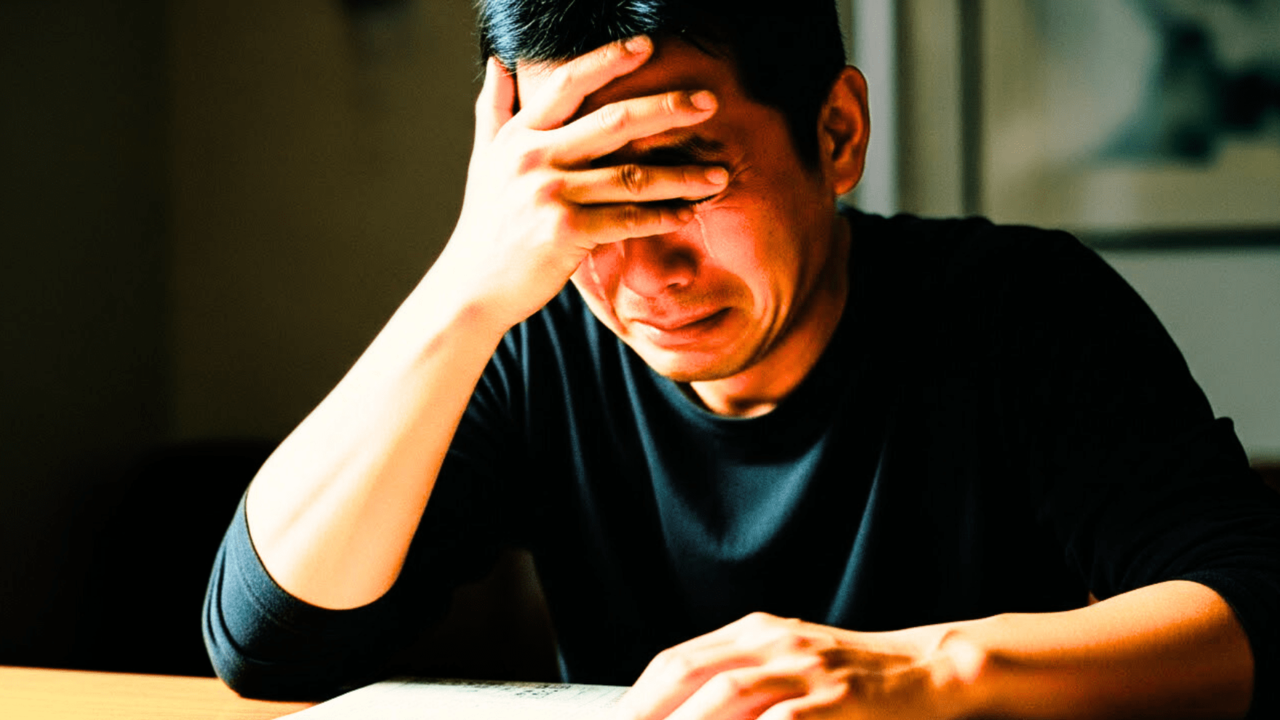第三章 片頭痛を克服するために~その対処法と実際
10 CGRP関連抗体薬治療を受けるまでの流れ
ではCGRP関連抗体薬の治療を受けるにはどうしたらいいのでしょう? 繰り返す頭痛でつらいな、と思ったら受診のタイミングです。
①まず片頭痛の診断
この薬は片頭痛を予防する注射です。片頭痛以外の頭痛には効果がありません。
ご自分で片頭痛です、とか緊張型頭痛です、と診断をしてこられる患者さんがいらっしゃいますが、思い込みは禁物です。
以前にCTやMRI検査を受けて、「異常ないですね、片頭痛でしょう」と医師から言われた、あるいは「ただの頭痛です」とか「肩こりからくる緊張型頭痛でしょう」と告げられたりします。しかし、その時々で状況が変わる場合もあります。
頭痛専門以外の医師の場合、頭痛に対してきちんと学んでいないこともしばしばあります。医学部では、「命に関わらない」片頭痛に関する講義は重視されてこなかったという背景があるのです。
脳外科医は脳の異常(脳腫瘍や脳血管障害、くも膜下出血など)には詳しいし専門性が高いですが、必ずしも頭痛に関するプロではありません。
ですので、頭痛で困ったら頭痛専門医や頭痛治療に熱心な先生を選んで受診してください。近くに頭痛専門医がいない場合は、かかりつけの先生や内科の先生に紹介してもらうとよいでしょう。頭痛学会のホームページからもご覧いただけます。
②クリニック・病院での診察
頭痛外来では問診が重要です。いつからか、前触れがあるかどうか、頭痛に伴う症状(吐き気・嘔吐・光が眩しく感じる・音に敏感・においに敏感)、ご家族に頭痛の方がいるかどうか。女性は月経との関連、特定の誘発因子があるか、など。
曜日の傾向(週末頭痛など)、環境要因、睡眠など事細かに問診を行います。これまでに飲んだ薬なども記入していただきます。
問診票は片頭痛の診断上欠かすことのできないものです。ただし、これまでにない激しい頭痛の時は一刻を争う場合もあります。問診できないほど非常につらい旨を早く伝えましょう。
次に脳や体の病気で頭痛になっていないかどうか、画像診断(CTやMRI)検査を行います。ホルモンの病気や貧血で頭痛が悪化する場合がありますので、血液検査も行います。
③2回目の受診までの間、頭痛ダイアリーを記載
頭痛の記録です。頭痛の程度を+軽度、++中等度、+++重度と記入し、そのときの天候、月経、予兆、前兆(前触れ)、吐き気やめまいなどの気になる症状、誘発因子、外出やイベント、飲酒、睡眠など頭痛に関係あることを記載します。
服用した薬(急性期治療薬)を書いていただき、効いたかどうかも記入すると、診察のときにわかりやすいです。市販薬を飲んだ場合も記入します。
次回更新は7月16日(水)、8時の予定です。
【イチオシ記事】一通のショートメール…45年前の初恋の人からだった。彼は私にとって初めての「男」で、そして、37年前に私を捨てた人だ
【注目記事】あの臭いは人間の腐った臭いで、自分は何日も死体の隣に寝ていた。隣家の換気口から異臭がし、管理会社に連絡すると...