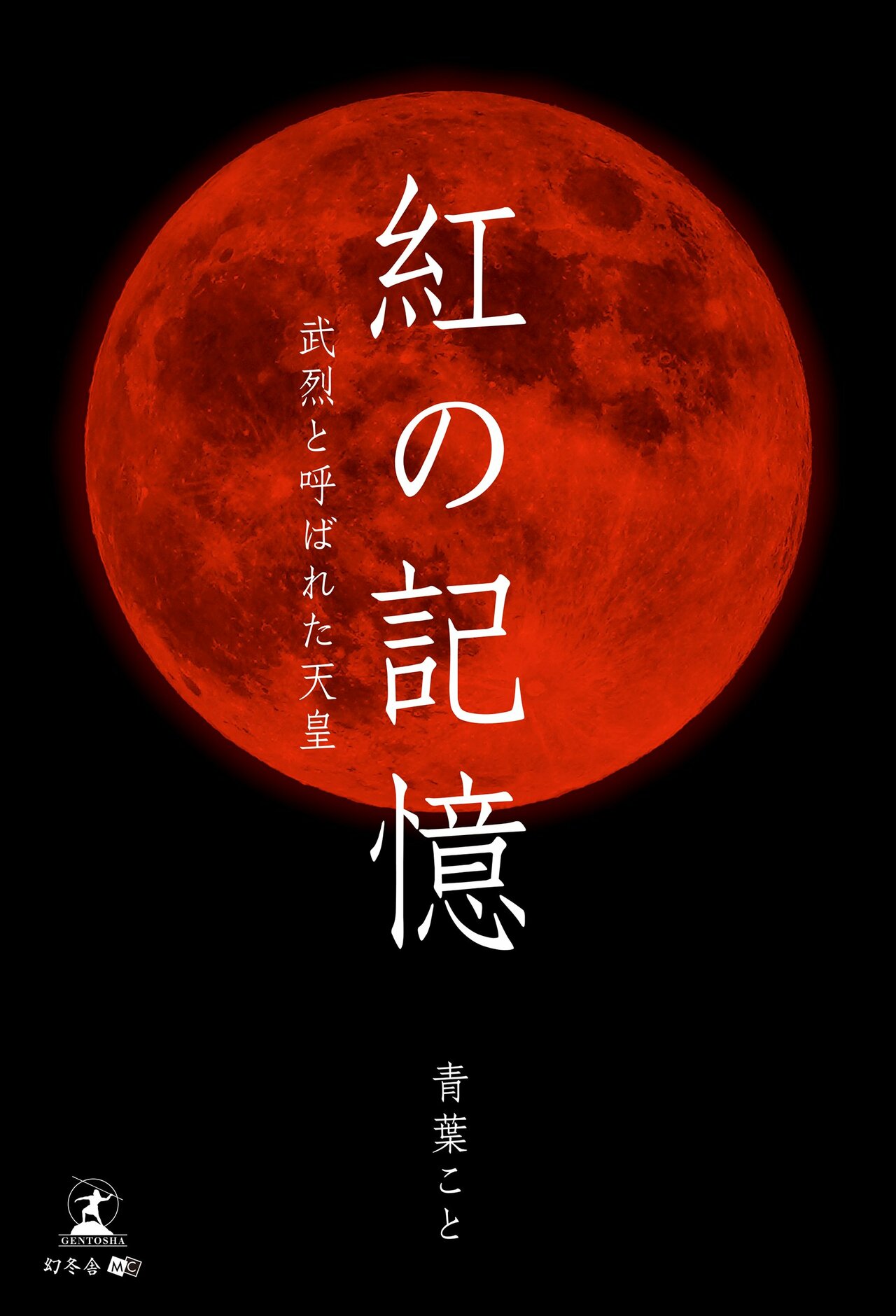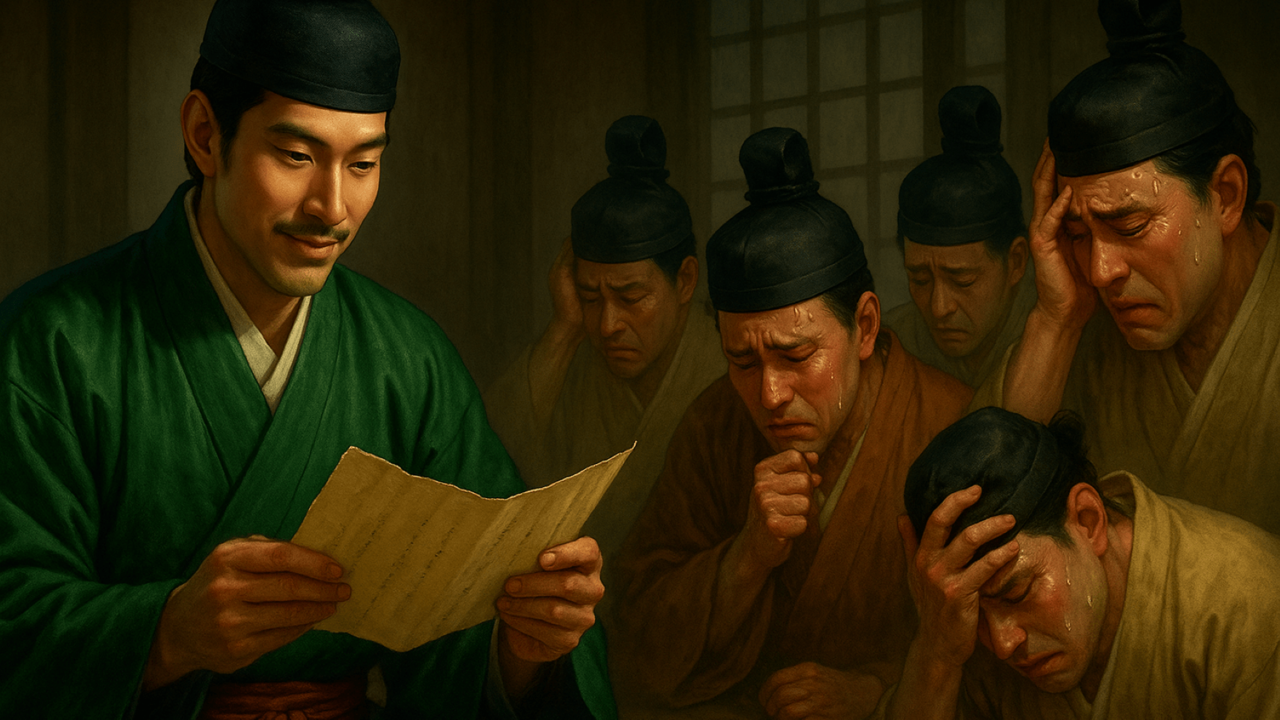そして、彼は歴史書の作成に従事することになった。
天武十年(西暦六八一年)に先代天皇、天武が日本にも国史が必要と明言した。日本の歴史書製作が決まり、これは朝廷挙げての事業となった。
不比等はできあがった文章を検閲する役職に抜擢された。
しかし、国史を作るには大変な労力が費やされる。
日本には神代(かみよ)(初代の天皇が現れるまでの神々が国を治めていた時代)からの長い歴史がある。各地からの伝説や史実が集められ、膨大な量となっている。
加えて、それらのほとんどは文字のない時代の、口伝(くでん)による物語である。何人もいる語(かた)り部(べ)の話を、文字に書き起こさなくてはならない。しかし、文字を書ける者が少ないこの時代。仕事は遅々として進まなかった。
何年続くともわからない、気の遠くなる作業である。それを考えただけでもため息が出る。しかし、ため息の原因はそれだけではなかった。
飛鳥浄御原宮は華やかな正殿(せいでん)を持っている。正殿は中央に鎮座し、周りにいくつもの脇殿(わきどの)を従えていた。
親王の部屋は西側の脇殿の一つ。不比等の仕事部屋は東側にあり、帰るには寒く長い回廊を歩かなくてはならない。
西と東を結ぶ回廊は正殿の裏にあり、北にある内安殿(うちのあんどの)(天皇の住居)の近くを通る。
内安殿は木々に隠されていて、今、その木の葉は赤や黄に鮮やかに色付いている。
しかし、不比等は秋を告げる草木には目もくれず足早に通り過ぎた。
歴史書の作成のために脇殿の一つが与えられ、不比等は一人で使える部屋を持っている。
不比等は部屋に入るなり、ドスンと腰をおろした。
肺の空気をすべて吐き出すほどのため息をつき、机に目をやる。視線の先には巻子本(かんすぼん)が山と積まれているが、それは歴史書の一部でしかない。