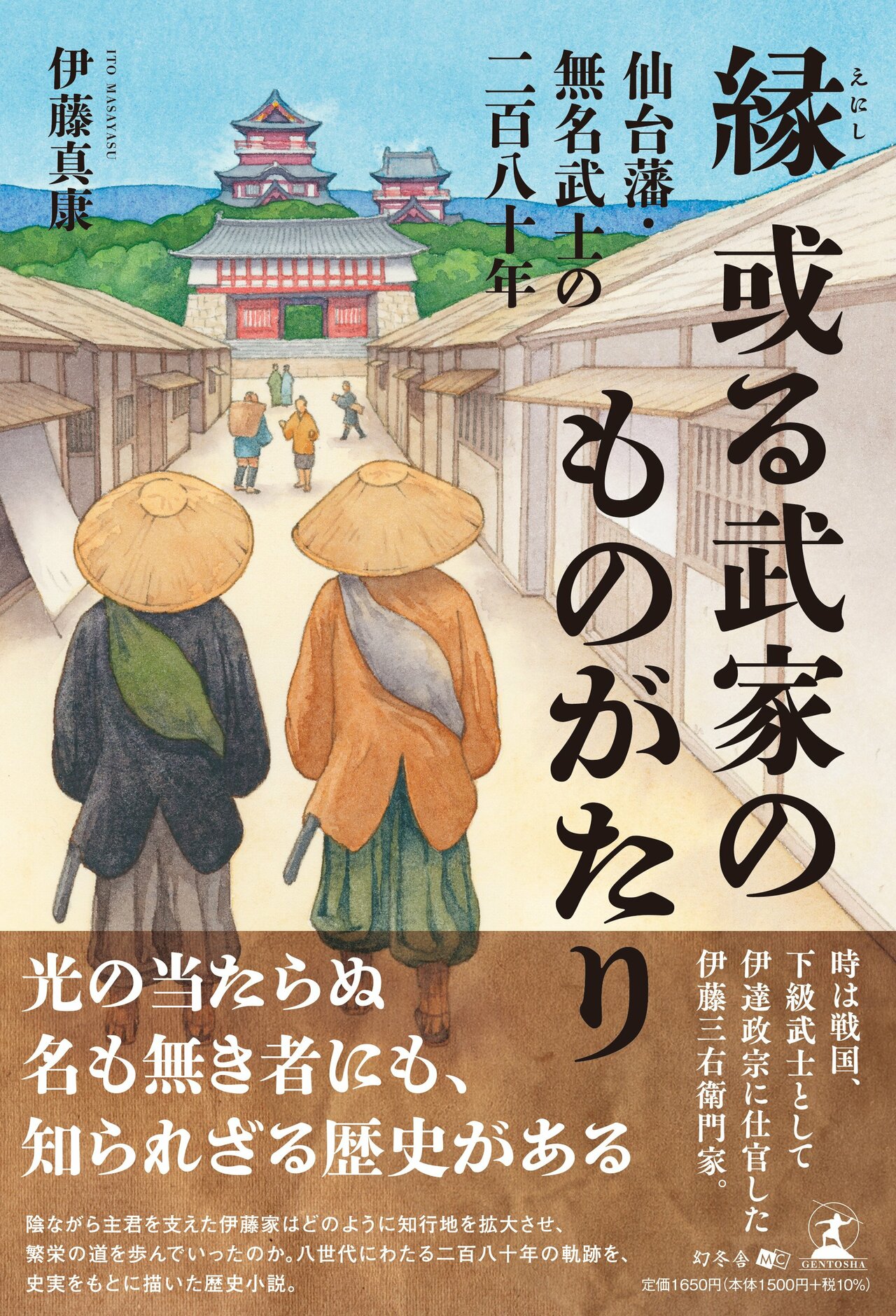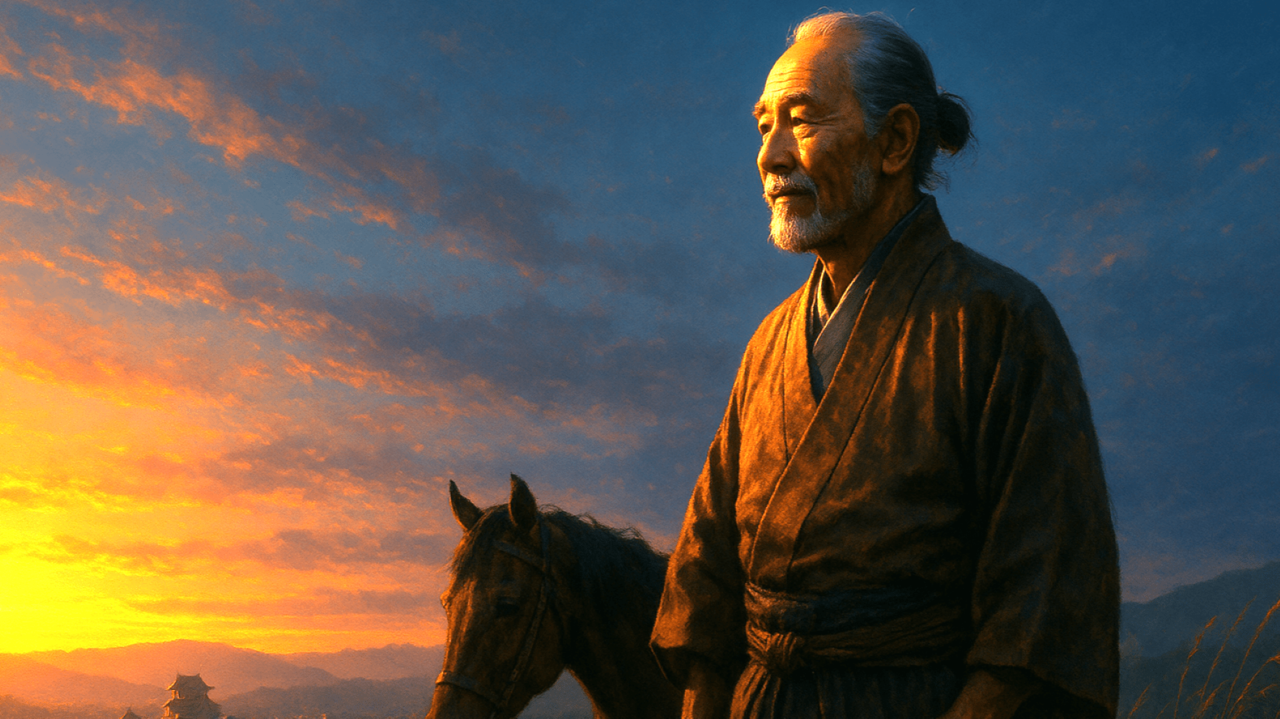盛親はすでに、片倉小十郎に密書を送り、妹と甥らの助命を依頼していたのだ。
小十郎の父、片倉備中守景綱は、かの豊臣秀吉が「我が配下に加えたい」と執拗に伊達家からの引き抜きを画策していた。太閤の執着ぶりに加え、頭脳明晰、器の大きさに慈悲の深さ。かつて伏見伊達屋敷で初めて拝謁した信氏が感服しきりであった、その人間的魅力と名声は、京・大坂一円に染み渡っていたのである。
さらに小十郎は「あれが鬼の小十郎よ」と、すでにその武勇ぶりが大坂一円の戦場に轟いていたことは、前述のとおりである。
あの片倉備中の嫡男にして「鬼の小十郎」なら間違いない……その武力と慈悲の心で、片倉家は必ずや我が女子供らを救い、身の安全を保障してくれよう。長宗我部盛親も、そして真田信繁さえも、小十郎に家族や子供たちを託すべく、密書をしたためていたのだ。
真田信繁の遺児・阿梅(おうめ)と大八(だいはち)が片倉隊に助命され、阿梅は小十郎の後妻に、大八はのち「仙台真田家」の祖に……美談として後世に伝わるが、それはまた別の物語である。
盛親が、片倉小十郎の陣であることを伏せ「釣鐘の馬印」とだけ妹に告げたのは、気位(きぐらい)が高く、容易に敵方に下ることを良しとしない阿古の性格を熟知していた、盛親の心配りであった。
「者ども! こちらにおわす方々は、片倉小十郎様の御客人なるぞ! 乱妨取りとは不届き千万。頭が高いっ! 控えよ! 道を空けんかっ!
ささ、阿古様、我らが陣所へ案内(あない)仕る。お子様方もさぞお疲れでありましょう。握り飯も汁も、湯も用意してござる。替えの着物もありますぞ。敵方といえども、心配召されるな。遠慮は無用でござるぞ。我が殿に一度刃を向けようとも、いずれ必ずや皆残らず味方とする。それが我ら伊達家の流儀じゃ。はっははは!」
老将・信氏の、雑兵どもを威嚇するような野太い声と、優しく諭すような声。そして大きな笑い声。あらゆる表情を見せる信氏の姿は、阿古と二人の幼子の心に長く残った。
【イチオシ記事】妻の姉をソファーに連れて行き、そこにそっと横たえた。彼女は泣き続けながらも、それに抵抗することはなかった