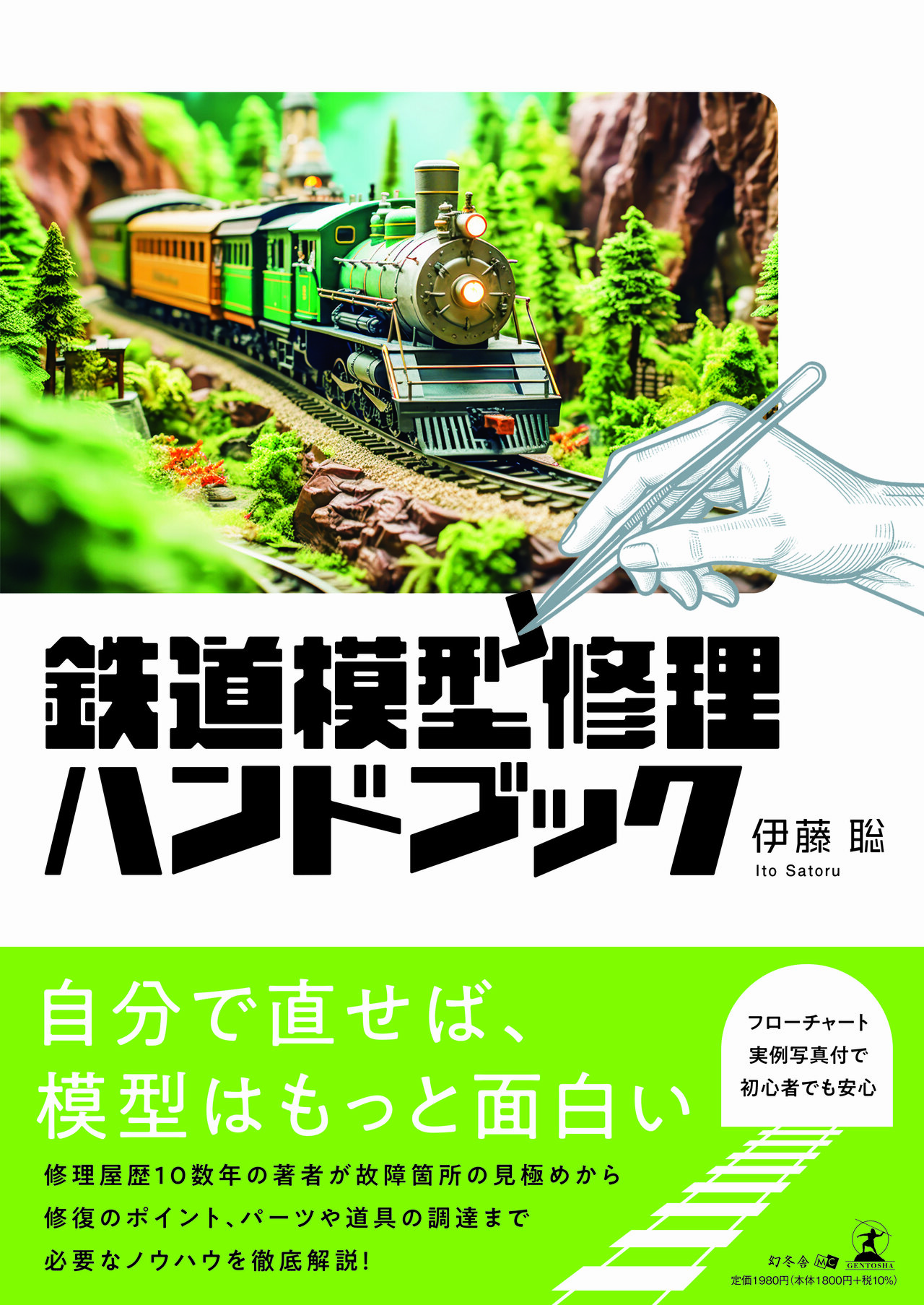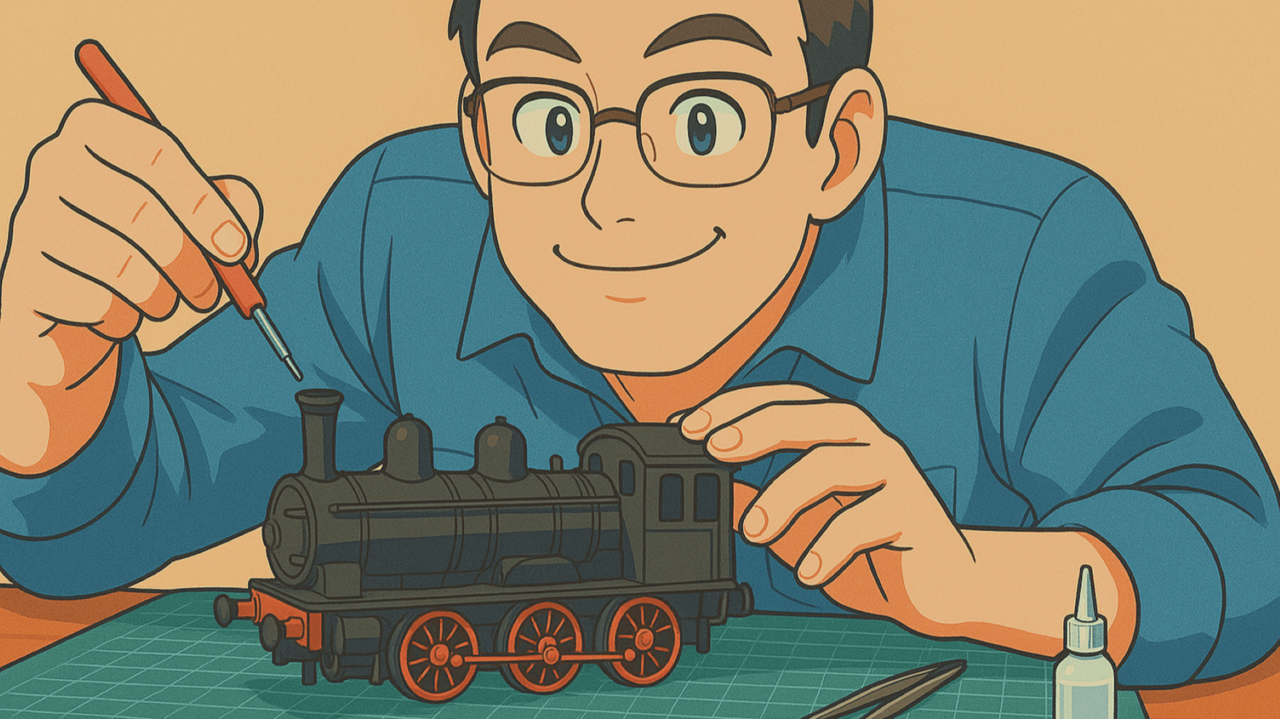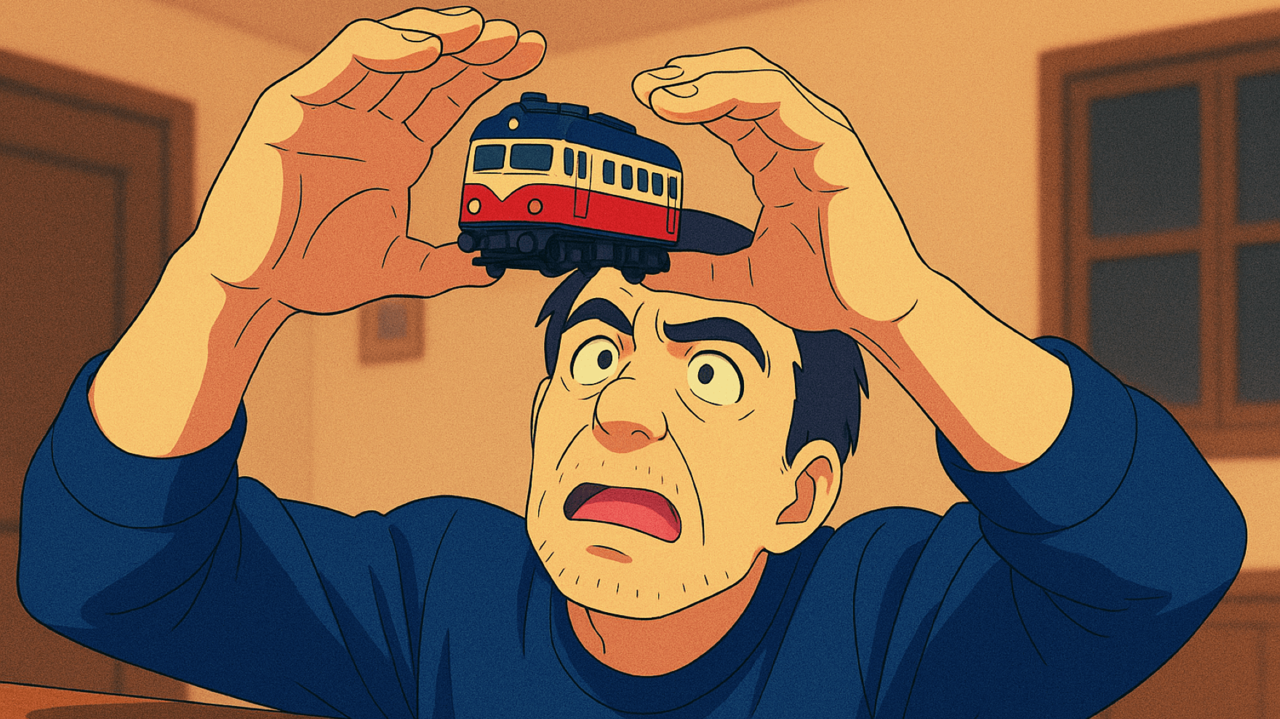3)ギヤ関連
ボイラーと運転席では室内の広さが大きく異なるのでこの空間を利用してモーターを収納する構造が多いです。従ってモーターは車軸に対し斜めに固定されたうえで、ウオームギヤを介して動輪のウオームホイールに伝達されます。
この場合、モーターは横軸型が多く、モーターの軸と連動ギヤの軸を繋ぐゴムジョイントの劣化で空回りするなどで不具合が発生することが多いです。
ギヤ自身ではボックス内のグリスが劣化固化して回転不能になることが意外と多くギヤ自体の損傷は少ないです。ウオームギヤとウオームホイール(ピニオンギヤ)を収納しているギヤボックスとモーター軸を繋ぐジョイント部でのトラブルが、特に劣化してくると多いです。
またギヤボックス内でもギヤ摩耗による空回りあるいは“噛み”が起こって支障をきたします。運転前後でのメンテナンスが重要です。数年に1回程度、メンテナンスをしましょう。
ギヤボックスを外して、金属製の場合シンナーでブラシ洗浄して乾燥させ、新たに非鉱物系のグリスを廻し付けして塗布します。元に戻して噛み合わせをしたところでネジ締めし、ウオームギヤをゆっくり前後回転させ、馴染ませればOKです。
HOゲージ系ではロッドを通じて他の動輪に動力を伝えるのでそれほどではありませんが、Nゲージでは、ロッド類は補完的に機能していて、実際の動力伝達は台車枠内に収納されている連動したピニオンギヤで伝達されていることが多いです。
このギヤはほとんどの場合プラスチック製です。
古くはフェノール樹脂(ベークライト)製が多かったのですが、今ではいわゆる“エンジニアリングプラスチック”と言われるポリアセタール樹脂(POM)、液晶ポリマー樹脂(ポリエステル、LCP)、ポリブチルテレフタレート樹脂(PBT)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリアミド樹脂(ナイロン-66)製などで作られており丈夫です。
とはいえ経時変化や注油の影響、過負荷、または中心軸が金属軸で絶縁されて左右車輪が嵌め込まれている場合などでは位相が“ズレ”やすくなってしまいます。
ギヤ自身も金属軸に圧入されているので割れてしまって空回りする、ギヤピッチが狂って噛んでしまうこともしばしばです。

次回更新は6月5日(木)、18時の予定です。
【イチオシ記事】あの日の夜のことは、私だけの秘め事。奥さまは何も知らないはずだ…。あの日以来、ご主人も私と距離を置こうと意識しているし…
【注目記事】ある日今までで一番ひどく殴られ蹴られ家中髪の毛を持って引きずり回され、発作的にアレルギーの薬を一瓶全部飲んでしまい…