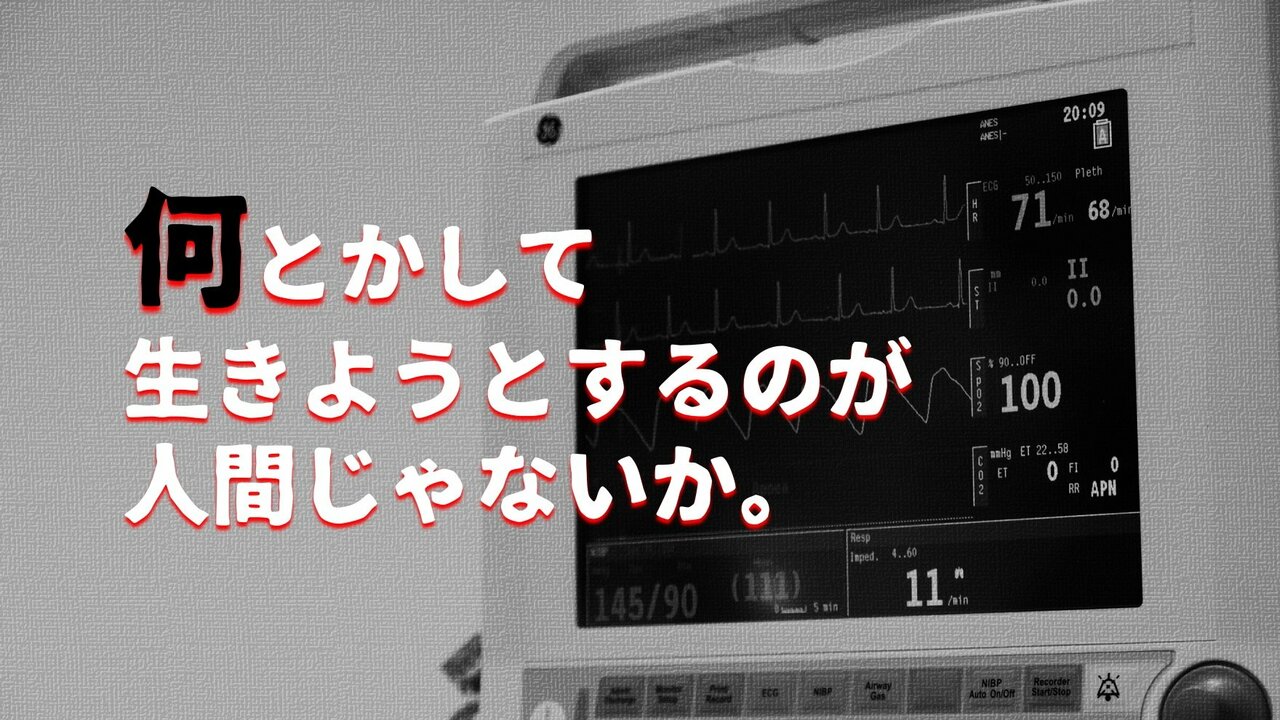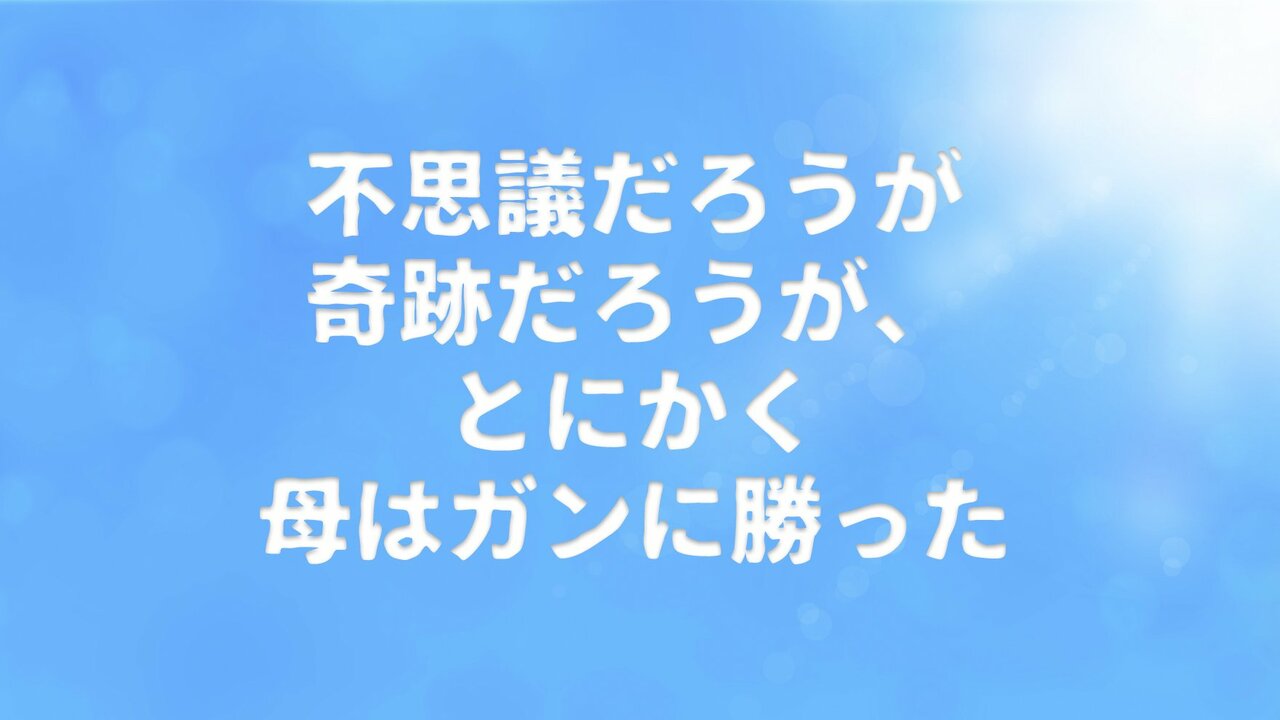第一章 青天霹靂 あと377日
二〇一五年
十一月十日(火) 奈良井総合病院(内科病棟)
「わかりました、それでは抗ガン剤治療(薬物療法)という取り組みはいかがでしょう」
「抗ガン剤だって切ない思いするだけです。ましてや、それで治れば良いけど、治らなけりゃ苦しみ損ってことですよね。私はご免です……」
「苦しいのは一時(いっとき)だけのこと。良くなって落ち着けば、じきに楽になるんだよ」
「一時ったって、本人にしたら耐えらんないもんなんだて。副作用や嘔吐で苦しむのは患者なんだっけ、お前には分からねんだてば!」
返す言葉がなかった。確かに、痛いも苦しいも当人だけのものだ。無用な励ましが、むしろ母の心を傷つけてしまったのかもしれない。それでも、今は何とか説得する言葉を探すよりない……。
「例えば、これが末期のガンや脳腫瘍であると決定されたとして、どんな事をしてもわずかな延命しか望めない……、十二ヶ月の余命が十三ヶ月になるかどうかという程度のものだとしたら、何もしないというのも仕方ないけど、今はまだ、そんな捨て鉢になる時でさえないんだよ。検査でも手術でも、出来る事があるなら辛くても頑張ってやって欲しいんだよ……」
「あんた、やるのはお母さんなんだよ。お母さんは少しの間でも、このまま生きていたいと思うだけなんだて」
「大昔、医療手立てが何もなかった時代なら天命・寿命と諦めたわけだけど、それだって、それなりに出来る事はやったはず。薬草でも祈祷でも……、何とかして生きようとするのが人間じゃないか。そうやって全て拒否するというのは、自殺するのと同じことだぞ。いくら穏やかに楽な余生をと望んでも、結局は苦しむことになっちゃうんだよ……」
「それでも切らない。そう決めたら気持ちが楽になった。これが結論!」
既に母は誰の言葉も耳に入れず、自らの意志だけを頑なに固持しつづけた。
“死”への尊厳……。これは難しい問題である。