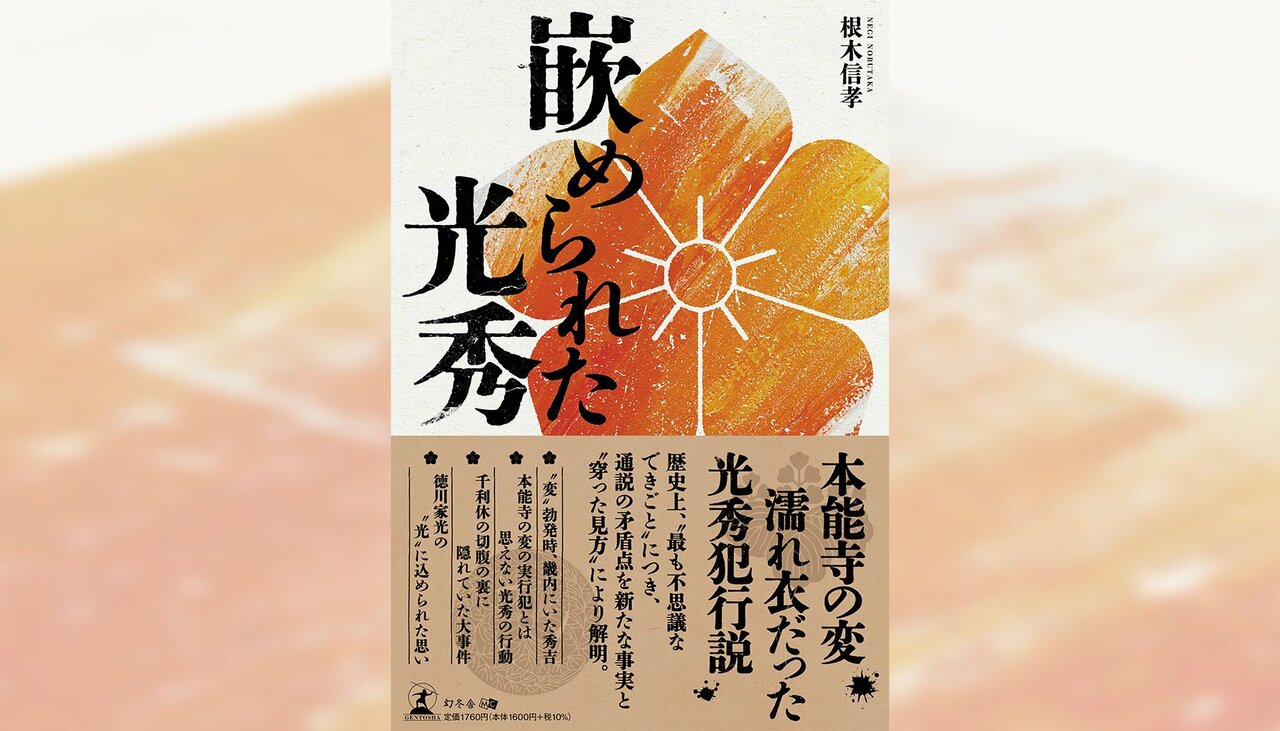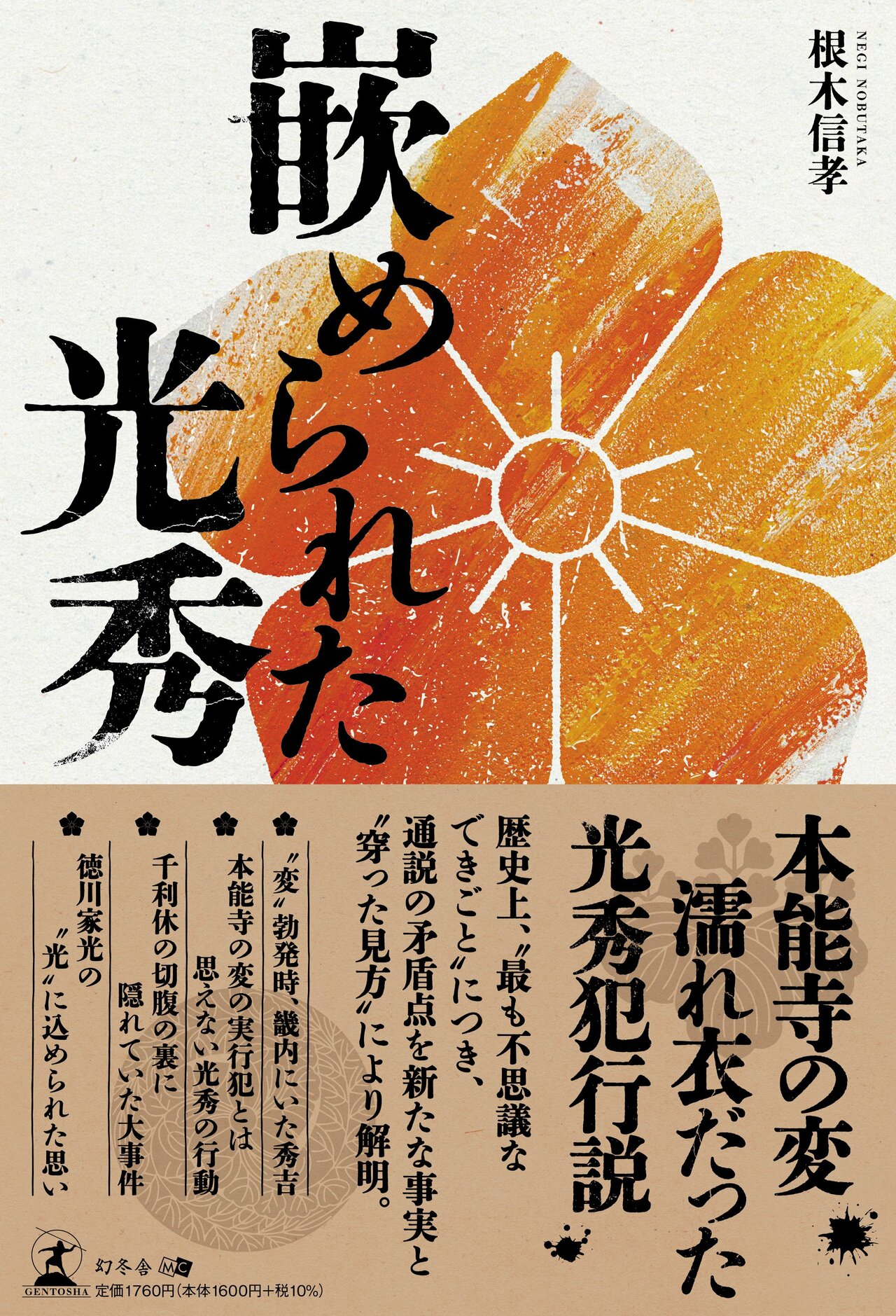【前回の記事を読む】義兄弟に背後から挟み撃ちにされた織田信長! 秀吉にしんがりを命じ、命からがら京へ逃げ帰った。――本能寺の変までの信長の足取り
第一部
2 通説、本能寺の変
本能寺の変については定説が存在しないが、本能寺の変を知らない方のために、本能寺の変について概略を紹介する。通説の中にはこの記載とは異なる説もあるが、いずれも筆者が考える史実(この本のストーリー)とは異なるので、どの説であっても結果は変わらない。
本能寺の変は、天正10年6月2日(ユリウス暦:1582年6月21日)早朝、明智光秀が謀反を起こし、京都本能寺に滞在する主君・織田信長を襲撃した事件とされている。
備中(岡山)の高松城で毛利と対峙していた羽柴秀吉は高松城を水攻めしていたが、その秀吉から毛利方の総大将である輝元が5万の兵で攻めて来るから信長直々の出陣を望むという書簡が5月17日に信長の許に届く。
信長自ら全軍を率いて高松城に援軍に向かって毛利を滅ぼす決意をし、畿内に残っている家臣に準備するよう命ずる。
明智光秀も援軍に向かうよう命令され、居城である坂本城に帰って出陣の準備をし、亀山城に移る。6月1日の夕刻、亀山城を出発した光秀はそのまま備中に向かわず、京に向かう。
信長は出発の直前の6月1日、本能寺で茶会を開き、そのまま宿泊した翌2日の未明、1万3千の兵を率いる明智光秀が本能寺を襲撃した。
信長は寝込みを襲われ、すべての弓を弦が切れるまで引くと長槍を取って応戦したが、勝ち目がないことを悟ると寺に火を放ち、奥の間に入ってすべての戸に畳を立てかけ、自害して果てた。
信長の嫡男で織田家当主の信忠は本能寺から1kmほどの距離にある妙覚寺に宿泊しており、本能寺の異変に気づくと本能寺に向かったが、明智の軍勢に阻まれ、断念。
明智勢に攻められた信忠は妙覚寺の隣の二条新御所に移って抗戦したが、やはり建物に火を放って自害した。
なお、信長・信忠ともに遺体が見つかっていない。
これを聞いた秀吉は直ちに毛利と和睦し、中国大返しと呼ばれる、5日から12日までの
8日間で備中から200km離れた山崎(大阪と京都の間)まで引き返し、6月13日の山崎の戦いで明智と対戦し、勝利する。