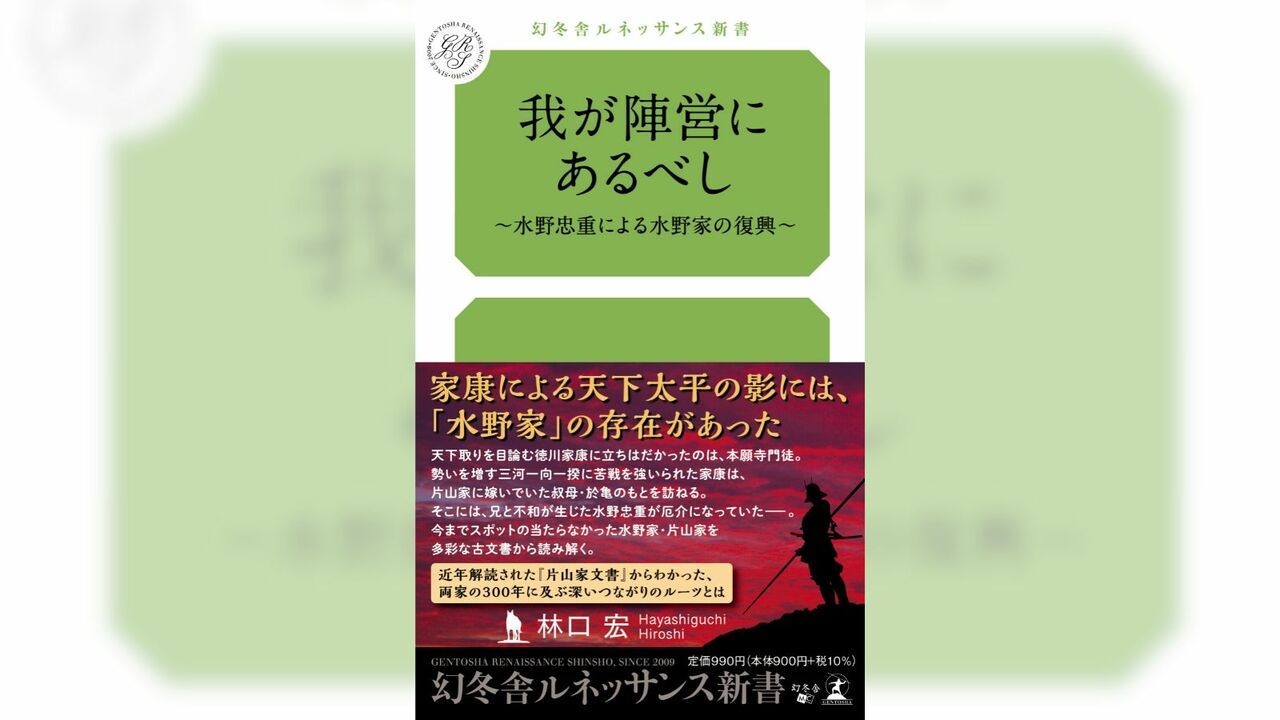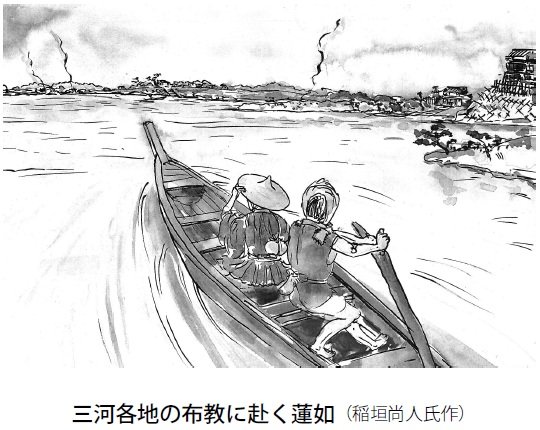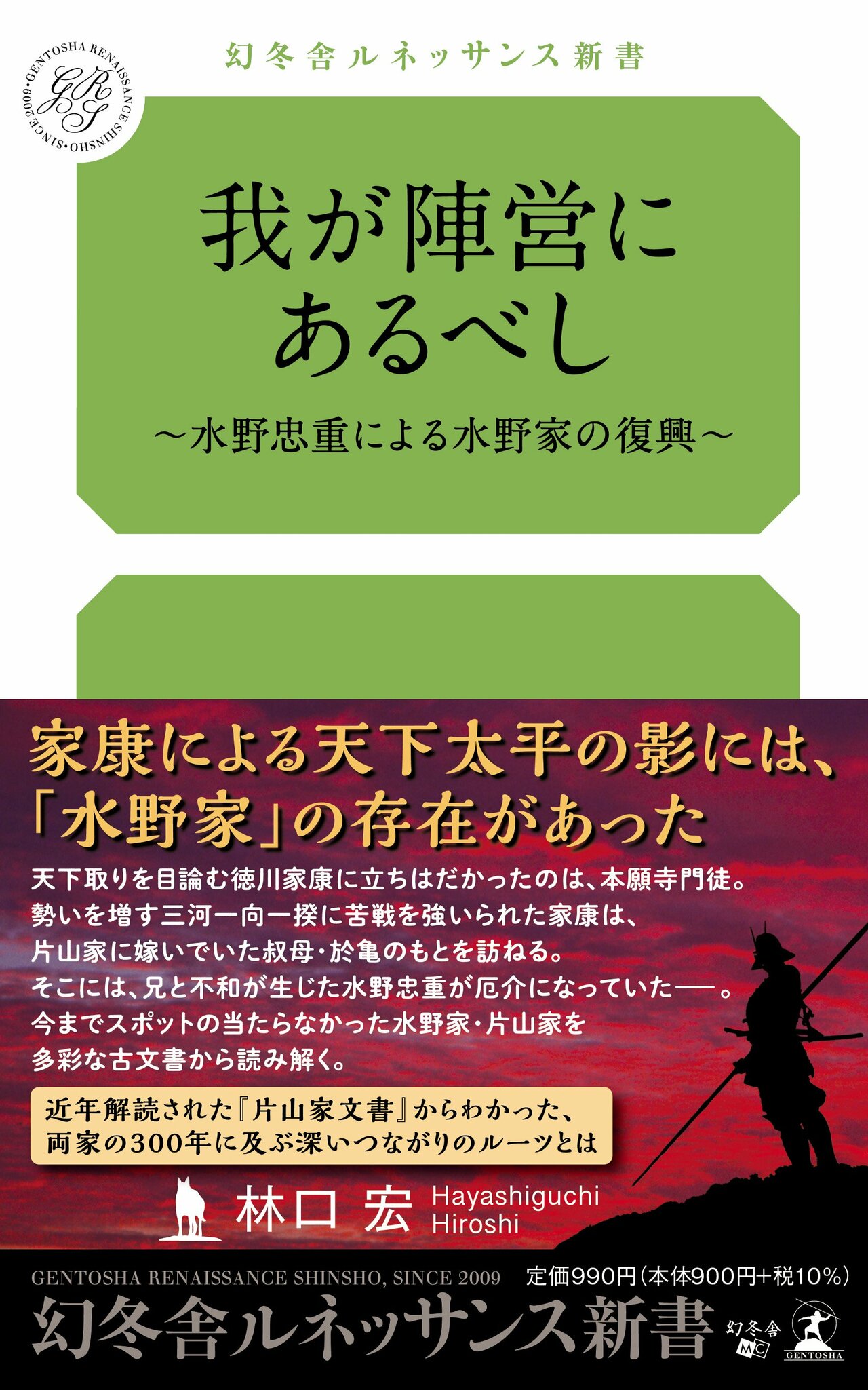【前回記事を読む】蓮如の布教以後、浄土真宗一色に塗りつぶされていった「真宗王国」矢作川流域。この地を治めたのは、徳川家康の祖先である松平氏で…
第一章 主君を求める武勇の片山氏
第一節 戦国時代の矢作川流域
第一項 勢力を拡大する松平家と真宗本願寺派
蓮如は応永二十二年(一四一五年)、京都東山本願寺に浄土真宗宗祖親鸞聖人より七代目の存如 (ぞんにょ)の長男として誕生している。母の名は伝わっていないが、本願寺の下働きをしていた女性との間に生まれたとの説がある。
六歳の時、父・存如が正妻を迎えることになると、母は蓮如に真宗の再興を託して本願寺を去ったとされる。蓮如が育った頃の本願寺は、参詣の門徒がなく衣食にも事欠く有様だったという伝承もある。
存如が亡くなった時、蓮如は四十三才であった。継母・如円(にょえん)は実子を後継者にしようとしたが、叔父が実力で勝る蓮如を強く推薦したため、蓮如が第八代門主となり、以後蓮如の活躍が始まった。
親鸞の説いた念仏の救いを民衆に理解させる方法として蓮如が考え出したのが「御文(おふみ)」であった。これは農民にも分かりやすい手紙文で、各地の「講」の開催時に読まれた。
念仏を唱えることで、男女の別なく、善人悪人、賢い者、愚かな者の別なく、すべての者が阿弥陀仏の救いに預かり、極楽往生を遂げることができるというものである。
蓮如と矢作川流域を結びつけたのは、碧海郡西端村(へきかいぐんにしばたむら)(碧南市)の杉浦一族に生まれた幼名耀栄丸 (ようえいまる)という少年であった。
少年は佐々木上宮寺 (じょうぐうじ)(岡崎市)に養子として迎えられ、如光 (にょこう)の名で活躍した。
彼は蓮如と巡り合うと、真宗高田派から本願寺派へ転向した。また、応仁の乱の頃まで、天台宗の寺院が多かったこの地方の寺院を、まさに蓮如の手足となり、次々に浄土真宗本願寺派に改宗していった。