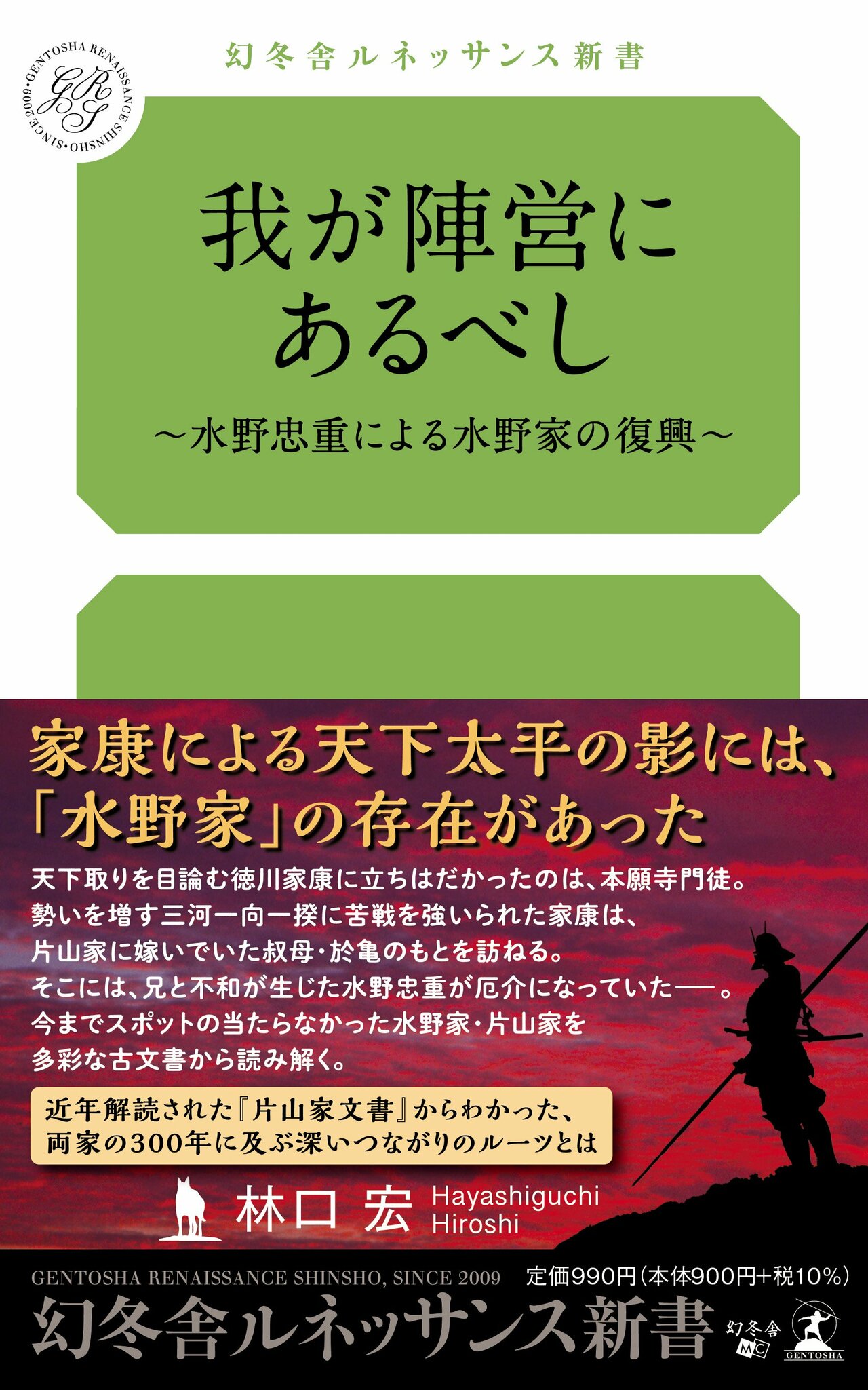第二項 松平長親に仕える片山忠正 (かたやまただまさ)
織田信長の家臣・太田牛一(おおたぎゅういち)は、その生涯を『信長公記 (しんちょうこうき)1』として書き残している。この中で牛一は、信長側から見た三河の大浜村、鷲塚村の様子を活写した。
三河の国端に大浜・鷲塚という海辺の場所に、戦略上重要な湊がある。これらの湊は富を蓄えており、人の数も多い。
大坂石山本願寺は、本願寺九代実如の四男を代坊主として鷲塚御坊に送り込み、門徒は繁昌している。ここにいる者の大部分は本願寺門徒で、一向一揆を起こしたので退治された。(『信長公記』)
この三河碧海郡鷲塚村 (わしづかむら)に片山忠光・忠正親子が移り住み、西条(西尾城)吉良家へ仕え始めた。明応年間(一四九二年~一五〇一年)のことであった。
私の家の先祖、片山四郎頼武 (よりたけ)は、菊池の一族で、肥後の国(熊本県)菊池の住人であった。
建武二年(一三三五年)十月、足利尊氏を追討する官軍にて菊池肥後守武重(きくちひごのかみたけしげ)と同じく、箱根合戦にて功名を立てた。
建武三年の春、官軍は、京都に攻め上ってきた賊軍である足利軍を攻め破る時、新田義貞(にったよしさだ)公の先手になり勇戦した。
新田義貞公から鞘巻 (さやまき)(腰刀の一種)と義貞公の家紋を賜わった。この時から、武具には義貞公の家紋である「大中黒 (おおなかぐろ)の紋」を用いるようになり、後になって、武具には自らの家紋と両方の様式を用いるようになった。
二代親元 (ちかもと)は、応安七年(一三七四年)三月、菊池武政が長門(山口県)で、足利義満将軍の手先と合戦のおり加勢をした。