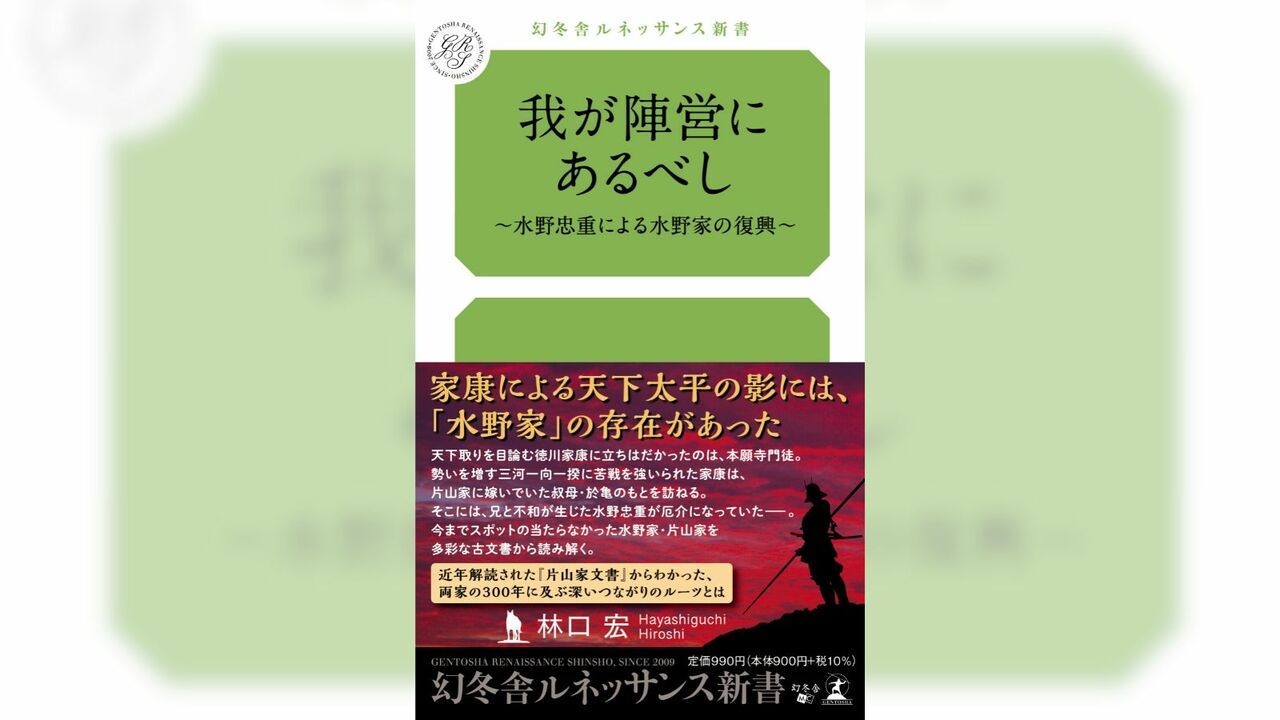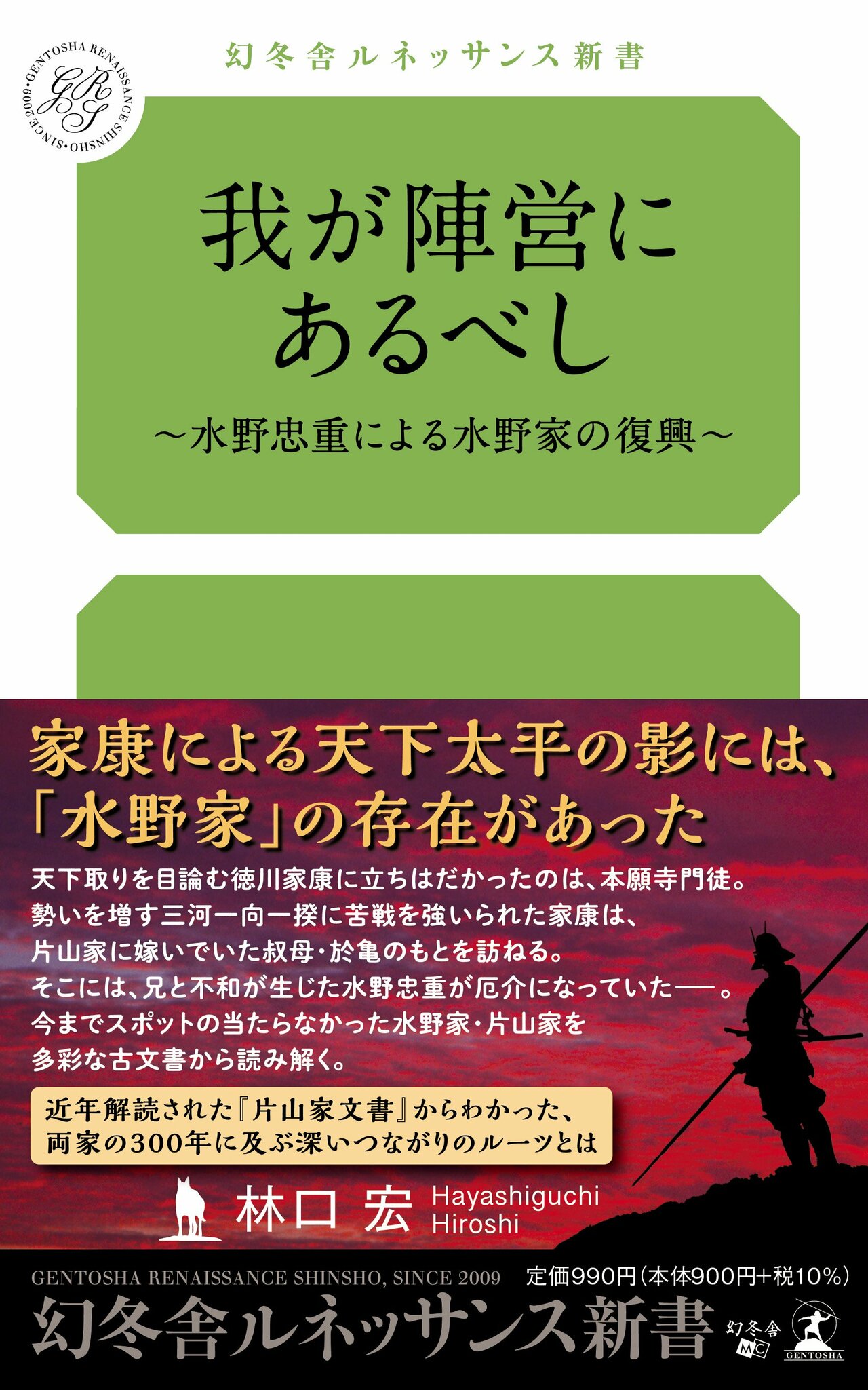はじめに
戦国時代の東海地方は、東には駿河の今川氏、西には尾張の織田氏という強国があった。
そしてその両国に挟まれるように、小大名の松平氏、水野氏が存在していた。両氏ともに領国を守るということは、苦難の連続であった。矢作川中流域では、松平氏が岡崎城を中心に支配し、矢作川下流域1では今川氏と同族2の吉良氏が川の東西をそれぞれ「東条」「西条」と、吉良荘を東西に分けて別々に支配していた。
水野氏は境川(さかいがわ)3右岸、尾張国知多半島北部を支配し、緒川城(おがわじょう)を拠点としていた。水野(みずの)清忠(きよただ)の次男・水野(みずの)忠政(ただまさ)は、天文二年(一五三三年)三河国刈谷に新城刈谷城を築き、三河松平氏側へ次々と娘を嫁がせ領国を守ろうとした。
忠政の娘で十四歳になる於大(おだい)は、天文十年(一五四一年)に十六歳の松(まつだいら)広忠(ひろただ)のもとに嫁いだ。翌年には竹千代(家康)を出産している。
忠政の娘とされる女性の総数は、後の時代に記述された家系図で異なり、六名とするものや七名とするものがある。忠政の娘で三河松平側へ嫁いだ女性は、家康の母・於大の他に石川(いしかわ)清兼(きよかね)に嫁ぎ妙春尼(みょうしゅんに)となる女性や形原城主松平(まつだいら)家広(いえひろ)に嫁いだ於丈(おじょう)の方がよく知られている。
本書の目的は、まず忠政の娘で三河松平側へ嫁ぎ、従来はほとんど知られることがなかった四人目となる女性、於亀(おかめ)の方が存在したことを明らかにすることである。次に於亀の方が嫁いだ鷲塚村『片山家文書』4を根拠に、同家が屋敷に牢居していた水野家の人々と三河一向一揆という難局にあった家康を結びつけたことに光を当てることである。
片山家の地元となる碧南市では、昭和三十年(一九五五年)頃、『碧南市史』第一巻の編纂が始まり、碧南市史編纂会は片山家に伝わる文書の存在を確認した。しかし、その内容の解読までは踏み込む時間がなかったようで、片山家について記述されることはなかった。
平成八年(一九九六年)には、同家に愛知県史編さん室の調査が入り『片山家文書』の史料目録までは作成されている。しかし、膨大な古文書の解読や同家の歴史的位置づけはなされなかった。