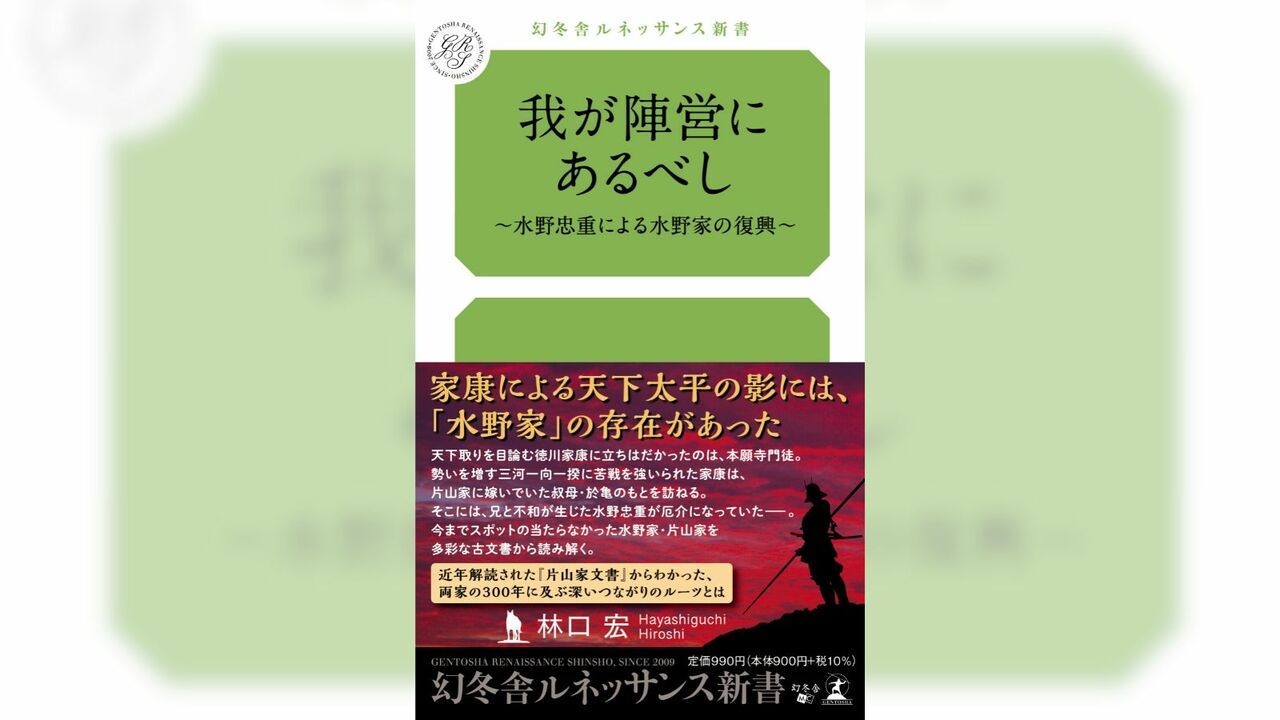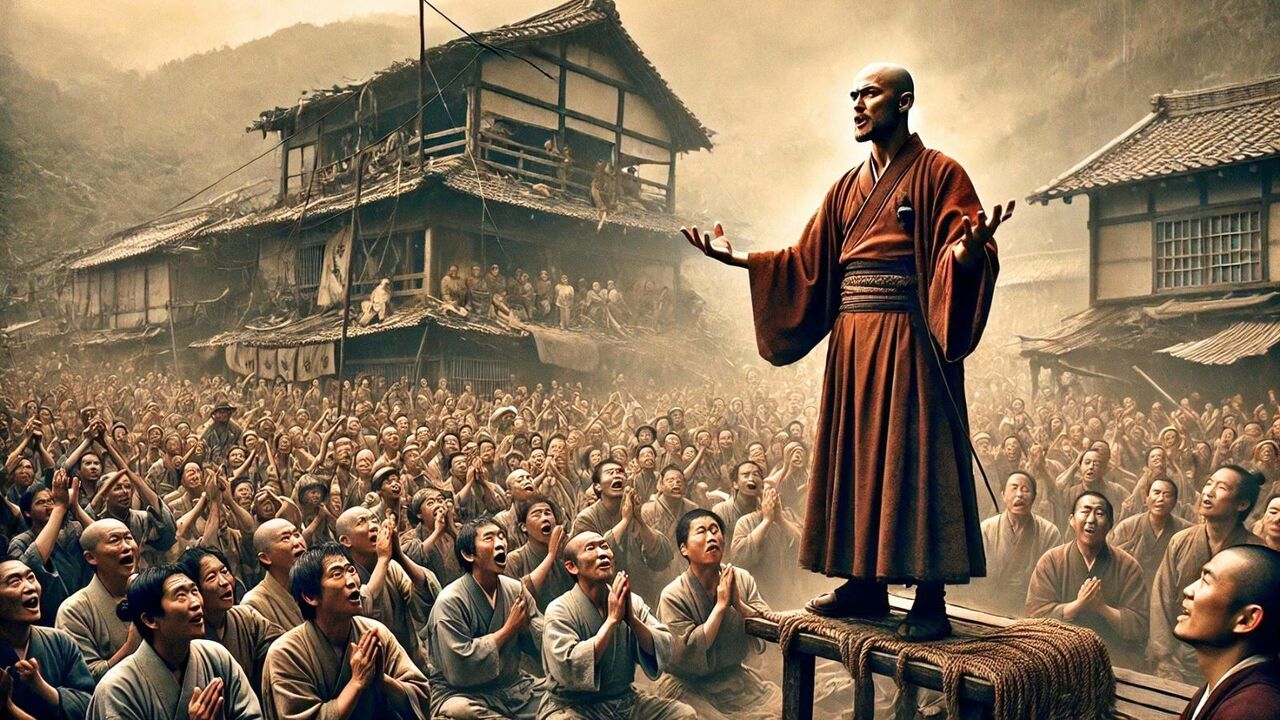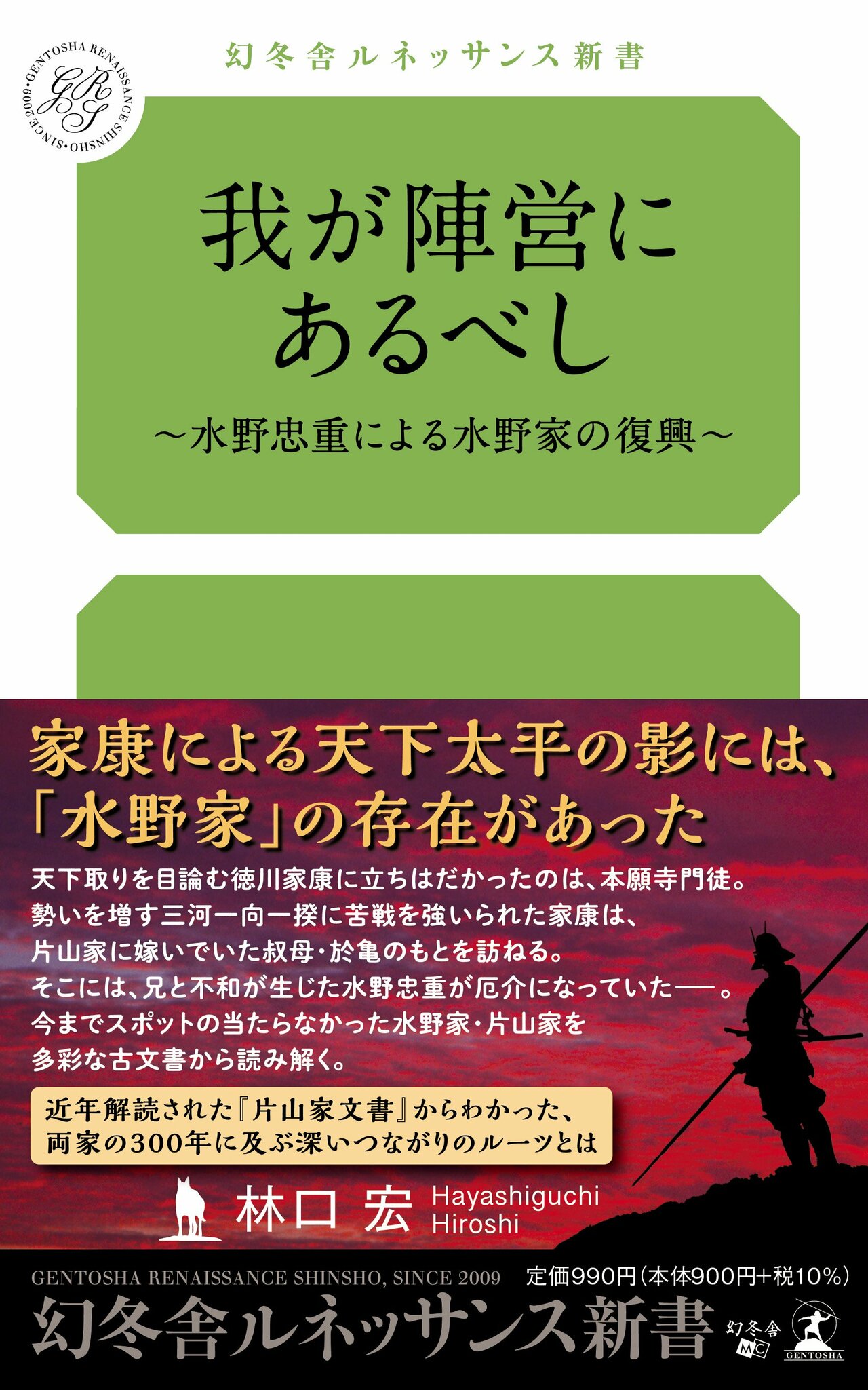【前回記事を読む】徳川家康・天下太平の影に三河牢人!? …300年以上続く「徳川家」「水野家」の協力関係、その始まりの言葉が「我が陣営にあるべし」
第一章 主君を求める武勇の片山氏
第一節 戦国時代の矢作川流域
第一項 勢力を拡大する松平家と真宗本願寺派
古代三河の国は、茶臼山(ちゃうすやま)山頂から三ヶ根山にかけて尾根の東側となる豊川流域が「穂国(ほのくに)」と呼ばれ、尾根の西側となる矢作川流域が「三河国(みかわのくに)」とされていたという。「穂国」はその名の通り豊かな実りのある地域であった。
大化の改新以後、「穂国」と「三河国」は合併し「三河国」となったが、国府、国分寺、国分尼寺、さらに天台宗、真言宗などの寺院は豊川流域に集中していた。現在は、豊橋市、豊川市、蒲郡市などから構成され東三河と呼ぶことが多い。豊川流域の人々は、地域の豊かさ故か気質が穏やかで日々の会話はゆっくりだ。
一方、矢作川流域は川の右岸に碧海台地が広がり水が乏しいことから、溜池、井戸が無数に存在する地域であった。日照りの年など、溜池の灌漑(かんがい)用水の配分を巡って村と村の「水喧嘩(みずげんか)」「水論(すいろん)」が多く見られた。
戦国時代までの矢作川左岸は、河口の吉良近くまで山が迫る地形で耕地には恵まれなかった。人々は、自然にたくましく、質素で飾り気を求めない気質が育まれた。また、この地域においても天台宗の寺院が多数見られ、中世の三河では神仏習合ともいえる熊野信仰1も盛んであった。
応仁元年(一四六七年)、京都で有力守護大名の抗争が始まると戦乱は諸国へ波及した。この大規模な混乱は、各階層に下剋上の風潮を広げることになった。三河では、細川氏、松平氏、西条吉良氏が東軍側、一色氏、戸田氏、東条吉良が西軍側となり争いを繰り返した。
国内各地で農民が領主に対し一揆を起こし、家臣が主家に代わって守護大名、戦国大名となることが起こり始めた。矢作川流域においても群雄が割拠し激しく争ったが、その最後に勝利を得たのは松平氏であった。