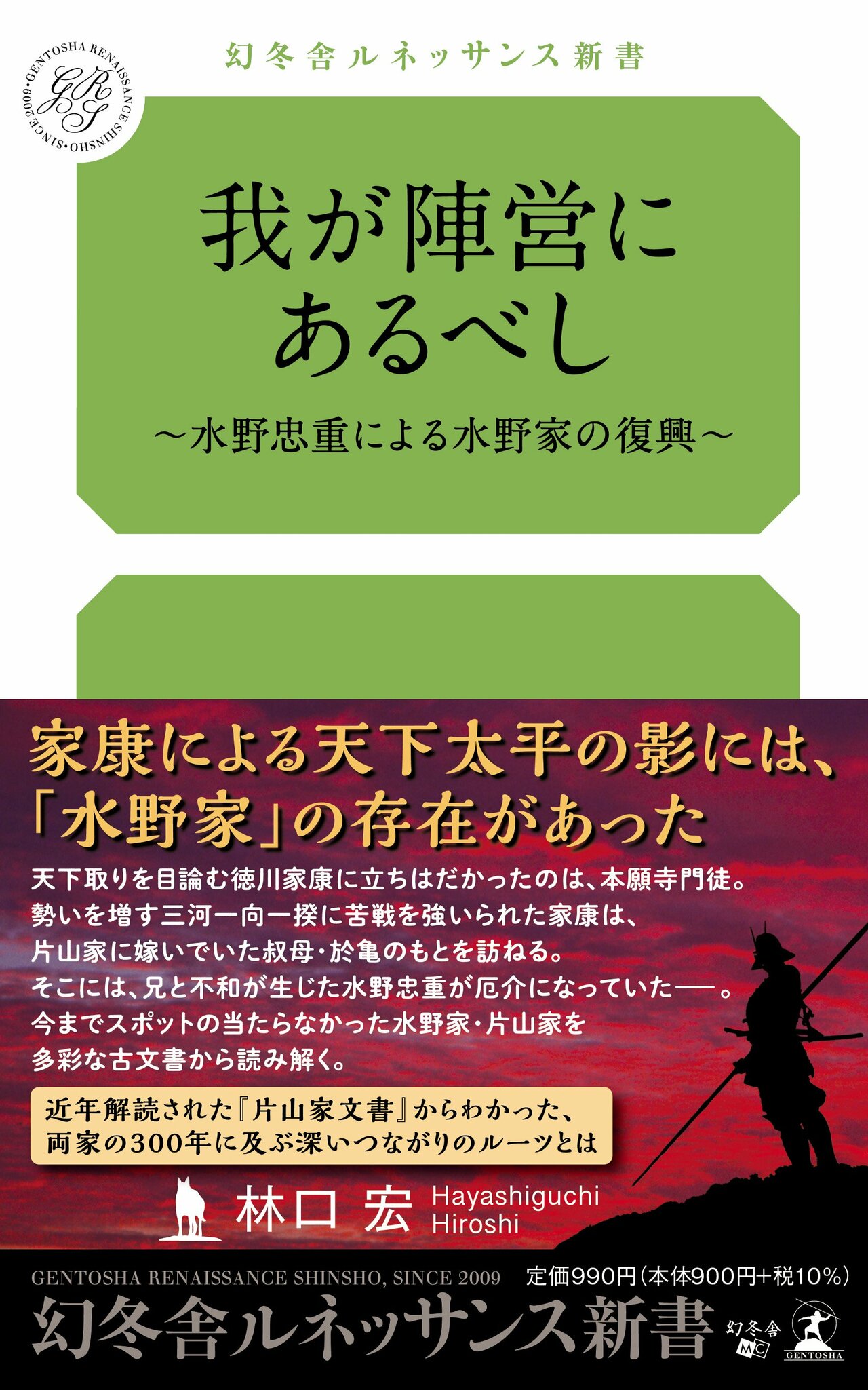矢作川流域の人々の宗教的特徴として、圧倒的に念仏系の浄土真宗の人数割合5が高かったことが挙げられる。特に浄土真宗本願寺派の割合が高く、真宗王国と呼ばれた。
この地方に浄土真宗が多くの信者を得て栄える契機は、蓮如による三河教化であった。宗祖親鸞の時代に、親鸞から念仏の教えを受け真宗に帰依していった人々もいた。蓮如の三河布教を遡ること二百年前に、鎌倉街道沿いの太子堂(別名柳堂・岡崎市大和町妙源寺)で宗祖親鸞による布教(説法)が確認されている。
親鸞は嘉禎(かてい)元年(一二三五年)、関東から京へ向かう折に柳堂に留まり説法をしたのだが、この柳堂説法にお寺の縁起があるとする寺院は多い。矢作川流域のこの地方が浄土真宗一色に塗りつぶされていくのは蓮如の布教以後であった。それまでは天台宗寺院や真宗でも高田派の寺院だったところが、この時期より蓮如の本願寺派への改宗・転派が確認されている。
1 熊野三山(和歌山県南東部)は、神仏習合発祥の地で自然神信仰と祖先神信仰、修験、仏教など現在の日本人の信仰の原点となる信仰がすべて揃っていた。熊野比丘尼という女性の宗教者は、諸国を巡り歩き地獄絵、極楽絵の絵解きをした。
2 愛知県碧南市築山町にある時宗の寺院。暦応二年(一三三九年)創建された。十五世紀前半、松平親氏が父の得川有親と共に来往し、有親はこの称名寺で逝去した。
3 坂井郷(酒井郷)は、現在の愛知県西尾市吉良町酒井と考えられている。
4 松平村は、矢作川上流に位置し、松平氏・徳川氏の発祥地である。現在は豊田市に編入されている。
5 『大日本寺院総覧』、堀由蔵編、明治出版社、一九一六年。同書では、西三河の浄土系は八十%、東三河の浄土系は二十%、尾張を含む愛知県全体の浄土系は五十%~六十%としている。
【イチオシ記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。もう誰のことも好きになれないはずの私は、ただあなたとの日々を想って…
【注目記事】娘の葬儀代は1円も払わない、と宣言する元夫。それに加え、娘が生前に一生懸命貯めた命のお金を相続させろと言ってきて...