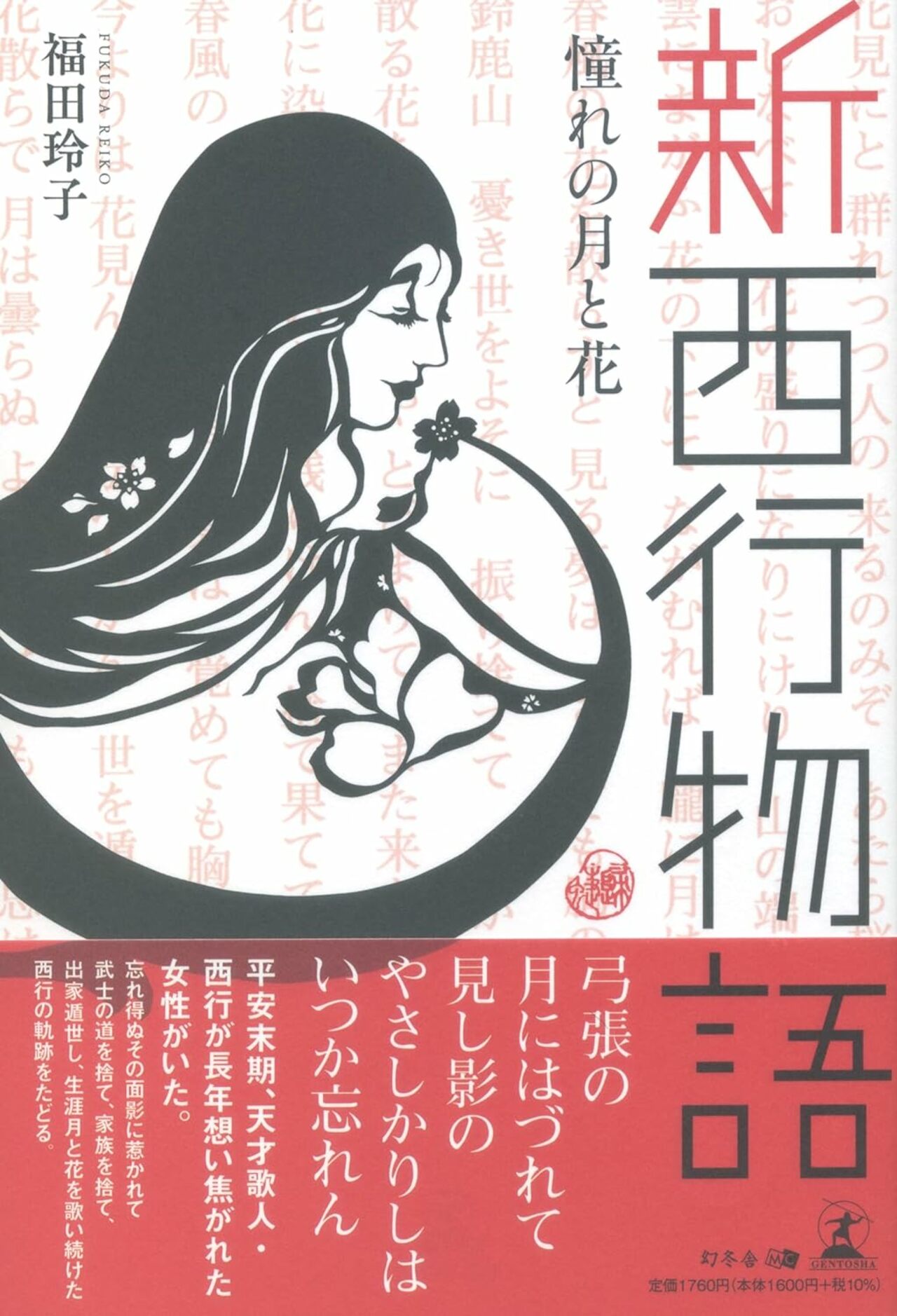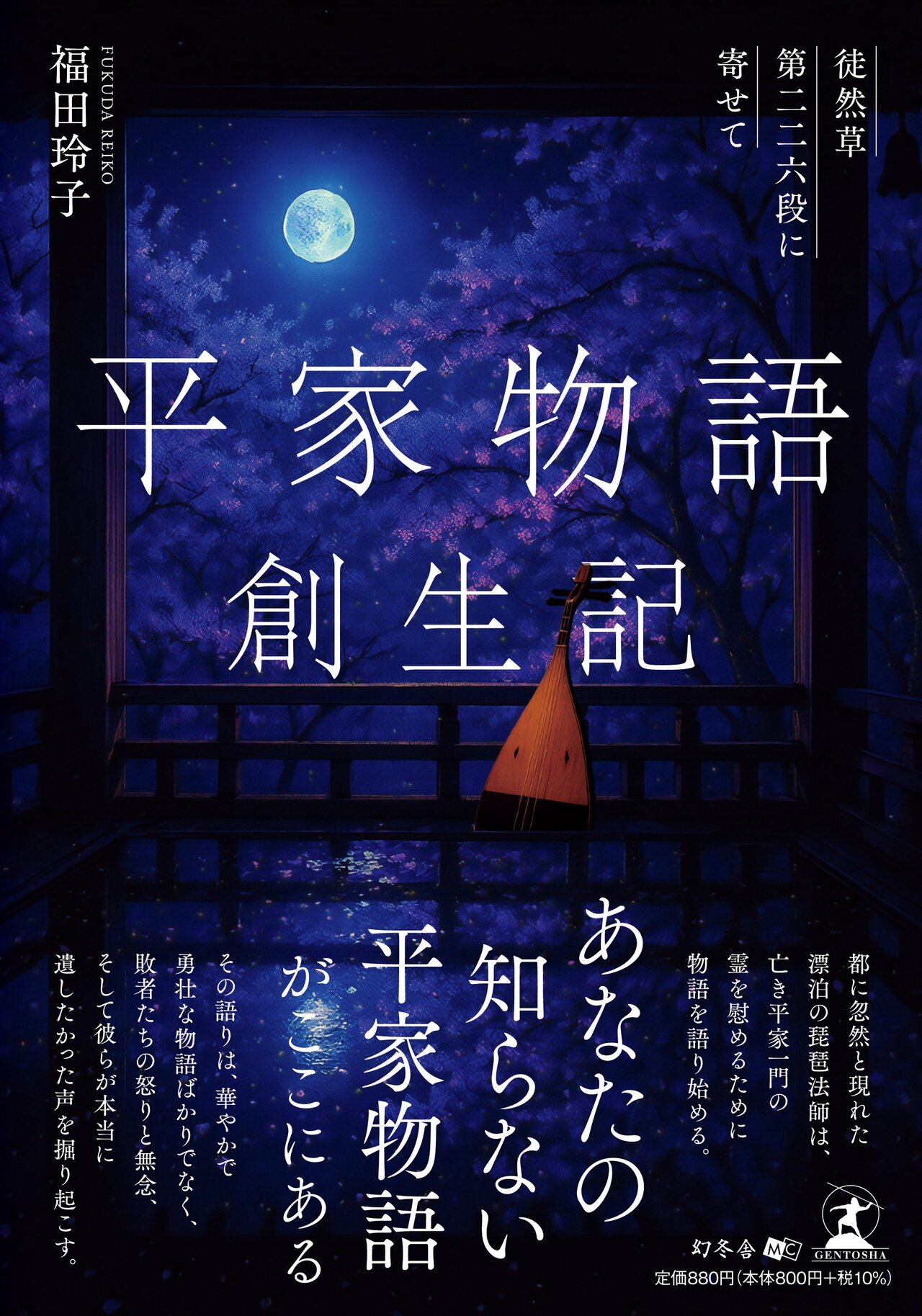折敷(おしき)が皇子達や姫宮、女房達に回され、薄紅色(うすべにいろ)の花形の唐菓子(とうがし)が人々の手に渡る。
風に乗って花びらが時折舞い散る庭に、乙前(おとまえ)の高く澄んだ歌声が響いた。
「茨(うばら)小木(こぎ)の下にこそ 鼬(いたち)が笛吹き 猿奏(かな)で かい奏(かな)で 稲子(いなご)麿賞(まろめ)で 拍子(はうし)つく
さて蟋蟀(きりぎりす)は 鉦鼓(しゃうご)の 鉦鼓(しゃうご)の よき上手(じゃうず)」
(茨(いばら)の小さな木の下で 鼬(いたち)が笛吹き 猿が舞(ま)い 猿が舞(ま)い バッタ殿は ほめて 拍子(ひょうし)つく さてコオロギは 鉦鼓(しょうこ)の 鉦鼓(しょうこ)の 名人だ)
幼い四宮雅仁親王( しのみやまさひとしんのう )(後の後白河天皇)が御簾(みす)の前に進み出て、鼬(いたち)が笛を吹く身振り、猿が長い手足で舞う手つき、バッタが首をのばして拍子(ひょうし)を打つ仕草(しぐさ)、コオロギが鉦鼓(しょうこ)を鳴らす仕草(しぐさ)をして見せた。
あまりのおかしさに五宮本仁親王(もとひとしんのう)が声を立てて笑い、女房達も「お上手、お上手」と手を打っ褒(ほ)めそやした。
こんな世界もあったのか。義清は息を吞(の)んだ。
佐藤家では、母も叔父達も義清が一日も早く官位に就(つ)き立派な佐藤家の当主となるよう大きな期待をかけていた。伝手(つて)を頼りに義清に一流の師匠を探し、義清は幼い頃よりひたすら学問に励み武芸を磨(みが)いて過ごした。義清は蹴鞠(けまり)や和歌で早熟の才能を示したが、その陰にはこうした厳しい鍛錬(たんれん)の日々の積み重ねがあったのである。
それに比べて、この庭は別世界のようだ、と義清は思った。 今様(いまよう)の澄んだ歌声が花盛りの庭に響き渡り、人々は和(なご)やかにこのひとときを楽しんでいる。皇子(おうじ)や姫君は唐菓子(とうがし)を頬張(ほおば)り笑っているし、剽軽(ひょうきん)な四宮(しのみや)(後の後白河天皇)はみんなの注目を浴びてご機嫌(きげん)だ。
女房達も心からおかしそうに手を打ち、笑いさざめいている。
今様(いまよう)が終わると、御簾(みす)から声が響(ひび)いた。