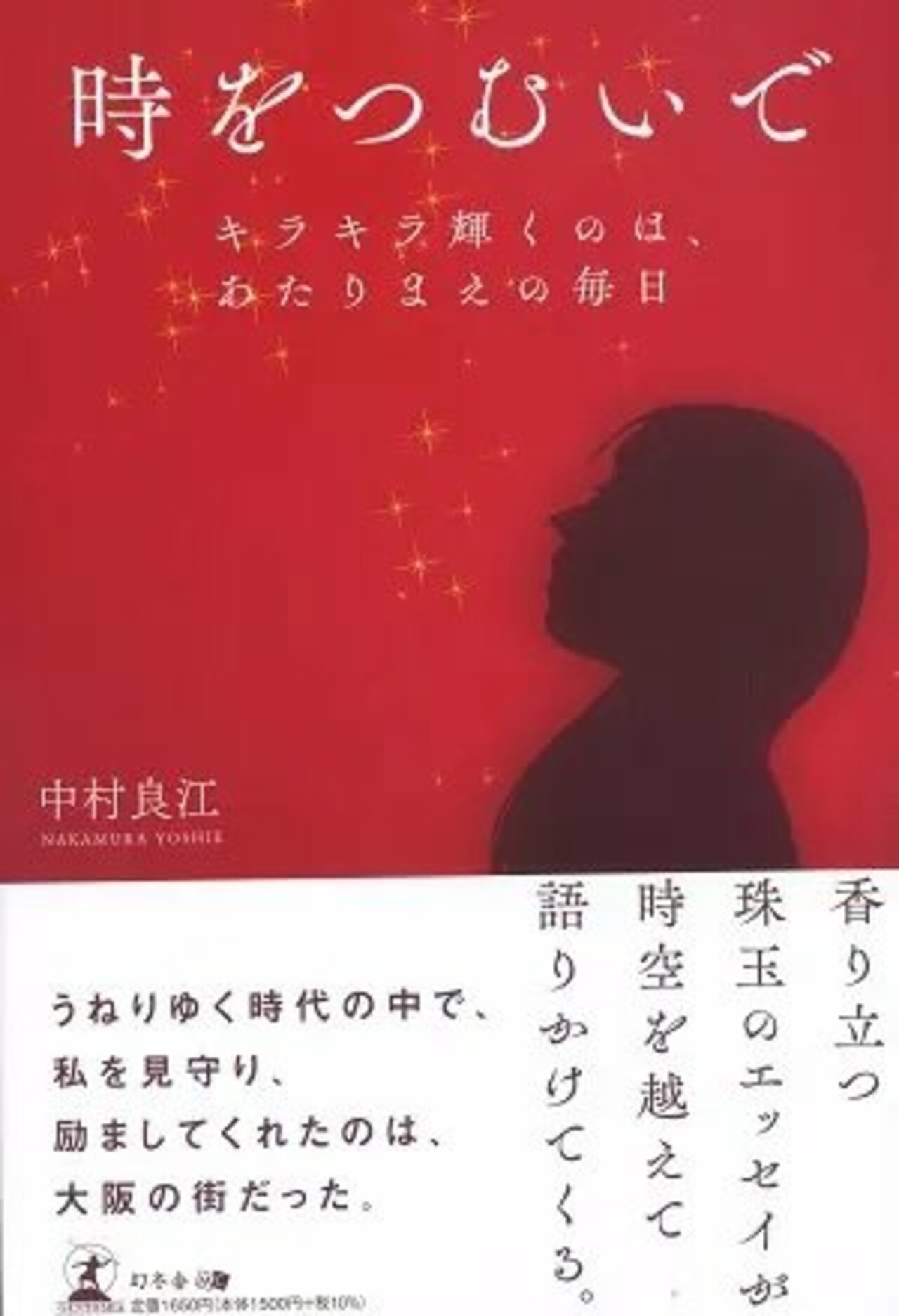【前回記事を読む】必死に逃げた道を戻ると、そこは徹底的に破壊され、焼き尽くされ、沢山の人が死んでいた。爆弾でえぐられた跡がいくつも…
第2章 戦時中から戦後の生活
3 大八車の旅
父の失業
「お金が無い」ということの辛(つら)さを知ったのは、父が失業してからだった。敗戦と共に、徴用にとられて働いていた造船所を放り出された父には、行くあてがなかった。
戦後の混乱期、人々は食べ物を求めて汲々としていた。衣料は統制であったし、とても元の呉服の商いができるような、社会の情勢ではなかった。家族の生活の為に、父は毎日毎日仕事を探して歩いた。
そして知り合いの鉄工所で働かせてもらったり、肩引きの荷車を引いて、運搬の仕事をしたりして僅かな賃金を稼いだ。長年反物を扱って生計を立て、五十歳に手が届きそうな年になっての肉体労働は、かなりきついものに違いなかった。
そのころは、ヤミ市へ行けば、法外な値段で何でも売っていたけれど、わが家ではとても買えるゆとりは無かった。滞りがちな米の配給の補いに、イモやカボチャなどで飢えをしのいだが、高いヤミの米も買わねばならなかった。
そんな時であった。「いつでも家にあるもの」とばかり思っていた紙一枚、泡の出ない石けん一個を手に入れるにも、「お金が要るのだ」と痛感したのは。
そしてお金が無ければ生活していけないという、至極当たりまえのことを改めて悟ったのだった。その当時、私は十五歳、多感な年ごろだった。
ある日のこと、家族みんなの顔が揃った食事時だった。父が弟に、「おまえ、前田の所へ行ってみる気はないか。手に職さえつけておけば将来食いはぐれることはないぞ」と言った。
前田さんは父の友人で、小さなパン工場を経営している人である。弟は黙って箸(はし)を動かしていたが、しばらくして「行ってもいい」と、素直に父の言葉を受け入れた。
父もよくよく考えての上であったろうが、私は側にいて胸を突かれる思いだった。その時、弟はまだ旧制中学の一年生であった。失業してみて、呉服を扱う以外手に職がない為に、生計を立てる苦しさを知った父であった。