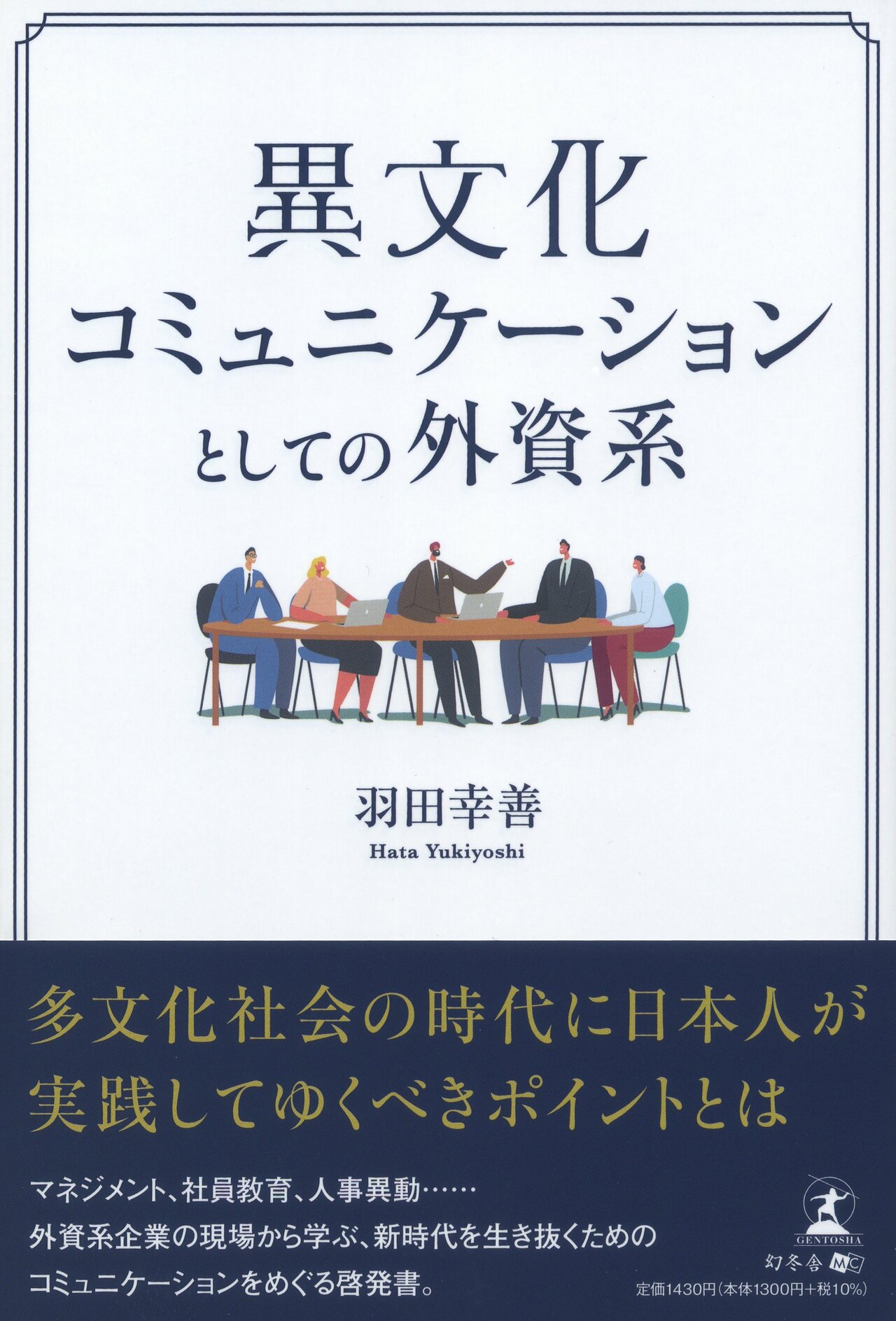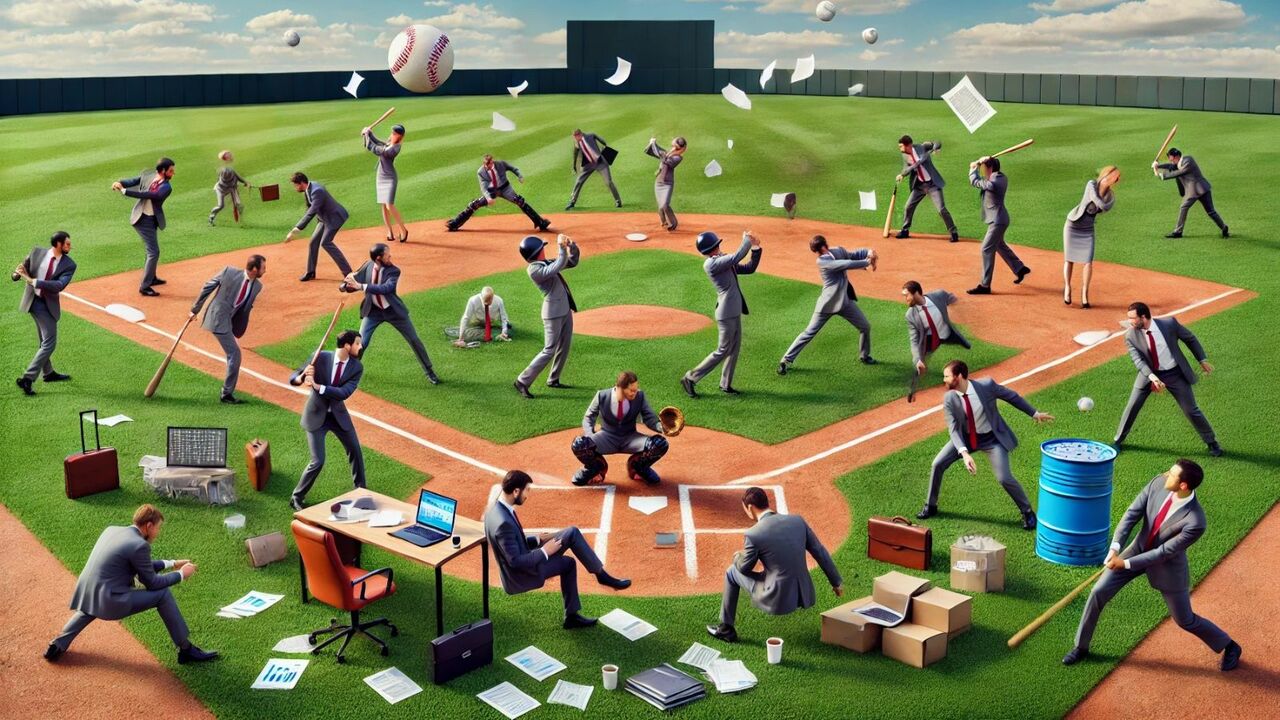そういう社員が減ってくると、一部門での効率化が多くの他の部門での非効率化を引き起こすなど、会社全体としてのビジネスや仕事の改善に支障が出てきます。専門家はどうしても目が内向きになりがちなのです。
ビジネスを行なうに際して監督官庁の許認可が必要な金融機関などの場合、このような個別分野の専門家が集まった組織からなる企業、すなわち自分が担当する分野については十分な経験・知識を持っているが、自分の担当以外についてはあまりよく知らない社員が多い企業は、会社のなかでの仕事の流れやビジネス全体に対する目配りが行き届かず、ときとしてコンプライアンスなどさまざまな問題が生じる可能性が相対的に大きくなります。
「純粋培養と中途採用」、「ジェネラリスト集団とスペシャリスト集団」の違いです。
専門家が非常に多くなった外資系には、もう一つ日本の会社とは違った側面が現れてくることがあります。それは、社員の意識レベルにおいて、企業としての一体感が少なくなることです。新卒で入社してから、さまざまな分野を人事ローテーションで経験する日本式の社員育成方式と異なり、販売、IT、事務処理、経理、人事などの分野ごとの専門家が集まった企業では、どうしても会社としての一体感が希薄になりがちです。
中途入社の社員が多いこともそれに輪をかけます。みなでどうにかしよう、社員一丸となって挑戦しよう、といった雰囲気が社内で醸成されにくくなるのです。おたがいに自分の担当分野のなかで最善を尽くす、というのが大方の外資系のやりかたです。
もう一つ、日本の会社ではあまり見ないことが起こります。それは、特に本社で顕著ですが、おたがいに相手を知らない社員が増加することです。新卒で一斉に入社し、人事ローテーションでさまざまな職場を経験し、同じ社員研修を受けた仲間同士ではあり得ないことです。