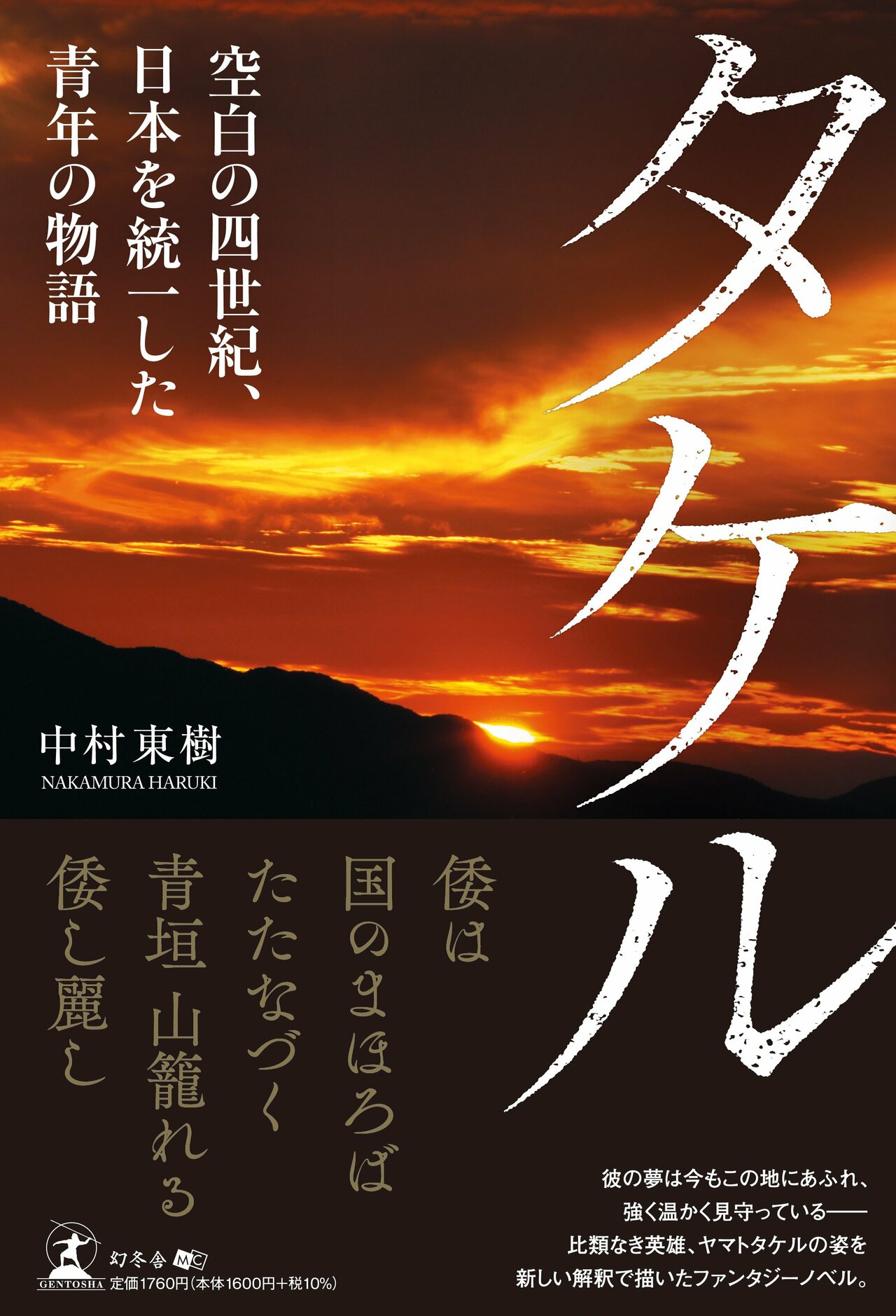川や運河には多くの船が行き来して、物資の搬送が盛んに行われていた。まだ建設途上の陵墓もいくつかあり、それに従事する人も全国各地からやってきた。
この時代になると、この地に各地から朝貢される多数の物産が集まってくるようになった。それらを貯蔵する高床式倉庫も多く造られていた。
これらの物資を持ってくる人たちは、帰りには必要なものを郷里に持ち帰る必要があり、さながらこの纏向の地は、日本各地の物産をやり取りする市場のような様相を呈していた。このような街ができたのはヤマトの国では初めてのことであった。
広大な宮殿の西側には、大和盆地が一望されるほど大きく開かれており、大王一族が所有する水田、畑地などもすぐ近くにあった。
敷地の中には、各地から選ばれた選りすぐりの職人たちが各工房で働いており、日夜様々なものが作り出されていた。
そこで働く人たちのための食事を作る厨房では、一日二回の食事の準備のために多くの人が忙しく働いていた。米、麦、野菜、塩漬けや日干しの魚、鹿や猪の獣肉など多彩な食材が調理されていた。
引用文献1 倉野憲司校注『古事記 第84刷』岩波文庫、p 45
【イチオシ記事】3ヶ月前に失踪した女性は死後数日経っていた――いつ殺害され、いつこの場所に遺棄されたのか?