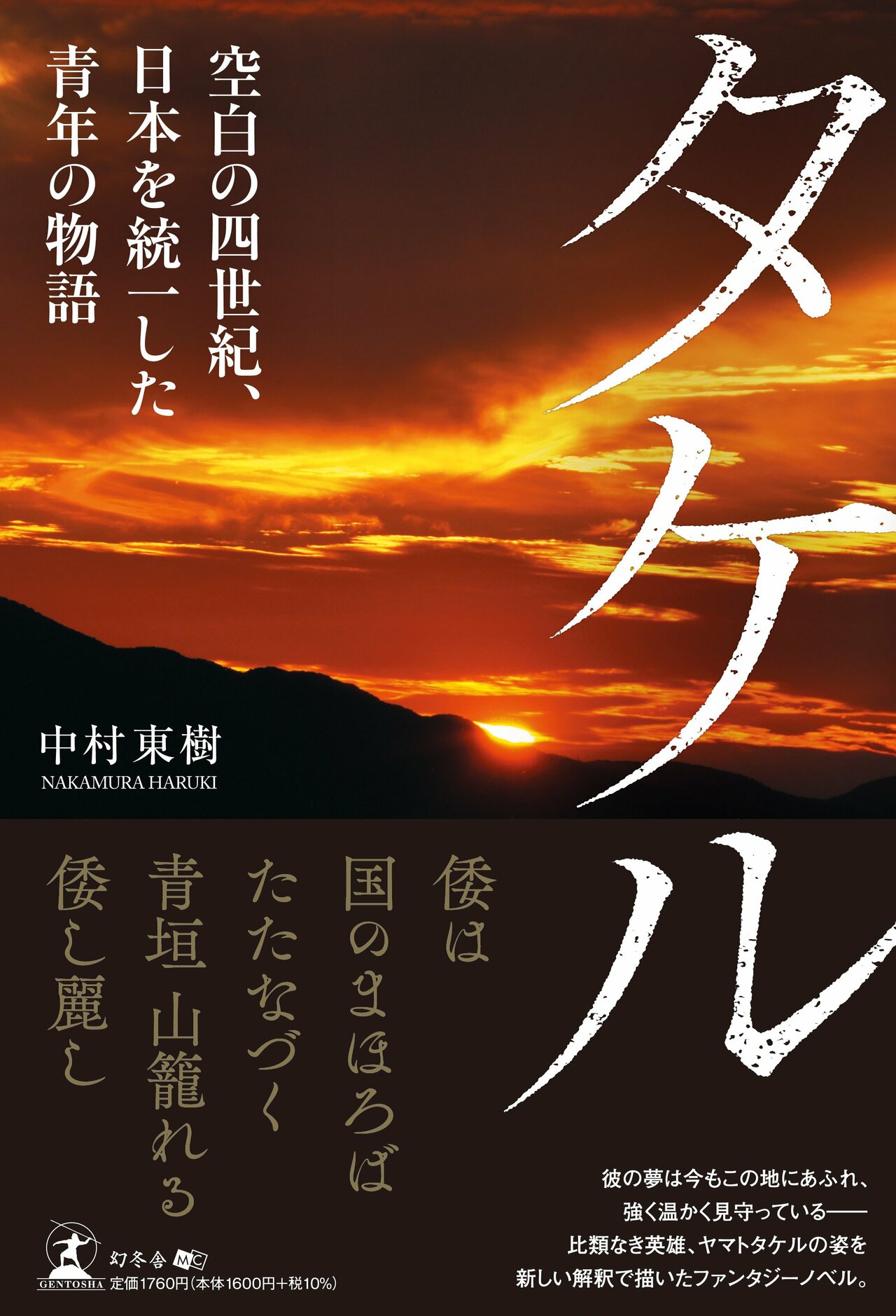大王家は、毎朝三輪山と箸墓に対する祭礼は欠かさなかった。この大きな墳墓の造営には、大陸からの帰化人の一族が関わったとされている。宮殿の東側の山沿いには、当時も新しい墳墓が多数造られていた。
ヤマトの国の大帯日子(おおたらしひこ)大王は、関東、東海、北陸、尾張、美濃、難波、備、中国地方、さらには四国や九州の一部など多くの国を従えるようになり、その権勢はますます巨大なものとなってきた。
後に古墳時代といわれている時代区分は、この纏向の地で造られた箸墓の造営から始まったといってもよく、この墳墓は大和朝廷にとって非常に重要な建造物なのである。
各地で大和朝廷に服属した豪族たちは、三輪山の神々をともに祀り、宗教的な同一性を保つことが必要であった。そのため各豪族の先祖は神々の系譜の中に組み込まれていった。それと同時に服属した豪族の地元には、自分の力を誇示する為の大きな墳墓を建造するようになる。この建造方法を大和朝廷は伝えていったのである。
こののち日本国中に大小さまざまの墳墓である円墳、方墳、さらに日本独自の形をした前方後円墳など、想像を絶するほど多数の墳墓(十数万基)が建造されたのが古墳時代である。この時代は三百年以上も続いたのである。
大王の広大な敷地の中には、祭祀を行う館、大王の一族が住む住居、各地の豪族や外国の使節など要人が宿泊する建物などが数多く建造されていた。宮殿を取り囲むように大きな濠があり、巻向川から大小の運河を介して、水が流れ込んでいた。