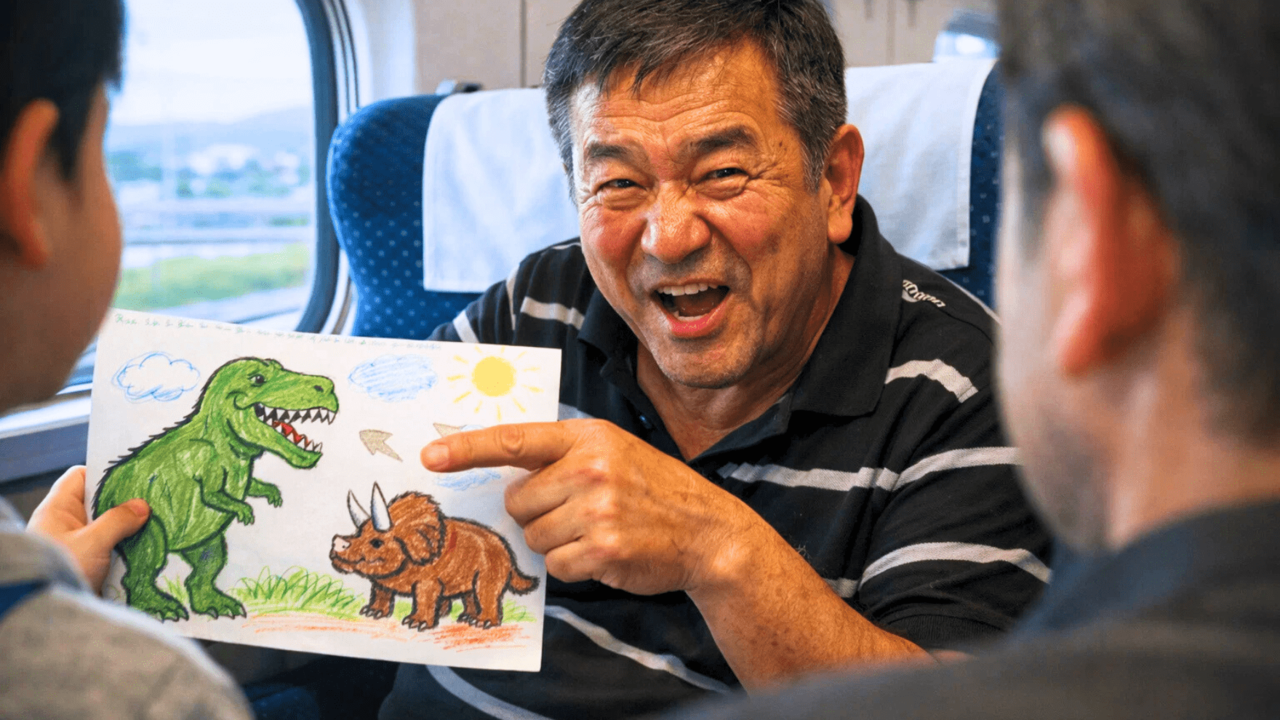4. 「省音(消音)の法則」は常に働くのか
上代語において、連続する母音がある場合、「消音の法則」が働くということは多くの識者の知るところである。
例えば、市鹿文(いちかあや→いちかや)、倉稚綾江(くらわかあやひめ→くらわかやひめ)、坂合(さかあひ→さかひ)、更荒(さらあら→さらら)、田油津江(たあぶらつひめ→たぶらつひめ)、村合(むらあはせ→むらはせ)、堀池(ほりいけ→ほりけ)等である。
しかし、消音の法則は常に働くのであろうか。
吉田と武井は、それぞれ「八尺鏡訓二八尺一云二二八阿多(やあた)一。」をとり上げ、古音重視の考えから訓注のままに訓むこと(ヤアタ)を主張した(第一節参照)。
武井は、「八」(ヤ)と「尺」(アタ)とが結合しても、この場合、「ヤタ」とはならない旨を特に注記しているものと受け取ることが、もっとも自然な受け取り方であることを指摘した注2。
山口佳紀もまた、「実際には、ヤタと発音されたと見る必要はなく、ヤアタと発音されたと考えてよい。」とした。そして、『古事記』(思想体系本)の補注が、『日本書紀』にみる「八田(やた)間大室」や「八咫(やた)鏡」を参考例にしてヤタと訓んでいることを不適切であると指摘している。
また、山口は、同母音が連接すると一つになることが多いことは当然としながらも、必ずしも一つになる訳ではないとして、
「うらはぐし 布勢の美豆宇弥」(万葉十七・三九三三)
をあげている注3。小松英雄の「アクセントの変遷注4」での指摘や後世の資料をもとに、上代においては、「美豆宇弥(ミヅウミ mizu-umi)」が「湖」としてまだ一語化していなかったことを明らかにしたうえで、母音連接の例としている。
西宮は、消音されない例として、志賀高穴穂宮(しがのたかあなほのみや。現在の滋賀県大津市穴太。景行天皇、成務天皇、仲哀天皇が都としたところ。傍線は筆者、以下同じ)を上げ、このような読み方が決して奇異でないことを示している注5。