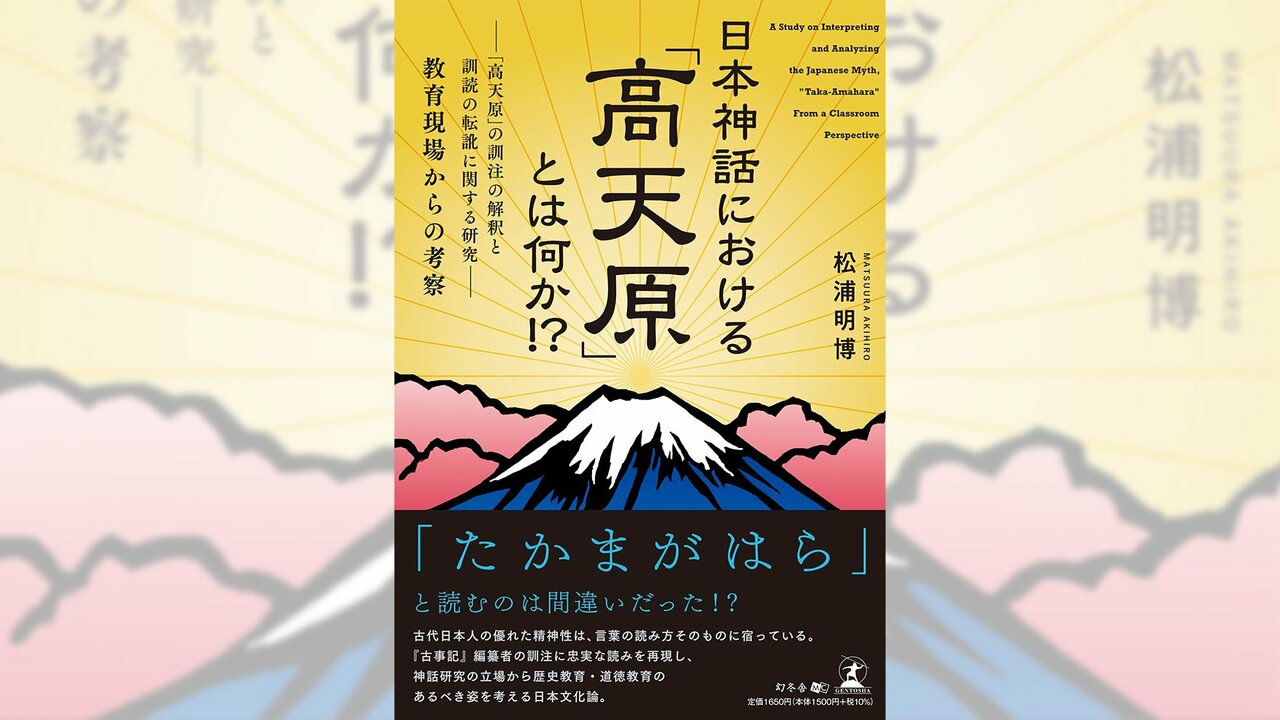【前回の記事を読む】さらに吉田は高天原が延喜式の祝詞にも多く使われていることに着目した。そこから得られる論拠とは?
第一章 「高天原」訓読の研究成果と考察─その今日的意義
3. 「たか あまはら」の研究事例と考察
『万葉集』などで、「天原」がアマノハラと読まれているからといって、「高天原」においても「之」がなくともノを入れて読むとは限らない。なぜなら「高天原」と「天原」は必ずしも同一ではないからである。
『古事記』において、「高天原」と「天原」の表記が同時に用いられ、その関係性が理解できる箇所を次に示す。
「爾高天原皆暗、葦原中国悉闇。」(古典大系80p)。
「爾高天原動而、八百万神共咲。」(同82p)。
「於レ是天照大御神、以二為怪一、細二開天石屋戸一而、内告者、因二吾隠坐一而、以二為天原白闇、亦葦原中国皆闇矣一…。」(天照大御神の言葉、傍線は筆者)(同82p)。
これについて武井は、「同一の〈もの〉が、天上での把握として《天原》、地上での把握として《高》+《天原》のごとく識別されていたものと考えられる。「天原」の表記については訓注がなく、また、そのあらわす概念についての説明もない。(中略)当代の読者にとって不要であったことを意味してはいないであろうか注1。」と問題提起している。
この『古事記』などの例から、「高天原」と「天原」は、同一の概念を表しているとの指摘がある。しかし、天上界での表現と地上界から仰ぎみた表現との立場の違いがそこにはある。また、上代人が『万葉集』で詠んだ歌の中の「天原」と「神話」の中の「高天原」とは、そこに本質的な違いがある。
そこで、「高=天原」という語形をイメージするならば、当然ながら、当代の読者は「タカ-アマノハラ」と読むに違いない。それを回避して、古訓に従い、ノを入れずアマのままで読ませ、違いを明らかにするために、あえて訓注を施したものと、筆者は考える。
高天原の訓みに、「ノ」を入れるか否かは、その後に大きな影響を及ぼすこととなる。この点については、後章で述べたい。