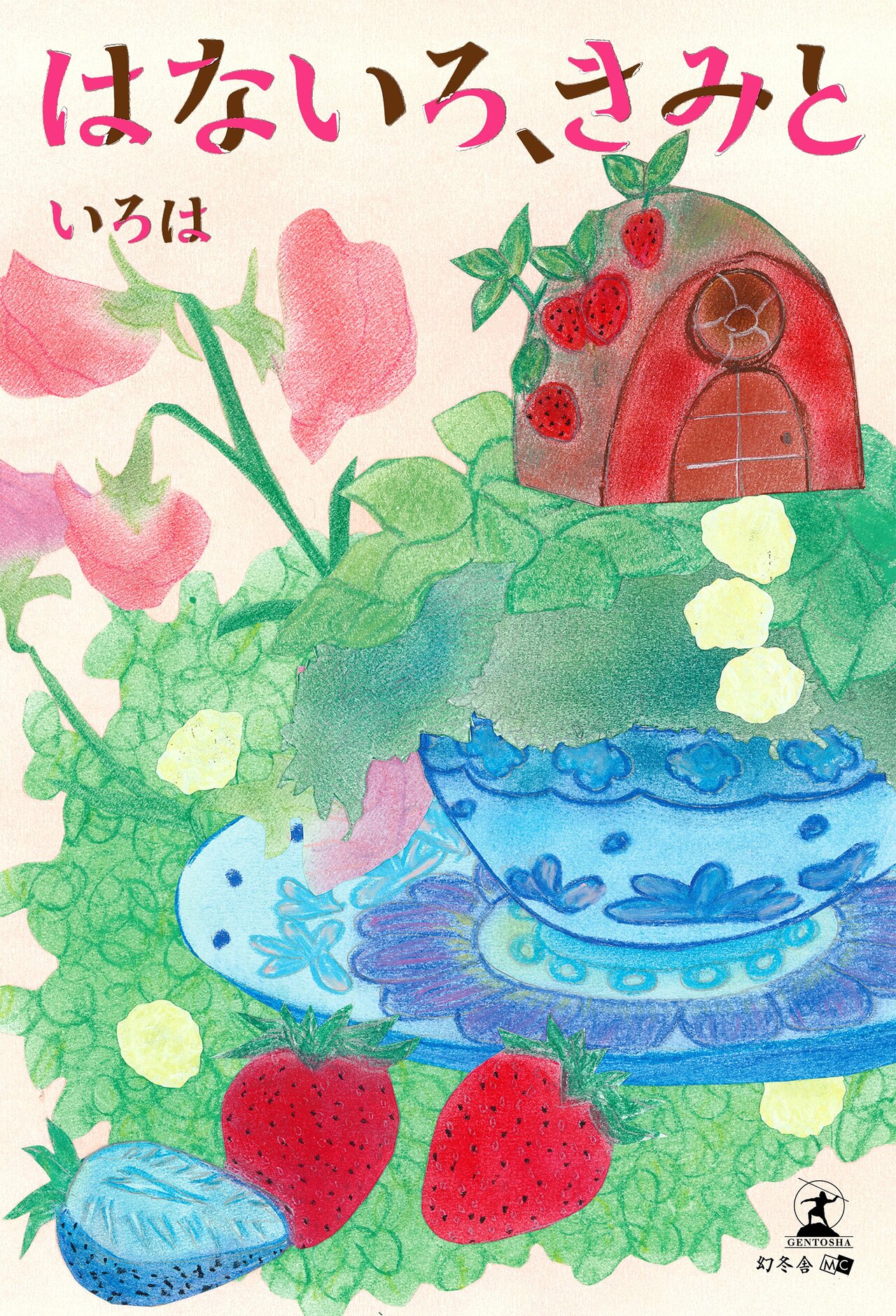私はそこでご飯を作ったり、洗濯をしたり、トイレや入浴の手伝いをしている。
以前は介護支援専門員をしていた。鬱病になってしまい、休職したら家から車で40分もかかるところへ生活支援員として異動することになった。
介護支援専門員とはもっぱら介護保険法の下で働く、その部門のエキスパートだ。そうだったのに障害部門にわざわざ寄こしたのは、嫌なら辞めてしまえということなんだろう。今度は障害者自立支援法の下で働かなければいけないわけだ。ルールが分からないので手も足ももがれたような気持ちになったが、まあ行ってみようと思った。
現場に行ってみて障害者と呼ばれる人たちは健常者と言われる人々から、「そう言うしかないよね」という感じでそう呼ばれているだけで、普通の人間となんら変わらないと思った。
ただ、一般に健常者と呼ばれている人たちのように住むには、誰かの手伝いや道具が必要だというだけだ。健常者の人と同じ生活がしたいと思うことは当たり前だなと思う。トイレに行くのに「お願いします」と頼まなければいけない、どこかへ出掛けるにも人に「お願いします」と頼んで体を抱き上げてもらわないといけないのは、辛いことだ。
「障害部門はわがままでさあ」と言う人は同業者に少なくはない。でもそれって全然違うと思う。体がきかない分、口が出るし、喋れなければ体で訴えるしかないのだから。別に「私は分かる女よ」と言いたいわけではなくて、シンプルにそうでしょと思うだけだ。
福祉とは、こぼれおちたものをすくうものかと思っていたらどうもそうではないらしい、と気が付いたのは最近だ。施設にいるとよく分かる。「もの分かりのいい利用者」「扱いやすい利用者」そういう人が職員に好まれる。管理しやすいから。利用者の人生の課題を一緒に考えていた私にとってなかなかに衝撃的なことだった。
コロナウイルスが2類から5類に変わった今、職員は節度を守れば自由にどこへでも行けるようになった。しかし、利用者と呼ばれる人たちは2時間の外出しかできない。ここは田舎なものだから、例えばお盆なんかは墓参りに行ったら施設にとんぼ返りだ。3時間あれば、喫茶店でお茶でも飲んで来られるだろうに。