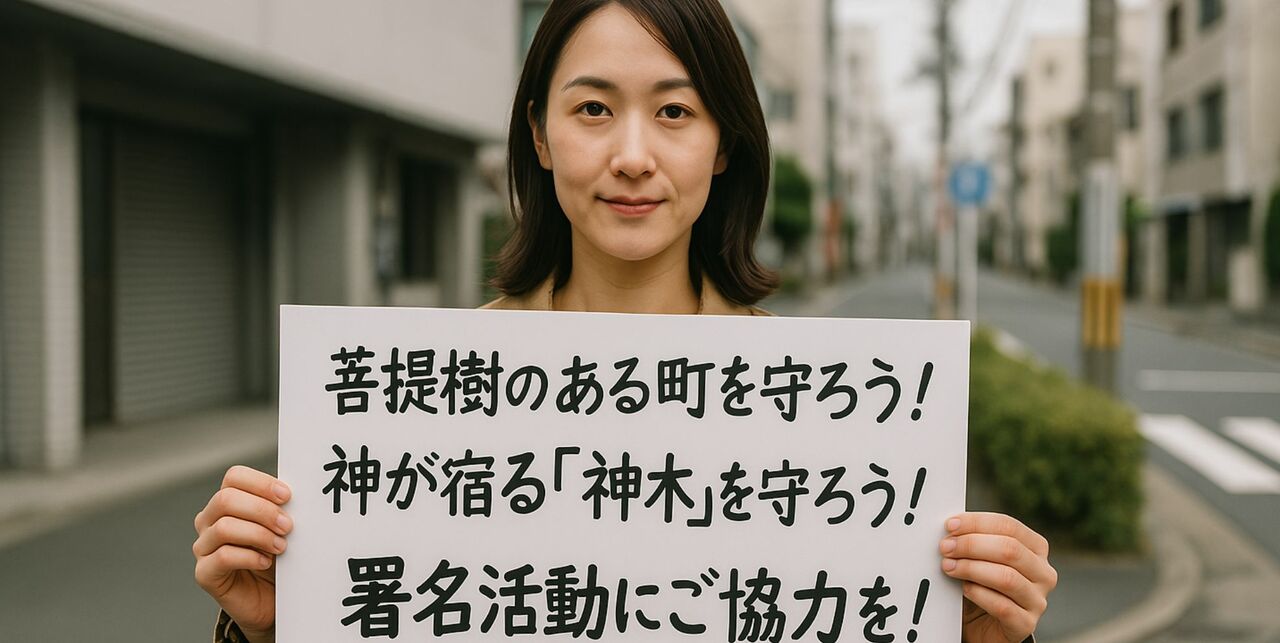菩提樹というと、シューベルトの『菩提樹(リンデンバウム)』をおもい出すけれど、沙那美は幼いときからそのハート型の葉っぱが大好きで、秋の紅葉ともなると母から、
「車が通るから、あぶないわ。道で遊んでは……」と言われていたけれど、それでも黄色く染まった葉を一生懸命拾い集めたものだ。
また落葉の季節にはどんな香水にも負けないような仄かな芳香が辺りに漂い、窓から沙那美の部屋に忍び込んできた。それは少なくとも年一回、沙那美にこの菩提樹が〝命の恩人〟であることを確認させた。
菩提樹はそんなことを沙那美がおもっていることも知らないかのように、まるで彼女の成長に合わせるように年々葉を茂らせ、花と黄葉 (こうよう)の季節に心地良い芳香を放った。
夏になってしばらく日照りが続き、菩提樹が葉を振るい始めると母は毎日、出勤前や夕方帰宅後よく根元にたっぷり散水していた。
秋には大樹の根方を中心にできる黄葉の落葉が象(かたど)る半円リングをじっと眺めたあと、熊手でさも惜しそうに掻き集めていた。そして学校の研修会などで家をあけるときは、
「忘れず菩提樹の様子を見てね。水をほしがったら、あげてね」と沙那美に声をかけた。
秋の落葉が激しく吹雪のように降りしきるとき、
「隣のおばさんから、掃除が大変だからこの菩提樹を伐って、と市役所に頼みましょう、って言われたの。あなたどうおもう?」と母は沙那美に訊いた。
「隣のおばさん? 放っといたら……、人にはそれぞれいろいろな考え方があるわ」
沙那美は別に隣のおばさんが嫌いなわけでもない。彼女の言うとおり落葉掃除の大変さは沙那美自身も経験していたからわからないでもなかった。それでも、秋に降りしきる落葉吹雪や冬風にからころと道を吹き転がる風情はその苦労を吹き飛ばしてあまりあるようにおもえた。