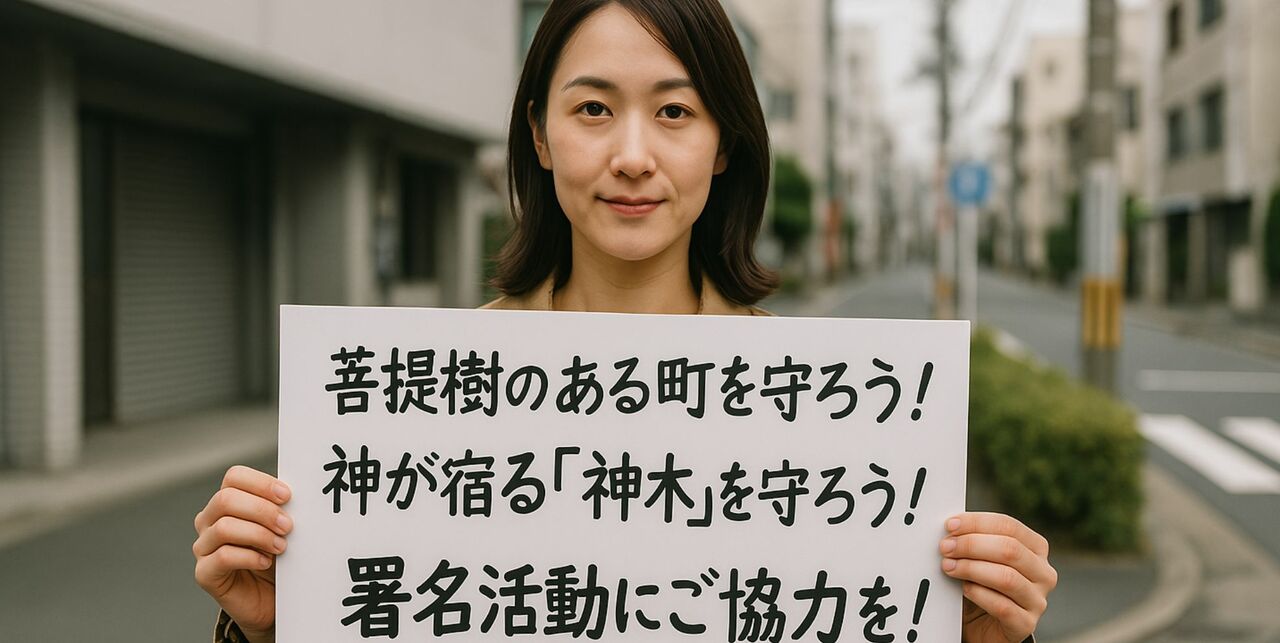長年、桜の接ぎ穂を作り続けてきた悠輔の指先はすらっとした長身とは違って第一関節は異様に膨れ瘤ができたようになっていた。その指先に力を入れると、大島桜の葉は少し軋んだような音を出した。
「おまえの作る桜餅は格別や。ぞんぶんに食べたいんや。それに桜餅の葉の香りは大島しかあかんさかいな。ウチの大島は香りが最高や」
悠輔が腰を伸ばし伸ばし葉を摘む姿が浮かぶ。
午後から桜子と麻美が来た。夕子は娘の桜子も可愛いが、女性同士どこかわだかまりまではいかないにしても、張り合う気持ちがある。
だが、孫の麻美は特別だった。四分の一、夕子の血が流れていることは理屈ではなかった。夕子は麻美にかかると、身体中が蕩けていくような感じを押さえることができない。
麻薬を使った経験はもちろんないけれど、一度その感覚を知ると、無意識に麻美とどこかで関わっていたい気持ちになった。
麻美が生まれる前は、友人の誰かが孫の写真を持ち歩き、誰とはなしに見せたがる様子を、夕子は実は内心、はしたない、とおもっていた。今は、その気持ちは十分理解できる。
しかし、夕子はその気持ちを素直に出せないでいた。麻美に接すると、(ウチは親ではおまへんえ。遠うから見な……)とおもってしまう。だが、麻美が何かの拍子に車道に飛び出したりすると、身体中からガクッと力が抜けてその場にへたり込んでしまいそうになる。
(ウチの心のなかはどないになっとるのやろう)と唇を噛んだ。
「さあ、葉を摘(つ)もか」