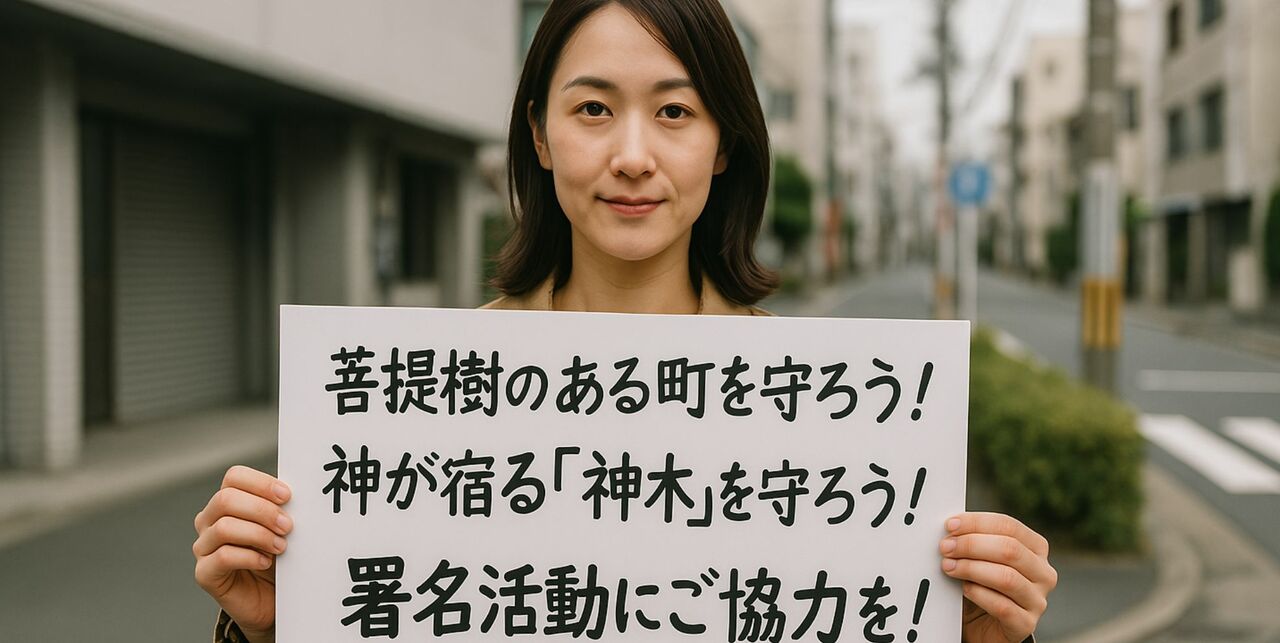古稀になった今でも燻っている。
(なんて執念深い女やわ)と夕子は自分の心を覗き込んで、氷の痼(しこり)を溶かす方法(すべ)はないかと彷徨(さまよ)っている。
そんなとき、どこかで微かに花びらが舞う音が聞こえるのだ。沈沈と更ける闇に聞こえるはずのない音は孤独に増幅されて聞こえる。
缶ビールを二本、キャンバス地のトートバッグに入れ、石室から自家製味噌を一さじ盛った手塩を手に持って家の外に出た。
風はない。
大紅しだれ桜の影をめざす。夕子は毎日、桜の様子を窺い通る桜の園の径は目を瞑っていても歩ける。星も出ていない闇はかえって夕子を確実に大紅しだれ桜の樹の下に誘う。
そこには満開の大紅しだれが待っていた。かつて開花は、染井吉野より一、二週間ほど遅かったのに、近ごろは温暖化のせいか間が縮まった。
桜は薄紅色の靄がかかったように見えた。
どこかの寺のふすま絵で観たのだろうか、おもい出せない。夕子の脳裏に刻刻とその満開の桜のイメージが広がる。これは初夜のあの日の幻想なのか、それとも夢か、定かでないが、なぜか夕子の芯を貫いた。
夕子はしだれ桜の根元の平たい鞍馬石の上に味噌の手塩を置き、トートバッグから缶ビールを出し、
「満開やな。新婚旅行も行かいで、ウチたちの初夜はこの樹の下やったわ。覚えとる?」
夕子は二つのプルタブを引き、大紅しだれ桜に向かって乾杯をするように缶ビールを目の高さにかざした。夕子は自分の顔に笑みが浮かぶのを感じる。
次回更新は3月26日(水)、22時の予定です。
【イチオシ記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。もう誰のことも好きになれないはずの私は、ただあなたとの日々を想って…
【注目記事】娘の葬儀代は1円も払わない、と宣言する元夫。それに加え、娘が生前に一生懸命貯めた命のお金を相続させろと言ってきて...