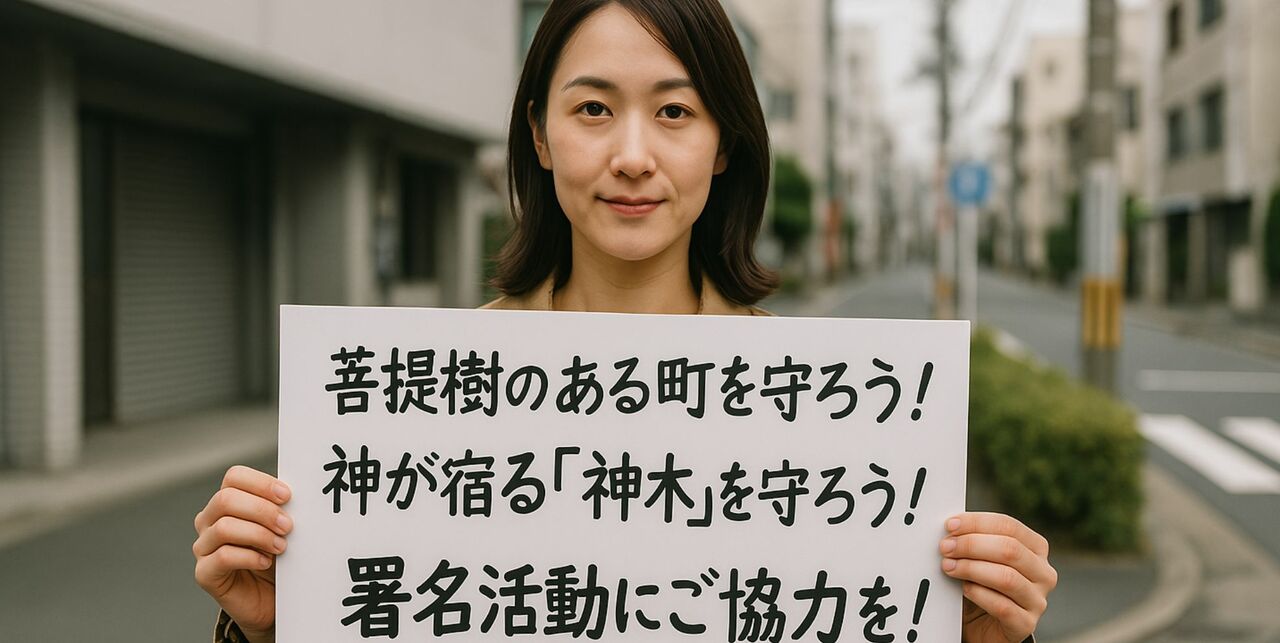夕子はそっと後をつける。悠輔はやがて地下鉄の改札口へ向かう階段の途中にあるパンケーキで有名な喫茶店に入って行った。
彼女は改札口まで降り、またエスカレーターで上まであがり、そっと中を覗き、改札口まで降りることを繰り返す。
そのとき、店の入り口に立った女に気づいた。さっきの受講生の中にいた顔だった。すらっとした体型だが、色の黒いあまり目立たない女(ひと)だった。
夕子の心は粟立った。
その日も悠輔は帰ってこなかった。次の朝、帰ってきた彼に、「どこへ行ってきたん?」と訊いた。
「やかましいわ。眠たいんや」と言うやいなや夕子の頬を平手で張り、布団に潜り込んで寝てしまった。悠輔が唯一、夕子に振るった暴力だった。彼にはそうするしか心のやましさを表現できなかったのかもしれない。
その日、夕子は手元が見えなくなるまで急ぎの接ぎ木をし続けた。接ぎ木は繊細な作業だ。気を抜いたら良い結果はでない。しかし、作業は夢中になれる。何もかも忘れられる。でも乱れた心ではきっとまともな作業になっていなかったとおもう。ただ夕子の気持ちを多少なりとも慰めた。
悠輔は次の朝まで起きてこなかった。
夕子の身体は悠輔を求めたが、心は娘の桜子を選んだ。桜子の手を引き、桜の園を見回ることで夕子の心は少しずつ修復されていった。そんな日々が半年ほど続いたが、とても冷え込んだ朝、悠輔は帰って来るなり、「すまんかったな」と一言。作業着に着替えると、苗畑へ行ってしまった。
寒月が新月を迎えるころ、彼は前と変わりないほど夕子の側に居続けた。
夕子はすべてを忘れようと気持ちを切り替えようとしたが、そう簡単に忘れることも許すこともできるはずもなかった。