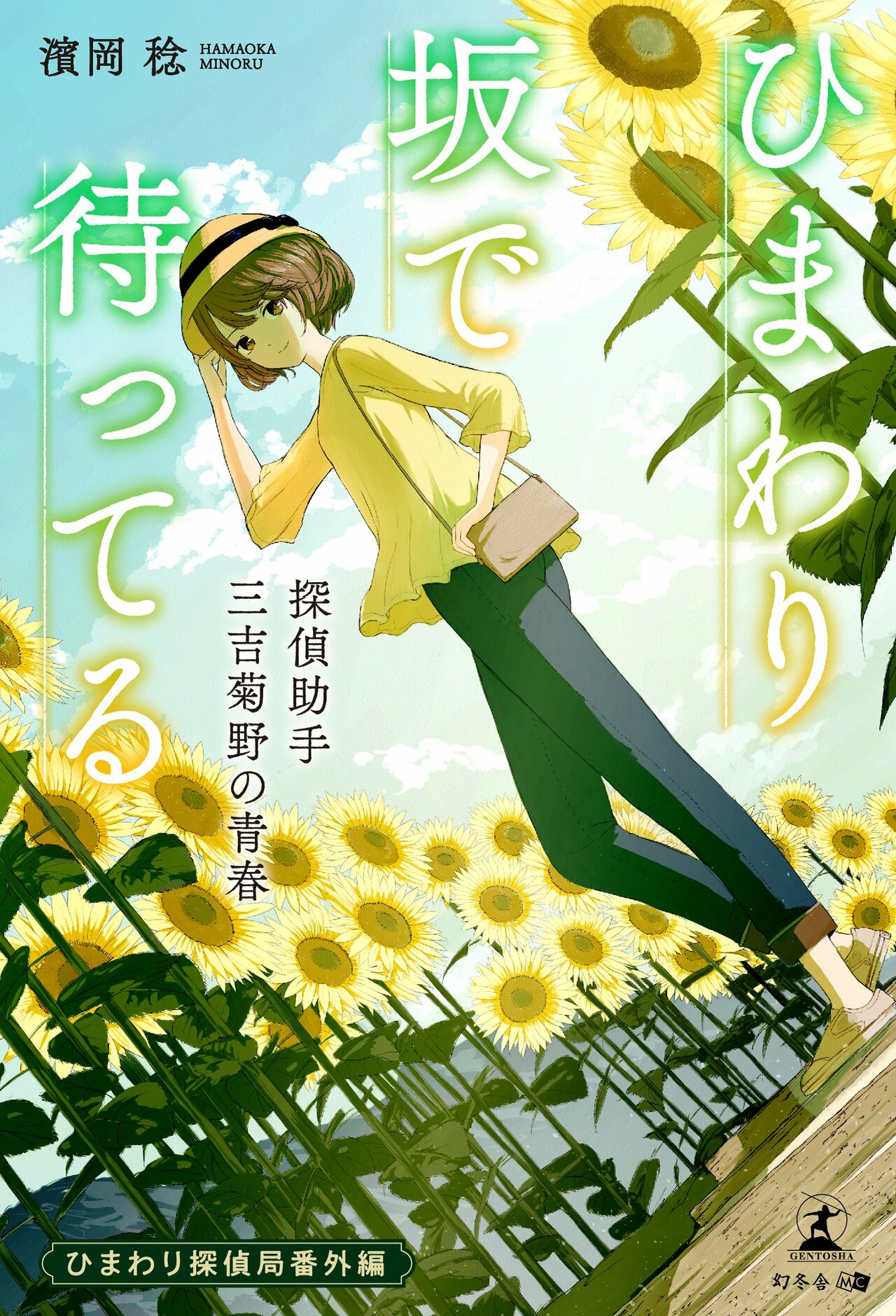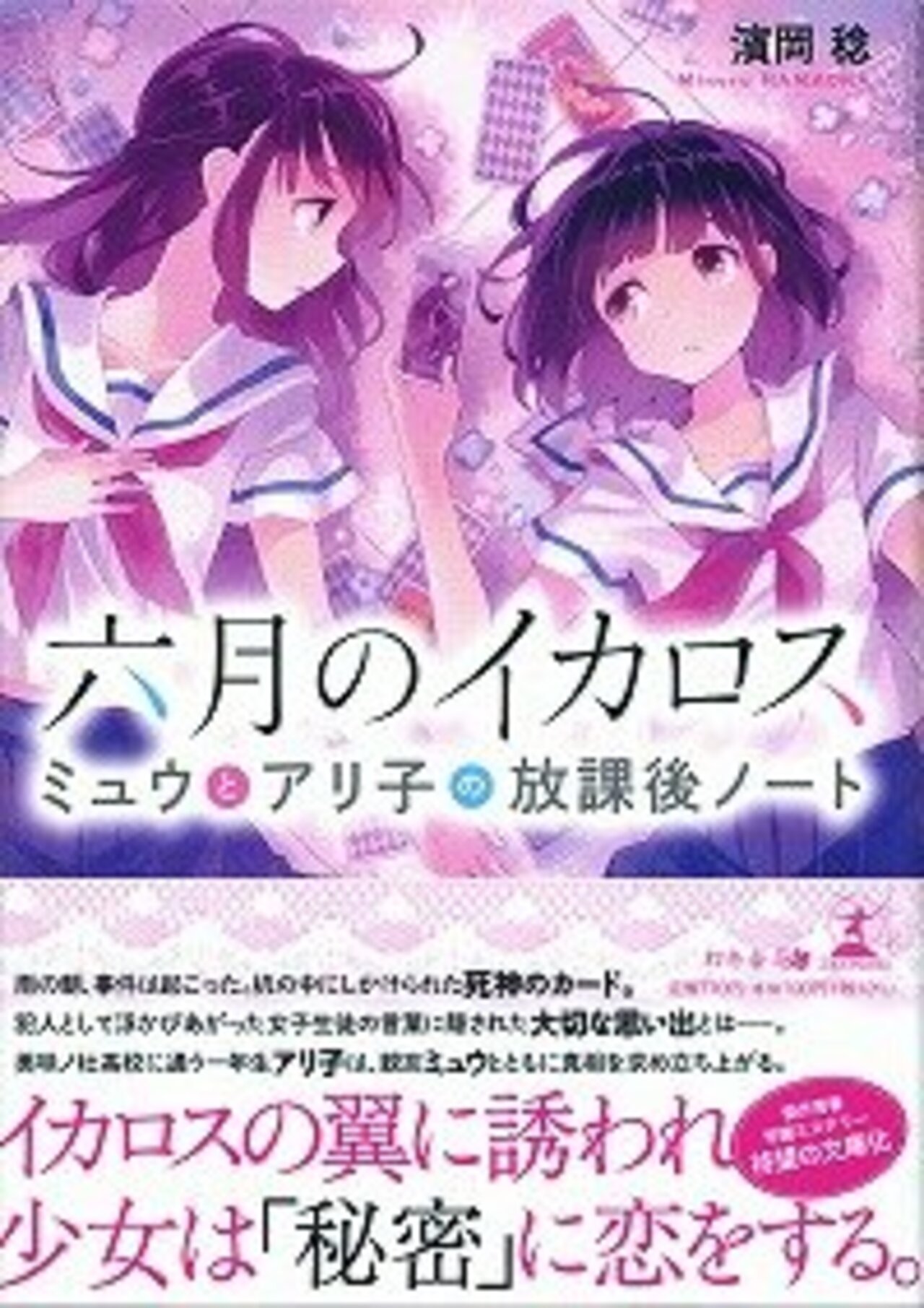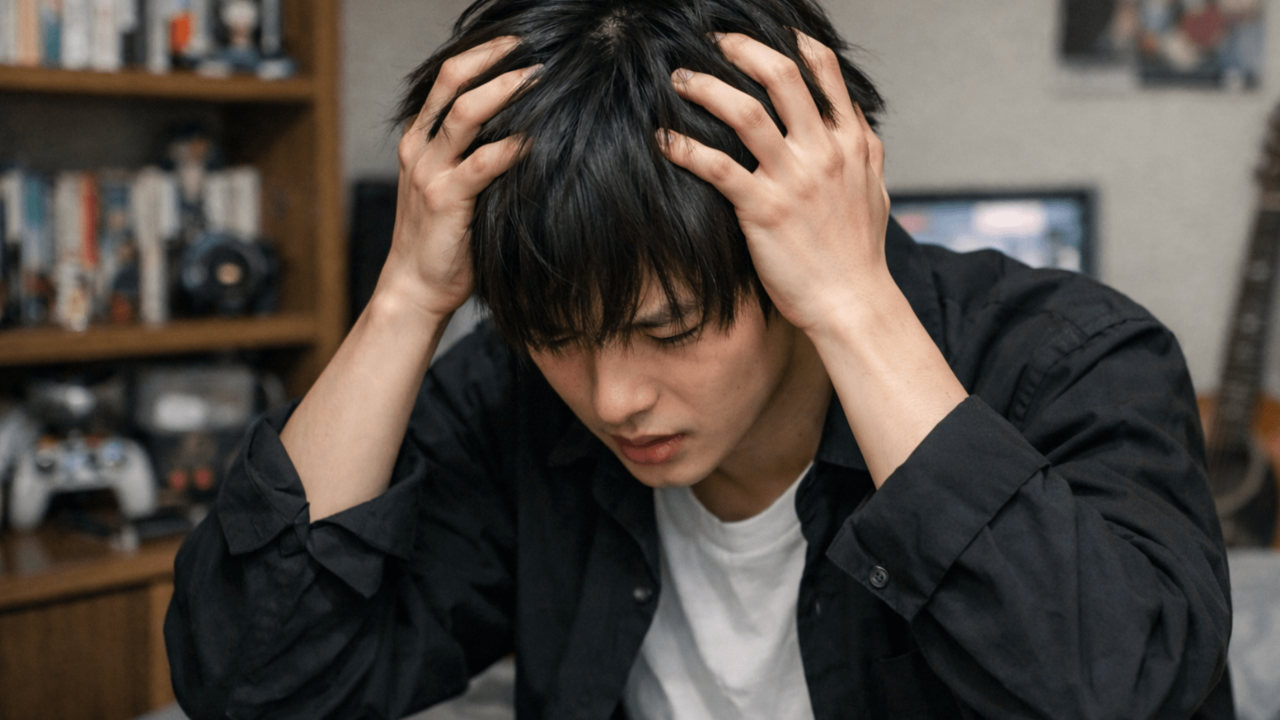そう声をあげたわりにはさしてあわてる様子もなく、牧野島さんは、木の間越しに空を見つめながら「ああ、でもほんと、あのころは楽しかったなあ。すっかり思い出にひたっちゃった。ザ・青春だったもんね」とひとしきり追憶の余韻を反芻(はんすう)した。
それから、「またみんなで集まろうよ。あ、これ社交辞令とかじゃないからね」と念を押し、「では、拙者は失礼つかまつる、なあんて」とにこやかに手を振りながら、牧野島さんは商店街のある方向へと去っていった。
一方的にエネルギーを吸いとられた気分で、わたしは、しばらくの間その場で呆然としていた。気がつけば、どこかに活動拠点を移してしまったのか、アブラゼミの鳴き声もすっかり収まっている。
やれやれ、なんて朝だろう……。
葉叢(はむら)から射しこむ陽の光に追いたてられるように(日陰をたどって歩く算段も、もはやすっかり消えうせていた)、日ざかりの下でゆらゆらと熱を放射するアスファルトに向かって、わたしはのろのろ歩きだした。
ザ・青春か――拙者にそんなものあったかな……なんて思いながら。
2
人と人が支えあって “人” という漢字ができた――わけではなく、 “人” という字は、腕をさげ、少し腰を曲げて立つ人を横から見た象形文字らしい。
生まれるときも、死んでいくときもひとり。咳(せき)をしても、くしゃみをしてもひとり。
人は、どこまで行ってもひとりなのである。けれど、その昔だれかが歌っていた気がする。人はひとりでは生きていけないものなのだと。それもまた、まごうかたなき真実だ。
人という字に “間” を添え、人の間と書けば “人間” 。これを “じんかん” と読めば、人が生きる世界――すなわちこの社会を表す。他者を認識し、社会という人と人との関係性のなかに置かれて、初めて人は人間(じんかん)に生きる存在、すなわち人間(にんげん)になる。