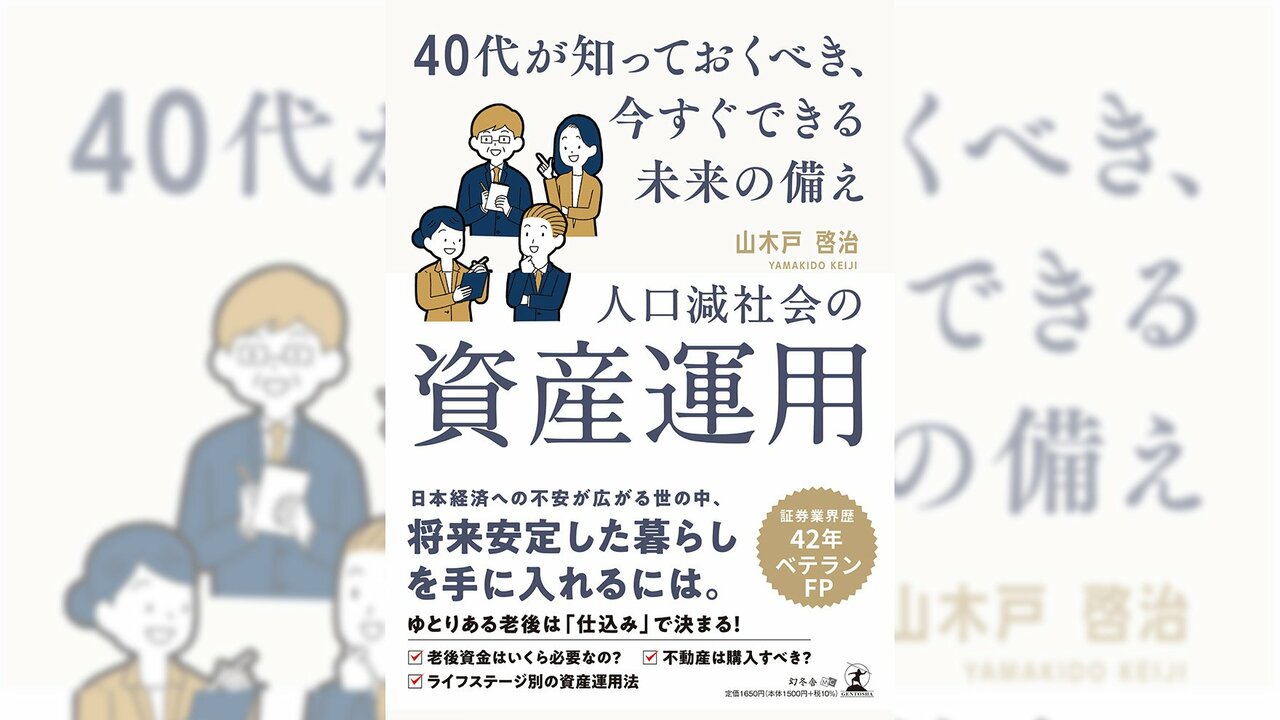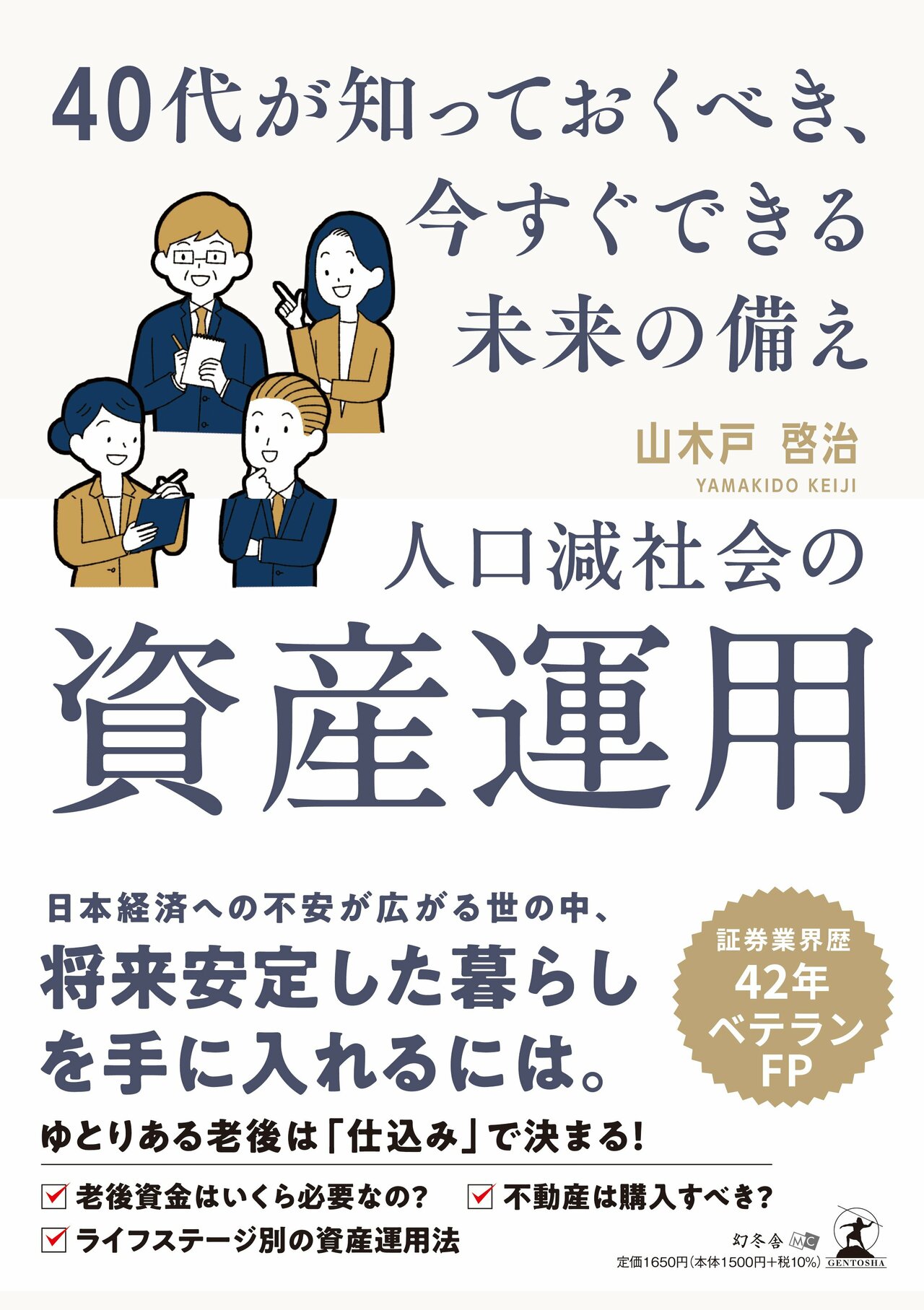【前回の記事を読む】人生100年時代の資産運用において大切なのはライフサイクルを意識した見通し。60歳になったあなたの人的資産価値は......?
第4章 ライフサイクルと資産運用
5 自分に合った金融資産をみつける
資産形成を重視する観点からは、定年退職までを、資産形成期と考えます。定年退職から年金受給開始までを移行期、年金が生活の柱になる年金生活期と区分します。
人的資産の価値が大きい時期は、積極的に金融資産による資産形成を図る時期です。株式等のリスク資産を中心に、中長期的な視点で適切なリスクを取って運用すべきです。
人的資産の特性が、国内経済に連動するリスクを持つと考えられる場合には、海外のリスク資産への投資が重要な選択肢です。
人口減社会の進展で、国内需要が減少し、成長期待が小さくなる状況では、早期退職制度のもとで失業の懸念があります。
働き場所に関するリスクの分散を図る必要性もあります。複数の働き場所、複数の収入を確保することにより、リスクの分散を図ることは、自然なことです。
ベテランの生き残る道では、経験を土台に、鍛錬を重ねてニッチな分野で、自然と感じる得意な型を持たざるを得なくなります。ジョブ型雇用では、より良い労働条件で働くために、自営業的な働き方で、緊張感がある専門職化、技術職化が生じています。
ニッチな分野で得意な型を持つことは、不確実な時代を生きるための対策ですが、人的資産が片寄るリスクはあります。
人的資産の特性が片寄るリスクを軽減するためには、世界の株式等のリスク資産を活用してヘッジする必要があります。
国内企業の持つ経済的リスクを軽減する効果が高いのは、海外株式への定額購入法による分散投資です。適切なリスクを取らなくてはならない理由のもう一つは、将来の負債はインフレリスクを伴うからです。
インフレリスクを相殺させ、将来の負債をまかなうには、リスクを持つ資産への投資でしかマッチングできません。
時価が変動する資産と負債を1つのものとして管理して、バランスをとることは重要です。現在のように物価上昇率がプラスで、名目金利がゼロ近くである状態では、保有するお金の実質的な価値が減るリスクがあります。
安全資産に限定した資産形成では、目標の達成は困難と推測できます。グローバル化の後退の流れから、国際貿易の不確実性が高まっています。国際的な商品の供給網がマヒすることを通じて、インフレ率が上昇することが考えられます。
グローバルな自由貿易を前提とした、エネルギー等の供給網の混乱は、インフレの長期化につながります。
移行期には、人的資産の価値の減少に合わせて、計画的に株式等のリスク資産への配分比率を減らす時期です。
年金生活期は、金融資産の活用が生活の柱となりますので、年齢を重ねると共に適切な水準まで、安全資産の配分比率を高めます。