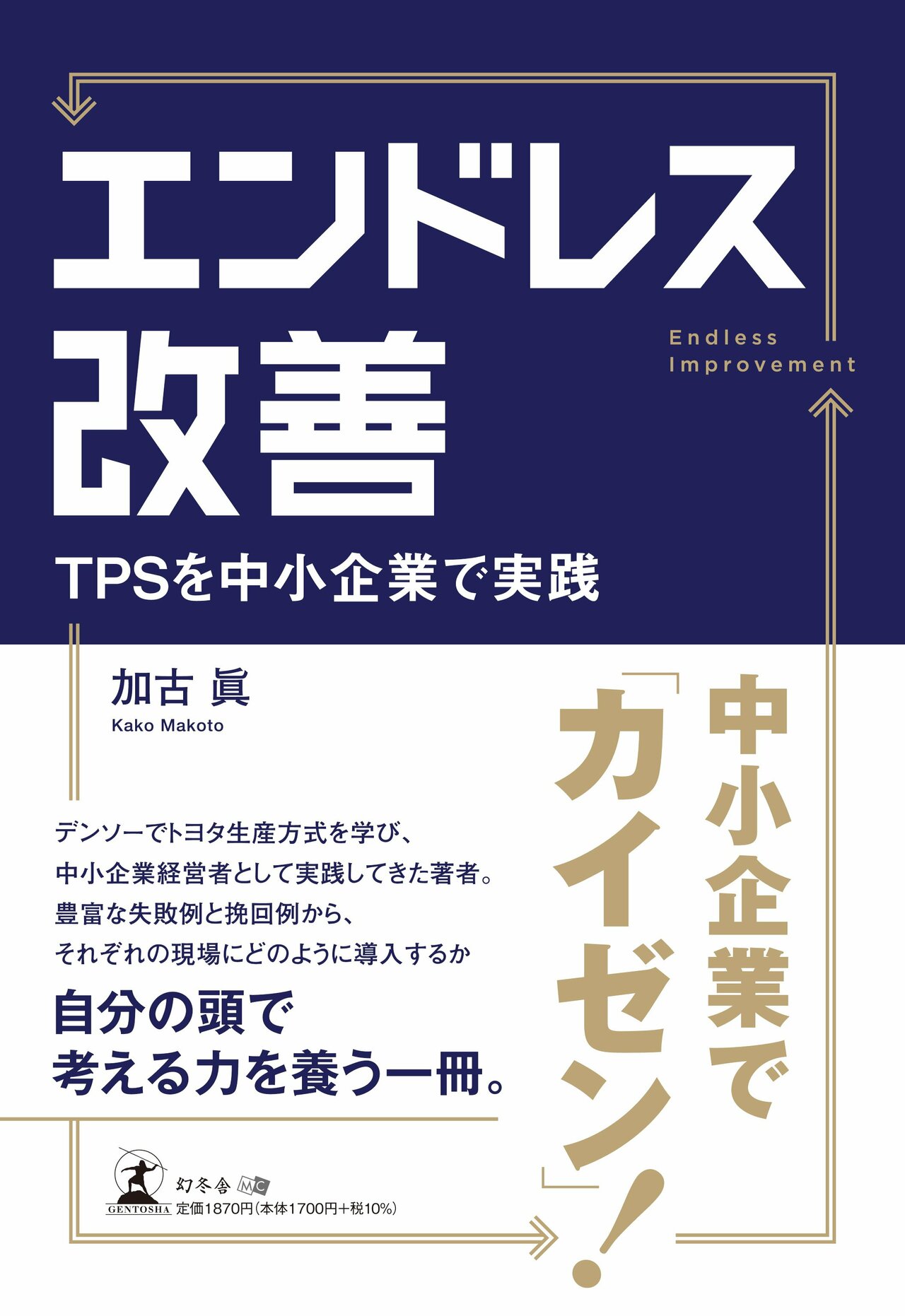こんな具合で、それぞれの部品在庫、製品在庫を①、②、③、④、+⑤(安心分)に分けてみる。例えば、②の振れ分は「0・2日分」、③は、製品が客先ラインとの同期度合いにもよるが0・3~0・8日あたりで決める、前工程、仕入先部品も段取り替え実力や輸送のリードタイムも考えて決める。
④は、先述のように生産技術、保全と相談する。ここらあたりをキッチリとやっていくと、曖昧な「安心分(⑤)」の実態が見えてくる。ただ、理屈だけでは決めにくいところも出てくる。私の経験では、2つの現実解を使ったことがある。
(1)小ロット化は、段取り替えの現実的な目標が稼働時間の1割程度としてみる。
(2) 理屈、計算で出しにくいところは、過去の経験・実績を見て「時々在庫がなくてヒヤヒヤする程度。
ここで理解していただきたいのは、「多すぎる在庫」のために、前後の工程でそれぞれの抱えている問題点が浮き出てこないことを防ぎたいということ。
小さくても目立たない、または慣れっこになっている頻発停止(チョコ停という人もいる)が、在庫のために見えない、目立たないのはダメということ。改善のニーズが消えてしまう。
このように考えれば、在庫の量、状態を適正にすることにより見え難かった問題点を浮き上がらせ、改善ニーズを湧き上がらせて、催促する有効な道具となる。
指導する場面では、「在庫が多い!」という発言だけでは、受ける人達が「何のための在庫低減」なのかを腹に落とせずに反発ばかりが起こり、言われたことだけをイヤイヤやっておこうと曲がってしまうケースを幾度も見てきて、残念であるし、助けてあげたいと思う。
【イチオシ記事】ずぶ濡れのまま仁王立ちしている少女――「しずく」…今にも消えそうな声でそう少女は言った
【注目記事】マッチングアプリで出会った男性と初めてのデート。食事が終わったタイミングで「じゃあ行こうか。部屋を取ってある」と言われ…
【人気記事】「また明日も来るからね」と、握っていた夫の手を離した…。その日が、最後の日になった。面会を始めて4日目のことだった。