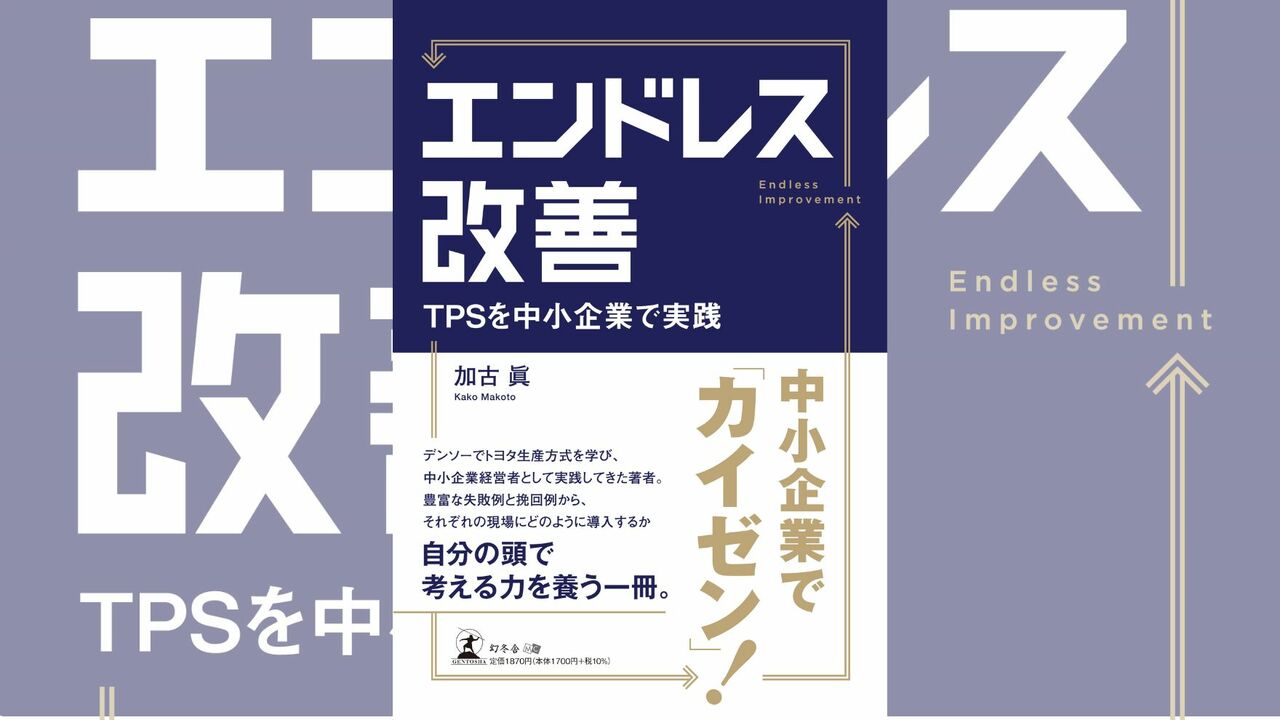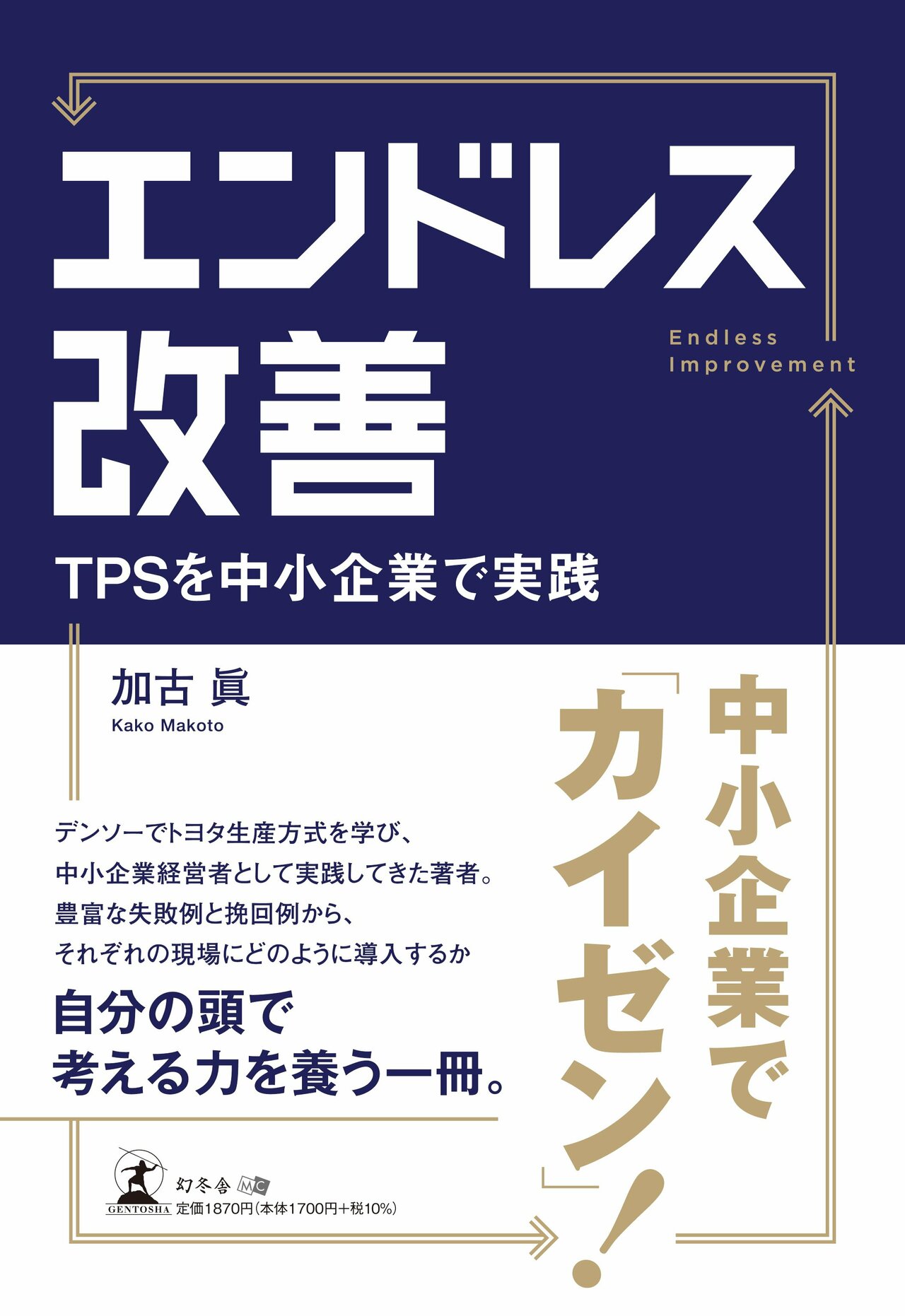【前回の記事を読む】捨てるゴミにも企業改善の可能性がある!? いつも何気なく捨てているゴミを分別してみると......
第3章 基礎段階
2 まず「問題点を見つけやすくする」行動をしよう
事例(2) 簡単な層別でOK!(ねじ加工会社での不良発生対策)
2009年頃の話、エアコン部品の小ねじに加工不良があり、組付けできないというトラブルがあった。このねじの製造は、岐阜県にある仕入先の担当だった。この会社は社長の他に奥様ともう1人の従業員の3名という規模。
トラブル発生時には、エアコン組付け工程と仕入先からの入荷品を全数選別して、当面の良品確保をしたのちに現地へ出かけた。ねじの転造機が3台あって稼働中であった。社長から、問題発生工程の説明と、当面の流出防止策の説明を受け、現場へ。
その時点では、まだ不良発生が完全に止まっていない状況だった。投入材料、設備本体、及び設備に付加された搬送レールの中のいろいろな要因が絡み合って、不良が発生していて奮戦されているとのこと。
私は、若い従業員の方にお願いして、ホームセンターでポリバケツを3個購入してきてもらった。色違いの3つのバケツに不良形態ごとに油性ペンで明示し、発生の都度、各バケツに放り込んでもらえるように頼んでその場は退散した。
その後、1週間もしないうちにそれぞれの要因別に対策が取られた結果、不良が激減した報告を聞いた。自分でやり切れなかった後ろめたさもあったが、社長自身が自分自身で問題点を要因別に対策し再発防止してもらった話をうれしく聞いた。結果的には、それで良かった。
ちょっとした分類で、見え難かったものが見えやすくなり、改善の効果も正確ではないにしても掴めたために、自発的な活動が主体的に進んだと思う。
生産現場での、不良対策というと頭から「データ取り」「分析」などとその現場に合わない、自分中心の指導、要請を言いがちだが、図らずも手抜きの「言いっぱなし」がラッキーだった。
問題点を見えやすくする手段であったことを、言い忘れたが……多分わかっていただけたと思う。
後から考えると、バケツの内側に何本かの線を書いて、もう少し定量的なアプローチをしたほうが良かったのかもしれない。または、もっと小さなバケツか小箱でその個数でカウントする方法もあった。さらには、現象別だけでなく、要因別に分類できたらもっと面白いと、後で感じた。