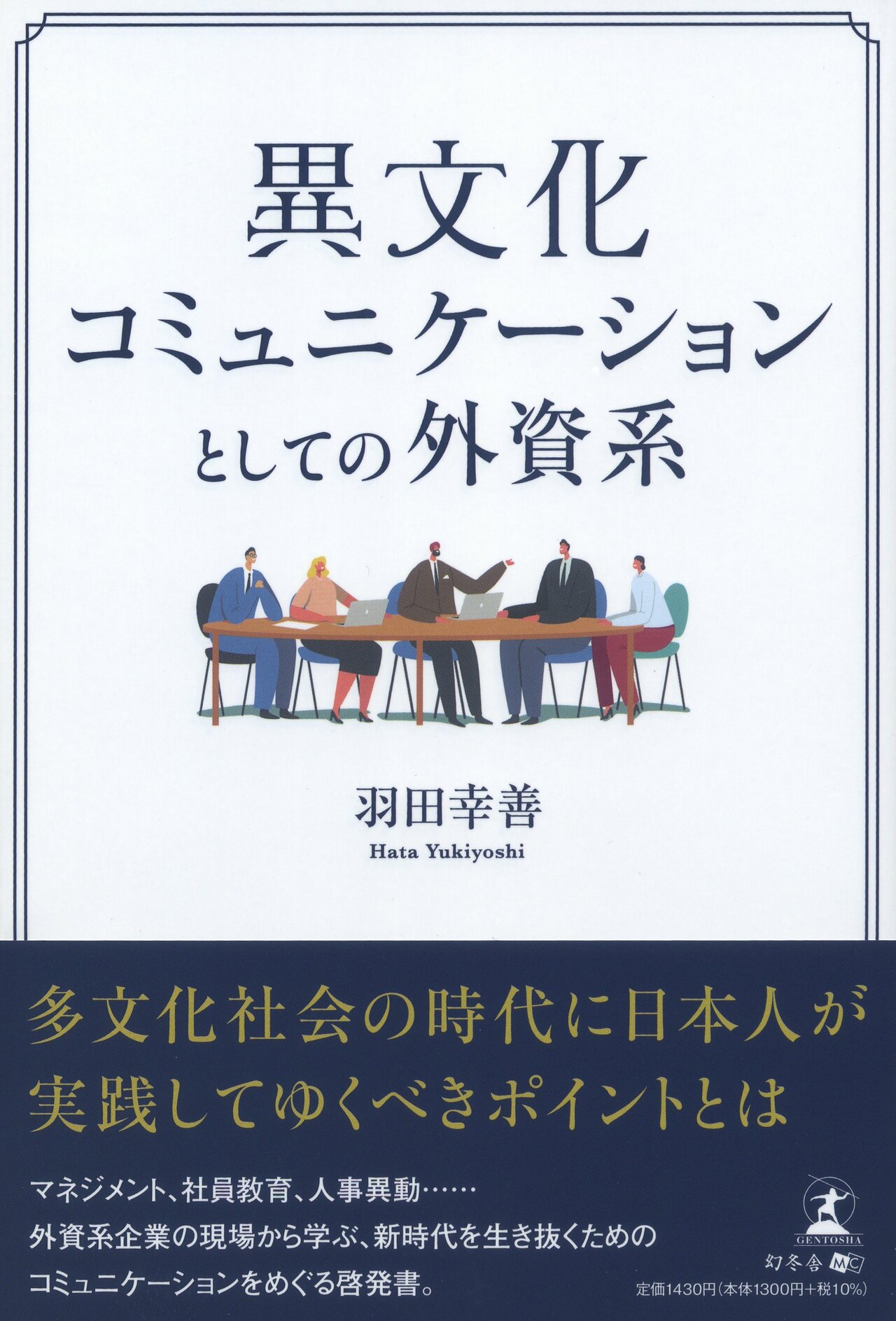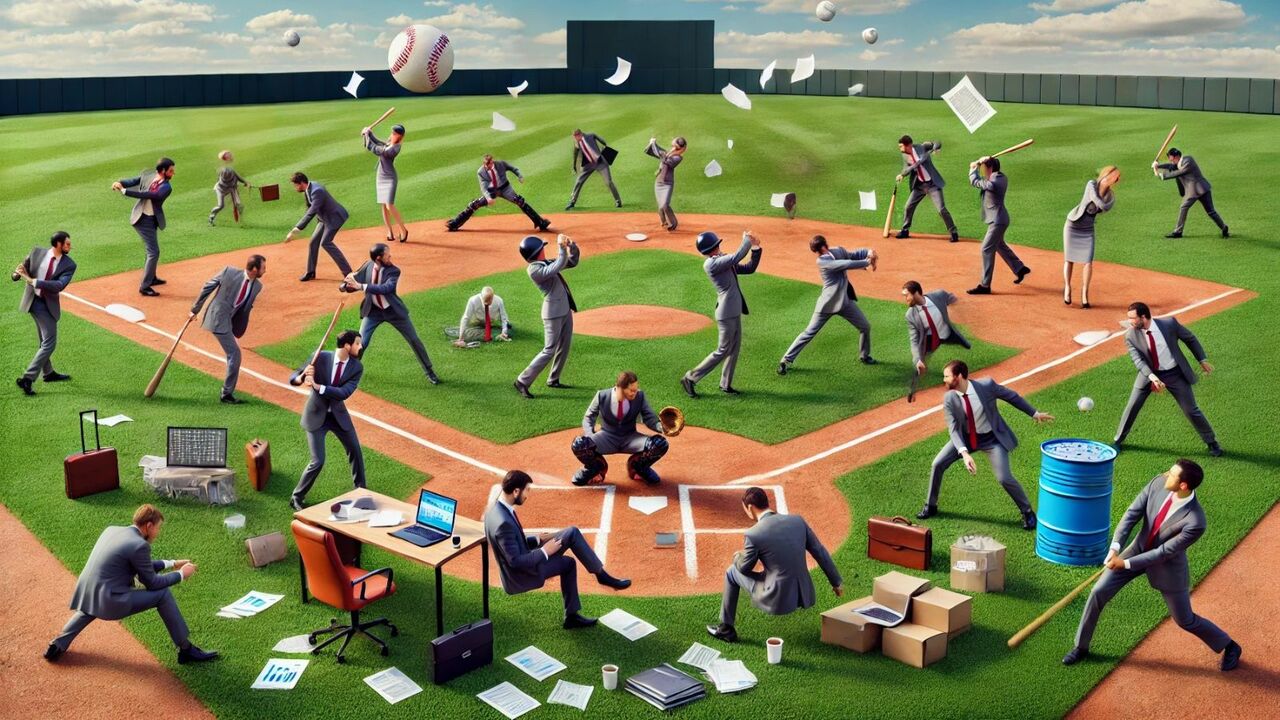競争が激化しているなかで、優秀な人材の獲得は会社の将来を左右します。他の業界や競争相手で経験を積み、専門知識を磨き、スキルを身につけた人材が入ってくる会社と、自分の会社でしか経験のない人材だけがいる会社とが競争するわけです。人材は会社の競争力に影響を与える数多くの項目の一つであり、これのみで会社の将来が決まるわけではありませんが、人材は会社の将来にとって非常に重要な要素であることは確かです。
また、この本の後の方でも触れますが、「純粋培養」だけでなく、さまざまな面で日本の企業は外国の企業と異なっています。必ずしも違うことイコール悪いことで改めるべきという意味ではありませんが、競争上で不利になるようでしたら問題です。それでも日本国内でビジネスをしている間はまだいいのですが、日系の「外資系」として海外でビジネスをする場合、不利になることがかなりありそうです。
広い意味での日本式のビジネス・マネジメントは、多くの会社が海外に進出するにともない、大きく変更を迫られているのではないでしょうか。
会社のビジネスに疎い専門家社員の増加
「純粋培養」する日本の会社では、新卒に対してだけでなく、入社後何年かたった社員に対しても、定期的に一定の教育訓練を会社として行なっています。新卒社員を対象とした基本的な教育項目の一つは、当然のことながら入社した会社の本業、その会社のビジネス自体にかかわる教育です。新卒社員は、そういった初期教育を受けることで、入社した会社のビジネスについて知ることができると共に、企業人としての基本も身につけることができます。
しかし必要な社員をその都度外部から採用することが多い外資系では、日本の会社で行なっているような新入社員の初期教育や、本業にかかわる基本的な教育を体系的に行なっているのは少数派でしょう。
というのは、必要としている人材は新卒のようないわば白地の人材ではなく、ジョブ・ディスクリプションに記載されているような、必要としている分野にかかわる専門知識や経験・スキルを持った、即戦力になる人材、つまりスペシャリストだからです。
さてこういった採用が何年も繰り返されるとどういうことが生じるか。結果として生じるのは、本業すなわち自分が働いている会社のビジネス全般に関する基本的な知識は少ないけれども、担当する限られた分野については専門知識や経験のある人たちが集まった、一種の専門家集団の組織ができあがることです。これは、新卒に対する初期教育から始めて、必要な専門知識を順次習得させる、日本的な社員教育をしている企業では絶対にあり得ないことです。
【イチオシ記事】ずぶ濡れのまま仁王立ちしている少女――「しずく」…今にも消えそうな声でそう少女は言った
【注目記事】マッチングアプリで出会った男性と初めてのデート。食事が終わったタイミングで「じゃあ行こうか。部屋を取ってある」と言われ…
【人気記事】「また明日も来るからね」と、握っていた夫の手を離した…。その日が、最後の日になった。面会を始めて4日目のことだった。