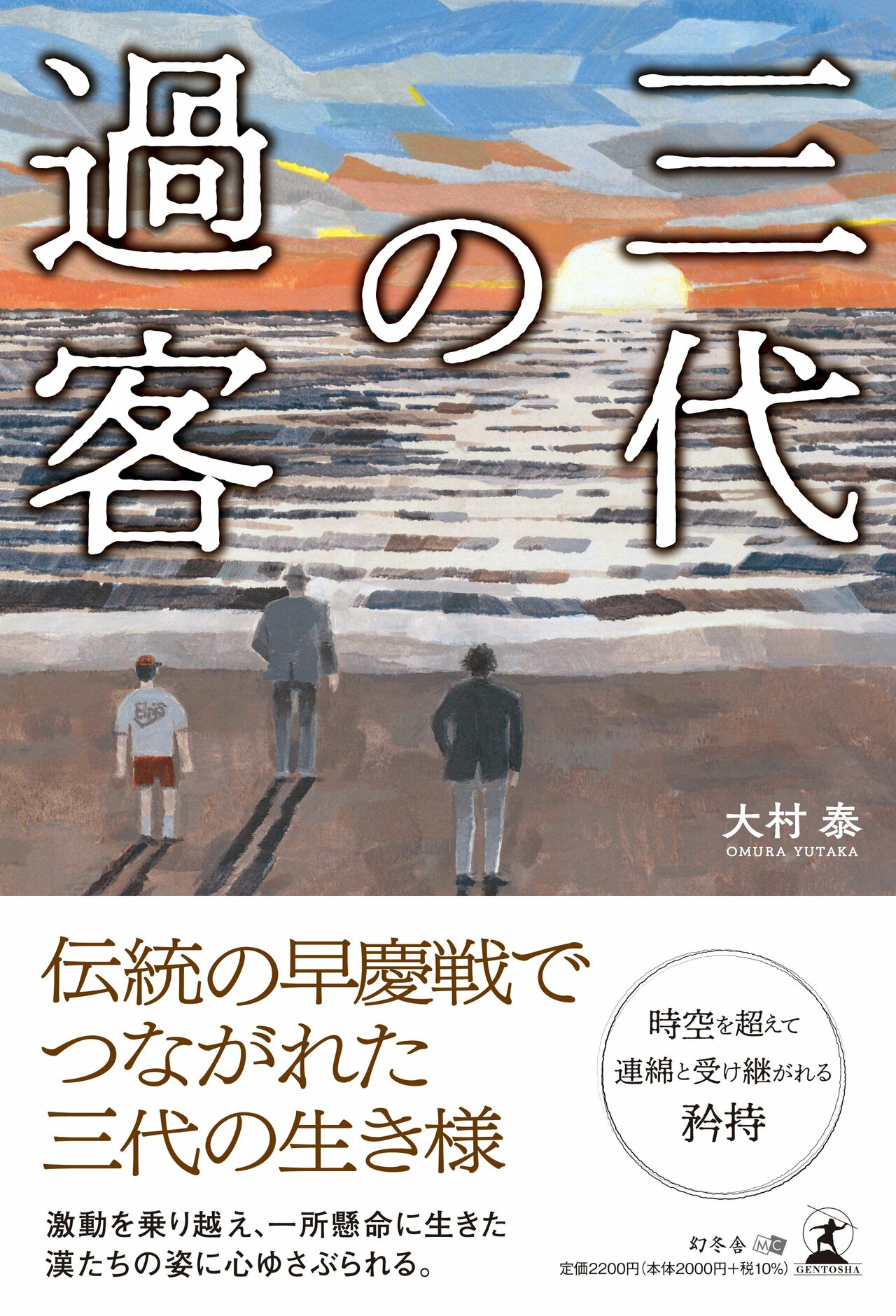第2章 一苦一楽 〈二〇〇五年夏〉大山諭、影の主役
慶大付野球部三年生の大山諭(さとる)はベンチ入りがかなわず、八月十五日、甲子園球場の応援席にいた。チームの仲間とともにユニフォーム姿でメガホンを打ちふるう後ろ姿に背番号はない。
六月二十八日、地方予選抽選日の前日。監督がベンチ入りメンバーを発表した。二十人のなかに彼の名前はなかった。その日、立つ瀬が同じ仲間と思う存分に泣いた。
翌日から与えられたミッションは対戦校の偵察。克明にメモを取りビデオを回す。活躍の場は縁の下でも、晴れ舞台への道程に、いくばくか貢献していると己に言い聞かせるほかない。
「ベンチ入りできなかった。残念です。子どものころバットやグローブを買ってもらった。何度もキャッチボールしたり、ノックしてくれたのに……期待に沿えなくてごめんなさい」。
翌日、諭は国際総合医療センターで療養中の祖父草壁俊英(くさかべとしひで)に頭を下げた。
【前回の記事を読む】師匠から届いた「五か条の御誓文」―これが心の師匠の「遺言」となってしまうとは…
【イチオシ記事】あの人は私を磔にして喜んでいた。私もそれをされて喜んでいた。初めて体を滅茶苦茶にされたときのように、体の奥底がさっきよりも熱くなった。
【注目記事】急激に進行する病状。1時間前まで自力でベッドに移れていたのに、両腕はゴムのように手応えがなくなってしまった。