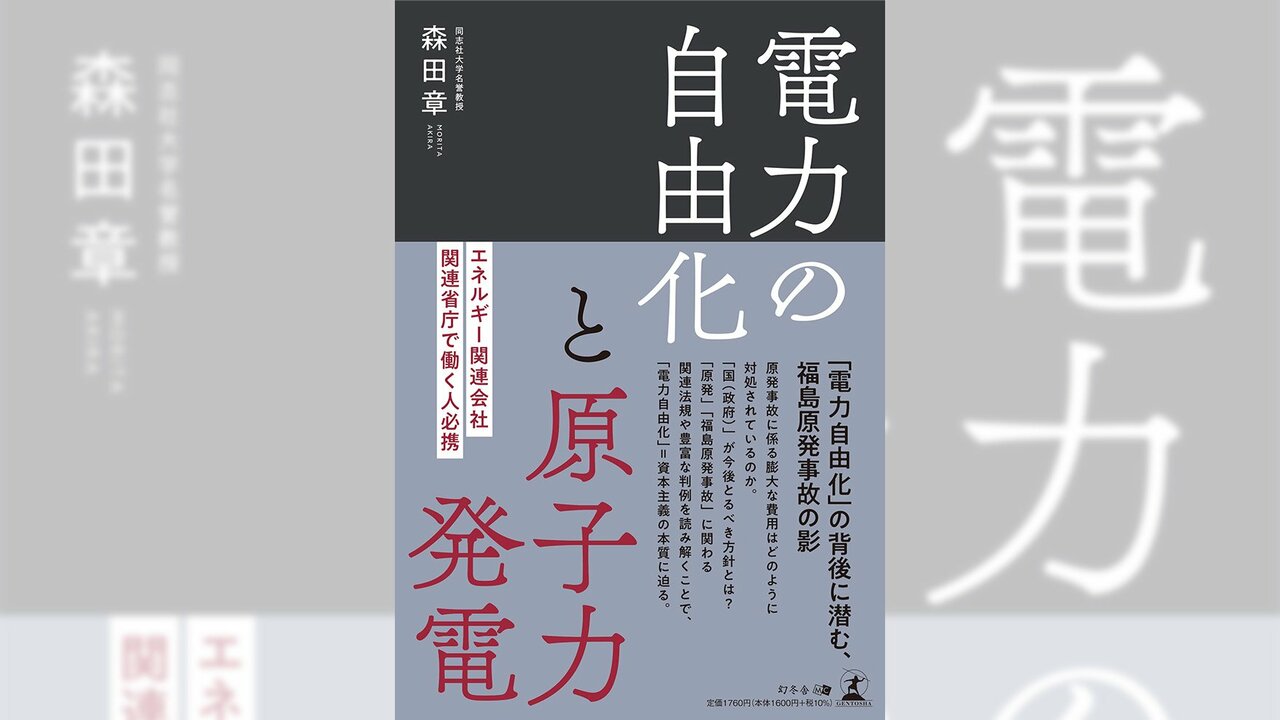第1部 電力会社のコーポレート・ガバナンス
1.原子力発電と電気料金
1‐6 電力会社の経営者の行動
①独占事業としての電力会社
米国においても1980年代の後半までほとんどの政治家は公益事業会社の競争などということを考えていなかったようである。
何十年にもわたって電気事業は発電設備を建設し、あるいは他の電気事業者と契約してそれらの地域の消費者に対する役務提供の義務を履行してきた。
電気事業は、資本コストが高いことおよび規模の経済性から自然的な独占であると認識されてきたことが理由となって、公益事業としてそれらの役務提供地域において大口顧客および個人顧客の両者に対して電力を提供するという政府の課した義務を負わされてきた。
その代わりに、規制当局は、それらの役務提供の不自由な市場を補償してきた。規制当局は、公益事業が消費者の行動に影響を与えることおよび市場の展開を奨励することを要求し、その見返りとして公益事業はそれらの投資に対する適切な収益の補償を主張してきたのである。
ところが、1982年にバージニア電力のCEOが発電の規制緩和と電力業界における卸電力売買の提案をするなどの動きが生まれてきた(Richard Pierce, Public Utility Regulatory Takings:Should the Judiciary Attempt to police the Political Institutions? 77 Georgetown L. Rev. 2031, 2073〈1989〉)。
そして、いまや電力業界の規制緩和がかなり進んできたといえるようである(Leigh Martin, Deregulatory Takings:Stranded Investments and the Regulatory Compact in a Deregulated Electric Utility Industry 31 Georgia L. Rev. 1183〈1997年〉)。
1997年の調査では、アメリカ人の25%が完全な小売り競争に向けた方針を持つ州において生活しているという。
②公益事業会社と株主利益の最大化
コーポレート・ガバナンスの本質的な議論として、バーリーとドッドの論争が有名である。バーリーは、経営者は株主の利潤極大化のために会社を経営すべきであるとしたのに対して、ドッドは、当時の労働不況等を考慮して、経営者は労働者などのステークホルダー(利益関係者)のためにも会社を経営すべきではないかと主張した。
バーリーは、もし経営者が株主の利益以外のものの利益を図るように経営するとなると、その成果の評価ができなくなり、経営者は誰からもコントロールされなくなるから、経営者の評価基準として株主利益の極大化が必要であるとした。