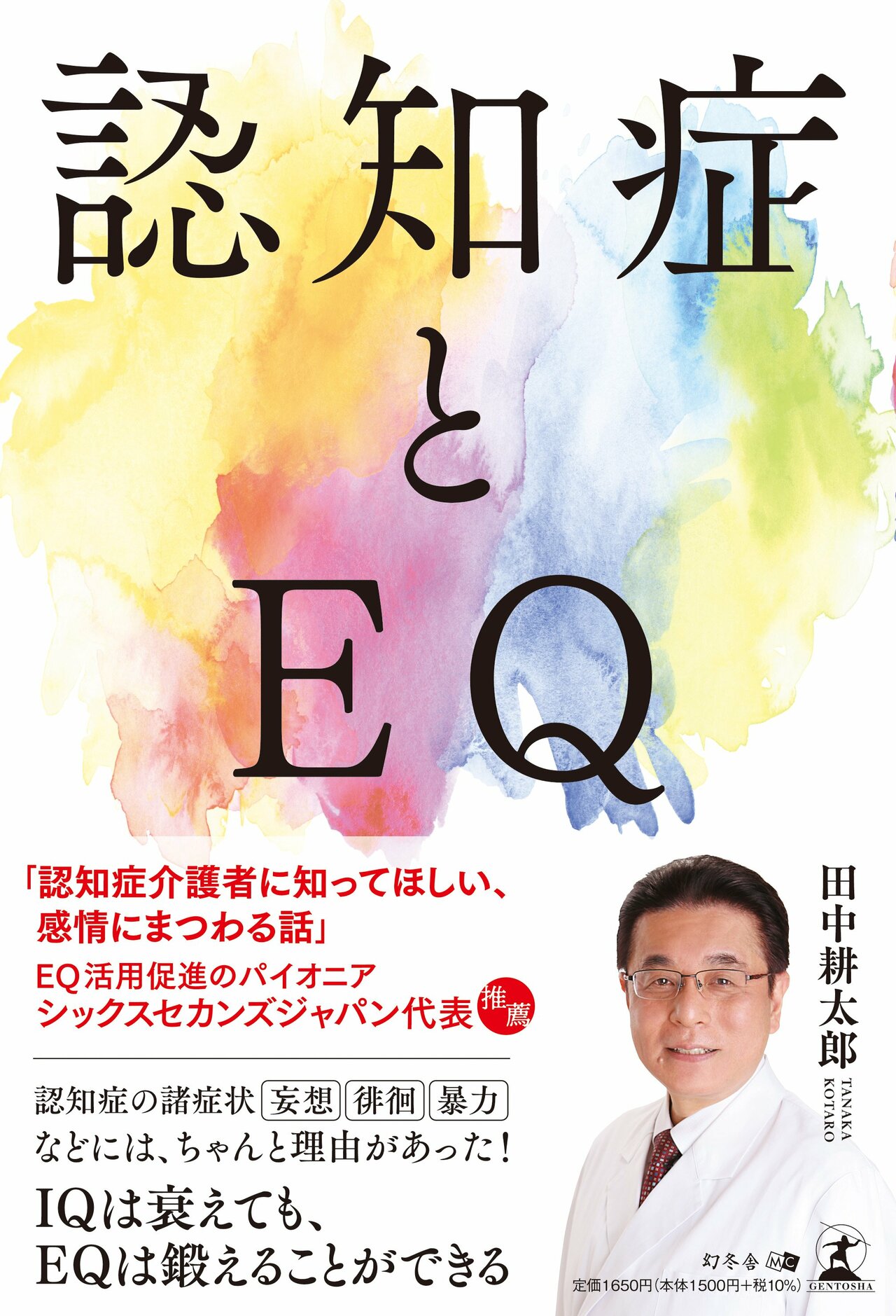非認知能力としてのEQ
子どもの教育において非認知能力の重要性が認められるようになっています。非認知能力を鍛えることで子どもと両親や教師との間のコミュニケーションがうまくいったり、集中力が増したり、忍耐力が増して効率良く自己管理ができたりして、結果的に学校の成績、つまりIQの向上も期待できます。
「ペリー就学前プロジェクト」においては、就学前の児童に対してアクティブラーニングが行われました。その結果非認知能力が向上したと考えられたわけですが、特に幼児における非認知能力は成長後のEQにつながっていきますので、どのような非認知能力が存在するのか、いくつか具体的な例を見ていきましょう。
感動する能力
まず、子どもにとってのEQの重要性を語る文章の中で、子どもと大人を比較するものがありましたので紹介します。
子どもたちの非認知能力、笑い、読解力について書いてきました。では大人たちはどうなのでしょうか? ちょうど良い例が「チコちゃんに叱られる」というNHKの人気番組で紹介されていました。「なぜ大人の時間は早く過ぎるのか」というテーマです。
番組では大人の代表としてタレントの岡村隆史さんが、子どもの代表として小学生が登場していました。小学生と岡村さんには「日曜日に何をしましたか」というような質問が出され、小学生はたくさんのことをしたと答えていました。いっぽうの岡村さんは家でボーっと過ごしていただけ。
岡村さんだけでなく、多くの大人がそういう毎日を送っています。大人は経験を積んでいくので、成長するにしたがって新しいことに遭遇することが少なくなります。毎日起こることは子どもも大人も同じですが、子どもは、お母さんがウィンナーをタコの形に切ってあげると喜び、大人は「今日のおかずはウィンナーか」と考えるだけ。そこが子どもと大人の違いです。
(『EQトレーニング』 高山直 日経文庫 2020年)
【前回の記事を読む】【教育】"非認知能力"を学べば、持ち家率など生活水準が上がる…逆に、学ばなかったら犯罪率や生活保護受給率が上がる!?
【イチオシ記事】喧嘩を売った相手は、本物のヤンキーだった。それでも、メンツを保つために逃げ出すことなんてできない。そう思い前を見た瞬間...