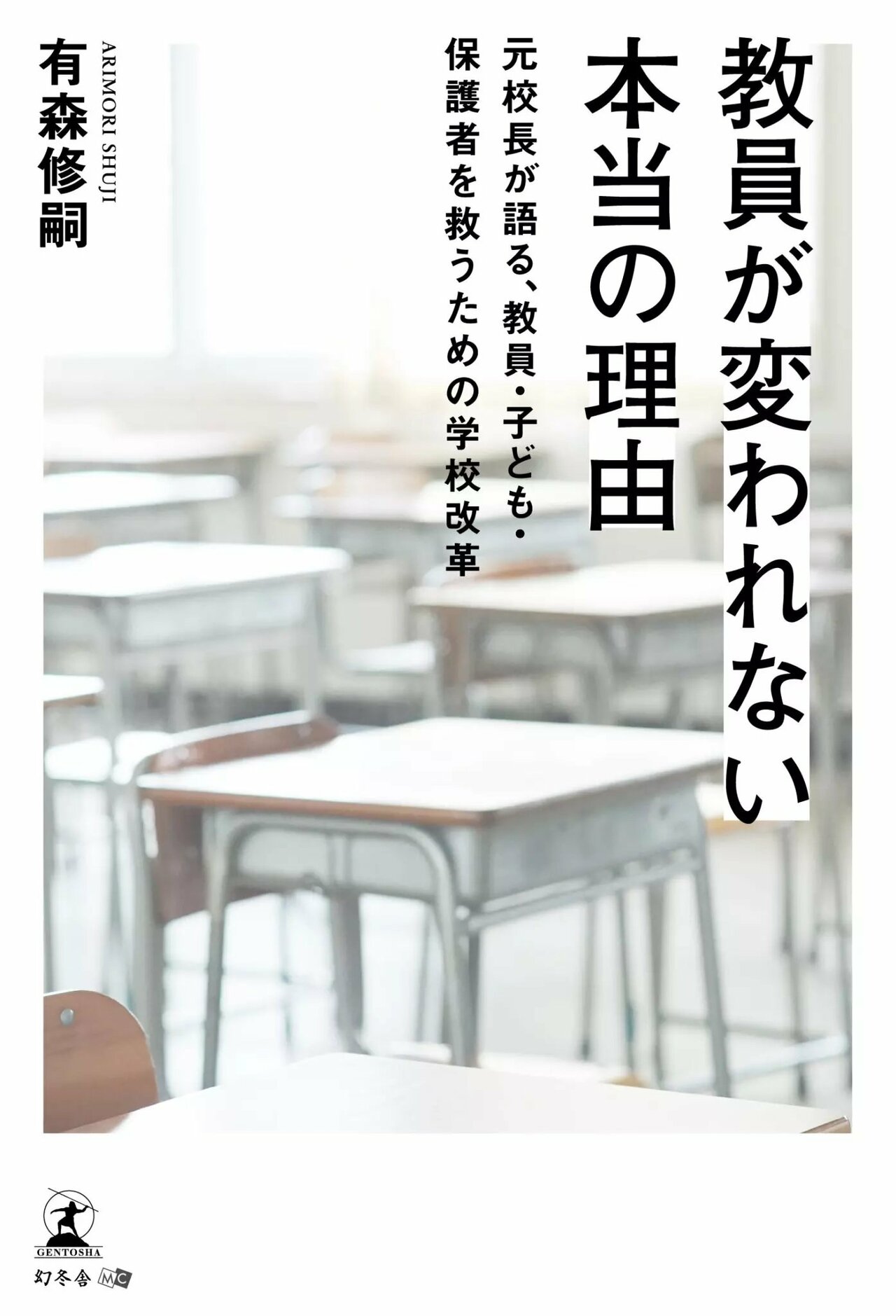価値が共有されにくい社会
価値観の多様化によって相対化が進んだ社会は、さまざまな価値が乱立する。そして、私事化傾向が強まれば、自分の人生をいかに豊かにするかが最大の関心事となり、個々の自由や個性はこれまで以上に尊重されるようになる。
それは、社会によって抑圧されてきたものが解放されやすくなる社会でもある。だからこそ性的マイノリティーへの偏見や、さまざまなハラスメントに耐えてきた人たちを苦しみから解放することに道が開かれた。
しかし、人々は自由や個性が認められれば認められるほど、ある種の不安を感じるようになる。決められたレールの上を走っていれば将来に何か良いことがあると思えた時代は、悩むことも不安に感じることも少なかった。
極端な例だが、江戸時代のように身分制度が固定的だった頃なら、自分が将来どんな職業に就けばいいのかということで迷うことはほとんどなかっただろう。いまはすべての人に職業を自由に選択する権利が与えられている(少なくともそう思われている)。仕事を人生の中心に置くか、趣味を真ん中に置くかといった生き方も自分で決めることができる。
それは裏を返せば、すべての選択に対して自己責任が問われるということでもある。自由な社会に生きるには、そういう覚悟を持たなければならない。しかし、これだけ選択肢が増えた社会の中で一つを選ぶのは、そう簡単なことではない。
私は、教諭時代に高校選択を前にした生徒によくこんな話をした。
「学校を一つ選ぶというのは、他のすべてを捨てるということだ。捨てる勇気を持たないと、何も決められない」
選択肢が増えるということは同時に捨てるものが多くなるということである。選んだ後に「本当はあっちの方がよかったかもしれない」と後悔しやすくなる。
その上、相対化が進んだ社会は、同じ拠り所を共有することが難しいため、迷ったときに本当に親身になって考えてくれる人は少なくなる。
「これでいいんだろうか」と相談しても「あなたがそう思うのならそれでいいよ」という答えしか返ってこない。多様な価値を認めるのだから当然そうなる。
【前回の記事を読む】今どきの子がすぐ不登校になるのは、”ひ弱”でわがままだから? ――いいえ、問題は子どもの側ではなく、学校の在り方に…
本連載は今回で最終回です。ご愛読ありがとうございました。
【イチオシ記事】喧嘩を売った相手は、本物のヤンキーだった。それでも、メンツを保つために逃げ出すことなんてできない。そう思い前を見た瞬間...