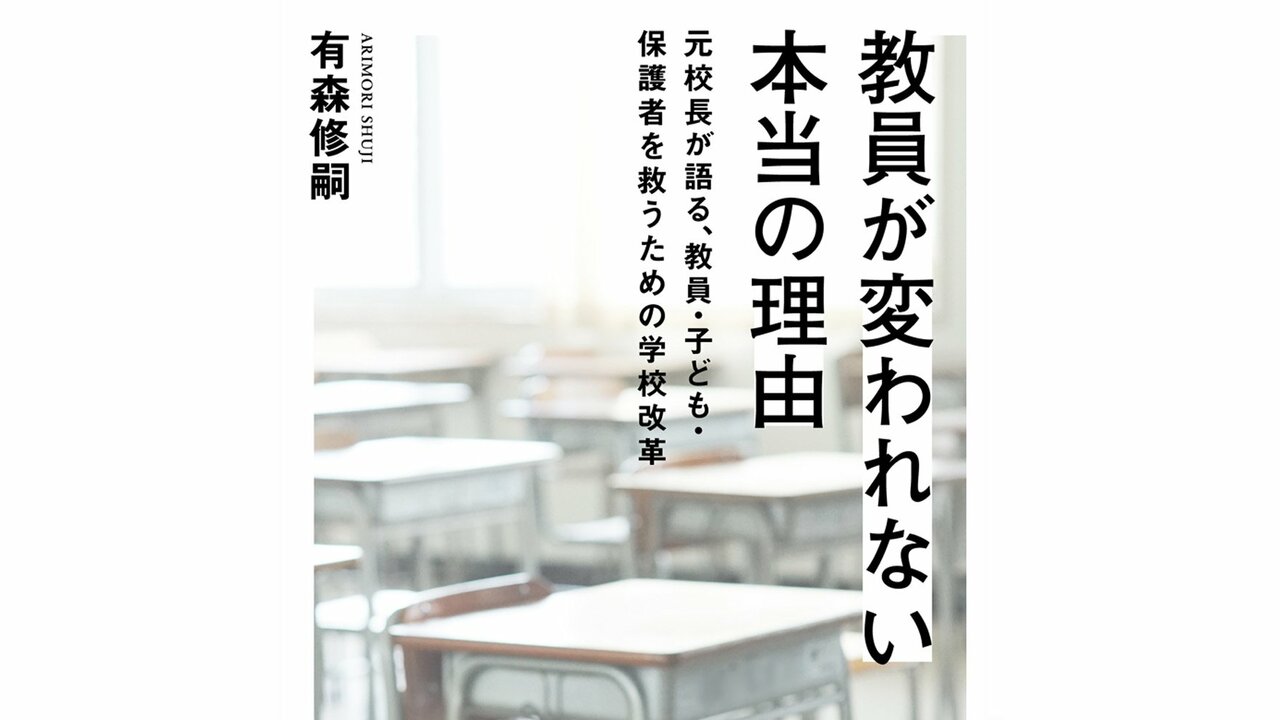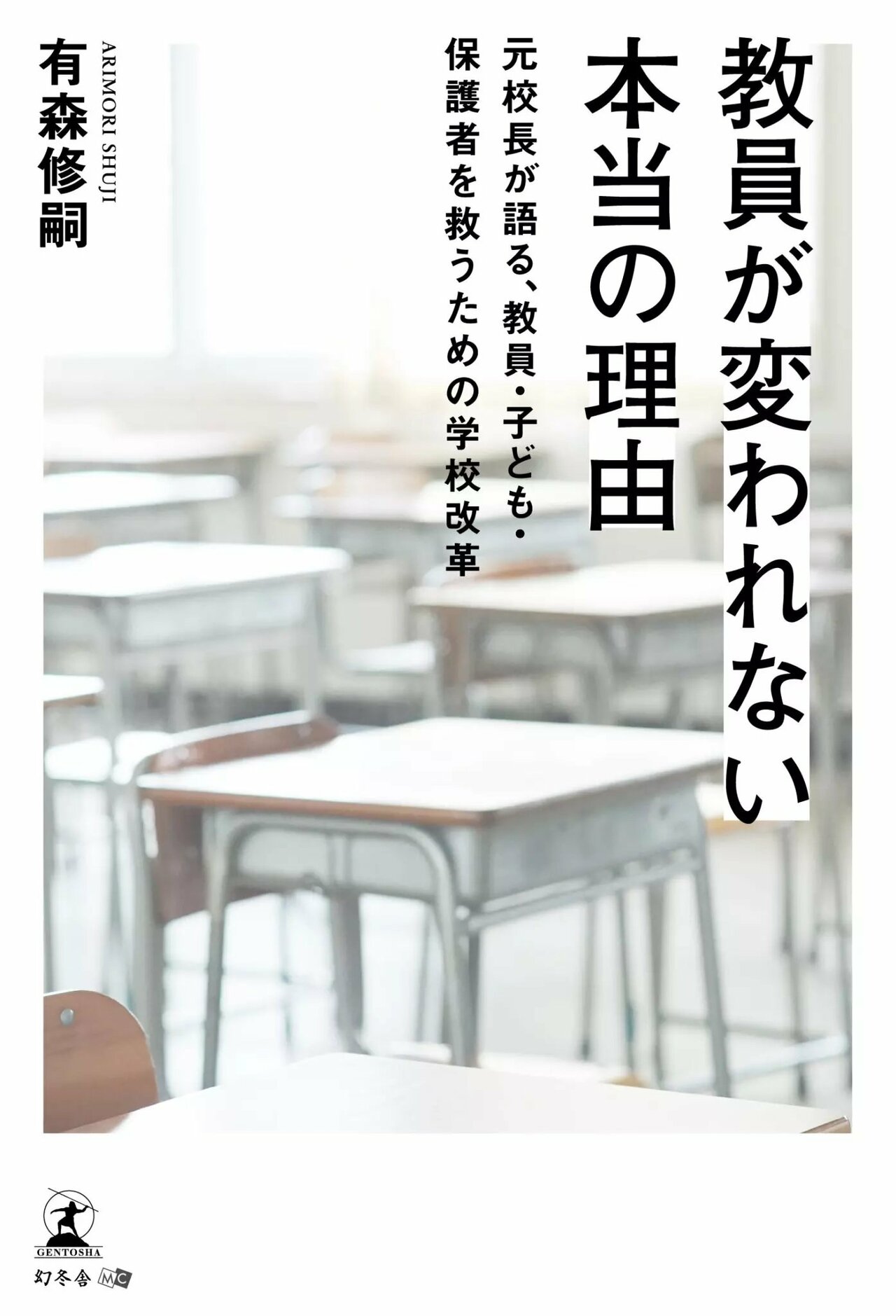四 相対化の正体
―学校相対化の中で生徒をどう理解するか―
(3)学校の相対化
私が最初に学校の相対化現象に出会ったのは『公立中学はこれでよいのか』という一冊の本だった。
それは、過熱する受験競争の一端としての現象であったが、同時に公立中学校の魅力のなさをも浮き彫りにした。この本の初版は一九九二年である。校内暴力など荒れた学校はまだ多く残っていただろう。
一般的に、校内暴力を力で抑え込んだリバウンドとして、いじめや不登校問題が浮上したといわれるが、そんなに明確な線引きができるわけではない。一九八〇年代後半から一九九〇年代初めの頃というのは、公立中学校に校内暴力といじめが混在していたと考えるのが妥当だろう。
そのため、問題の多い公立中学校に魅力を感じない保護者が都市部を中心に増えていったのである。
当時の都内某学習塾の塾長は次のように述べている。
「今の公立中学校の惨状は会社更生法を適用してもよいくらいにひどい。校内暴力やいじめなど、以前より下火になったとはいうものの、先生はその対策や生活指導に追われてばかりで、ろくに教科の研究もできていない。また、カリキュラムが私立と違って、英語が3時間しかないとか、時代にまったく合っていないし、高校受験を考えると不安だらけです。親などは、とにかく公立には絶対に行かせたくないという声が多いのです。」(秦、一九九二年、一五頁)
また、東京都教職員組合が実施した調査結果を引用し、次のように指摘する。
「……受験率では、東京都全体で平成3年度23・1%、ほぼ4人に1人が私立中学校を受験している。」(前掲、秦、一〇頁)
これは、私立中学校に進学を希望する児童が必ずしも成績トップクラスに集中していたわけではないことを示している。
公立中学校に生徒をつなぎとめるだけの魅力がなければ、こうしたことが起こるのである。いまでこそ校内暴力は沈静化しているが、いじめはまだなくなっていない。その上学校が〝ブラック〟とまでいわれる現状にあっては「ろくに教科の研究もできていない」状況は、当時と変わらないだろう。
ただ、この頃はまだ公立中学校にも望みがあった。
一九八〇年代後半になると、荒れた学校は徐々に減っていったし、深刻ないじめはあったものの、一九八六年には、森田洋司氏によっていじめの四層構造が明らかにされた。この研究は全国の教員に希望を与えた。
すなわち、最も学校的な価値を受け入れている存在である「傍観者」の子どもを学校側に引きつけることができれば、いじめは減っていくのではないかという期待がそこに生まれたのである。「傍観者」層へのテコ入れは比較的容易にできると考えられた。
ところが、一九九〇年代半ばに、全国各地で小中学生の自殺事件が相次ぎ、いじめ問題は、いわゆる「第二の波」を迎えることになる。公立中学校の「ソーシャル・ボンド」(引き付ける力)は、さらに弱まっていく。