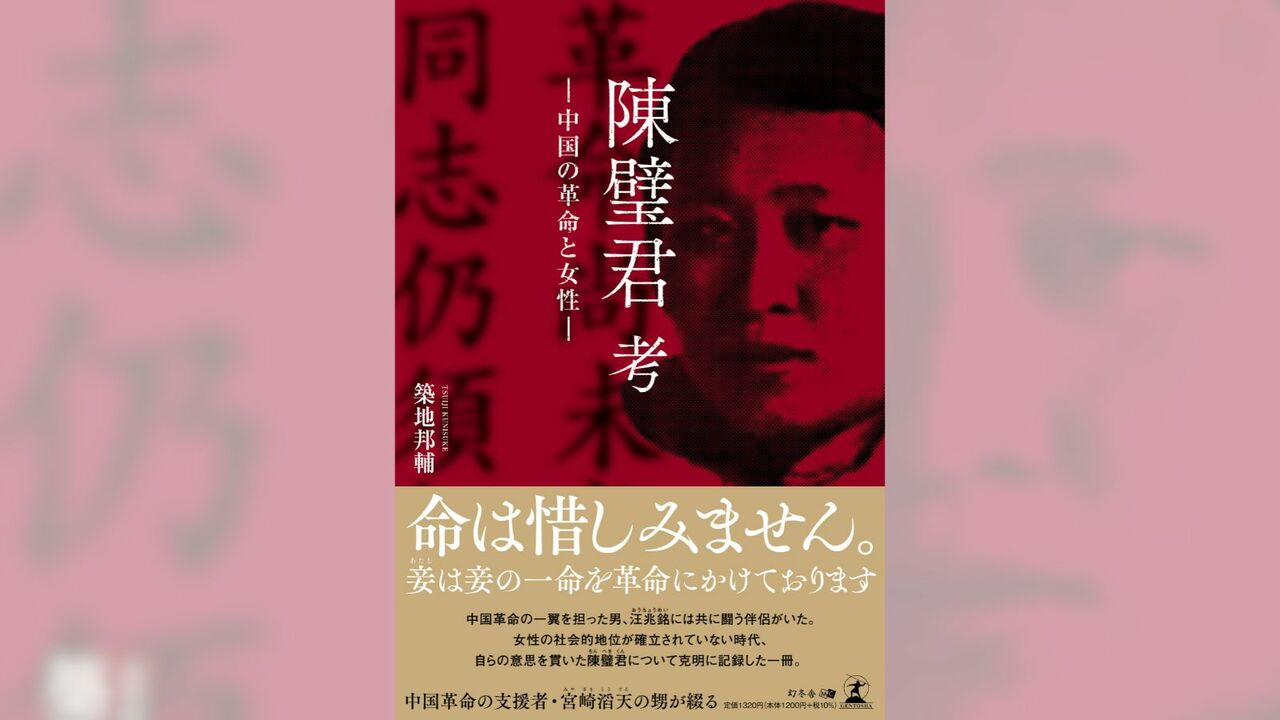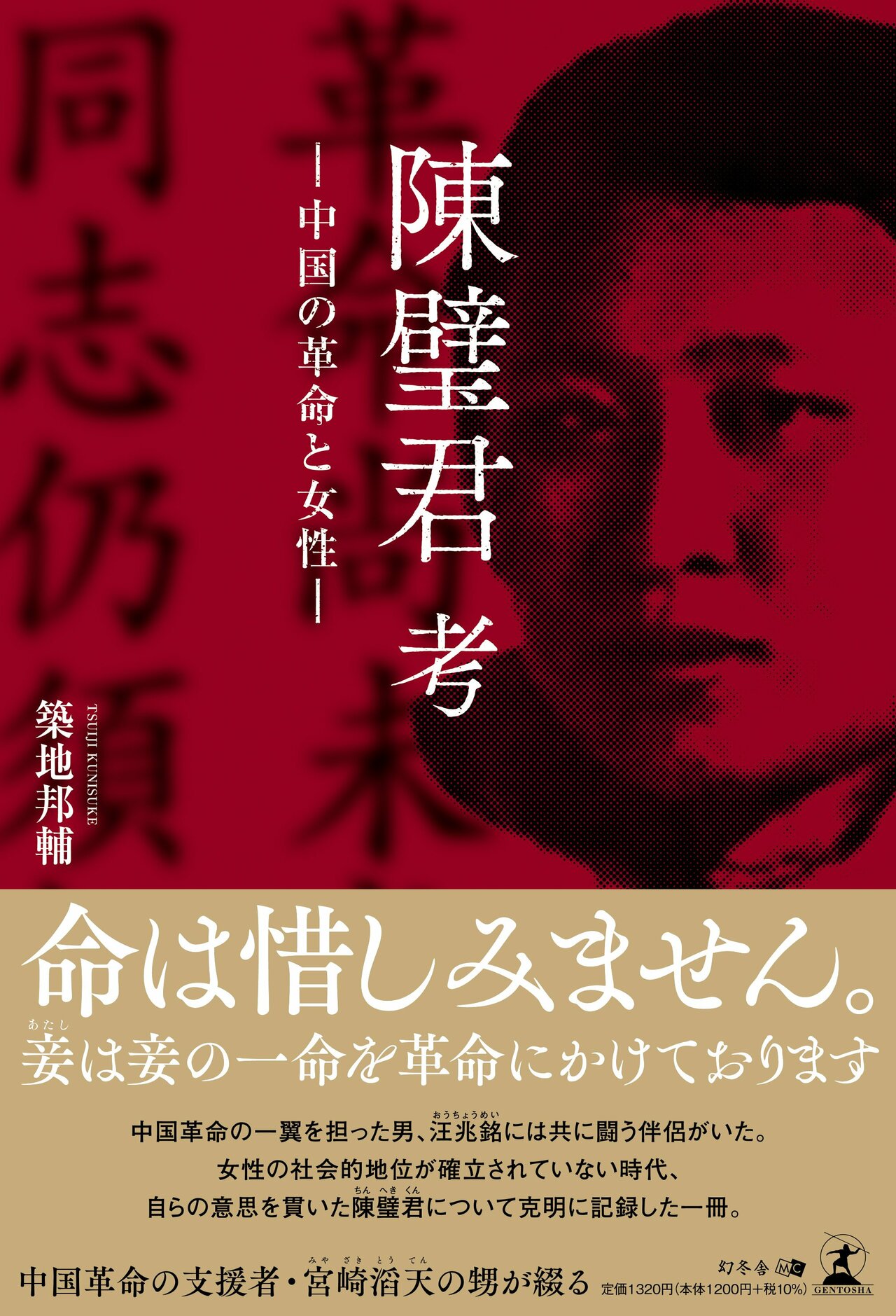第一章 ハレー彗星、現わる
一九一〇年(明治四十三年)の初夏、四月も末(すえ)っ方(かた)の頃。
九州、熊本地方も、雨期と言うにはまだ早い季節だが、来る日も来る日も五月雨の走りとでも言いたいような、小雨降る毎日であった。その雨上がりの夕暮れのことである。
珍しく雲の流れの合間から、チョイチョイ青空が拡がり始めていた。
西空にパッと入り日の光がさしたかと思う内に夜の帳(とばり)が下り始め、やがて空は星の座になり代わることであろう。その頃日本中の新聞は筆を揃えて、ハレー彗星という珍しい星が地球に接近する、という記事で賑わっていた。
この彗星の軌道計算によれば、地球との接近頻度は七十五年間に一度であるという。その年が今年にあたる。それも、今月、今日の夕暮れ、今、只今が現時点である。
もしこの彗星が地球に衝突することがあれば、或いはその尾鰭(おひれ)が地球に触れでもしたならば、地球に大異変が起こるかも知れないという説、又そんなことはないという科学者の学説もあった。しかしそれはそれとして、地球破滅説は流言として、田舎人の口から口へと尾鰭をつけて流れていった。
ハレー彗星が地球に衝突するかもしれない?
衝突したら地球は霧散する。地球上の生物は人間も草木も全部絶滅する。
この地球破滅説を聞いた者は、馬鹿でない限り一応怯(おび)えの表情を示した。だが、結局はさてどうしたらよいかとなると、仕方がないことではないか。その時はその時たい。考えることはなか、となる。
これが無知なる者の最高の知恵であり、武器である。そしてハレー彗星という怪物に敢えて関心を示さない。これが田舎の人の示した実態であった。