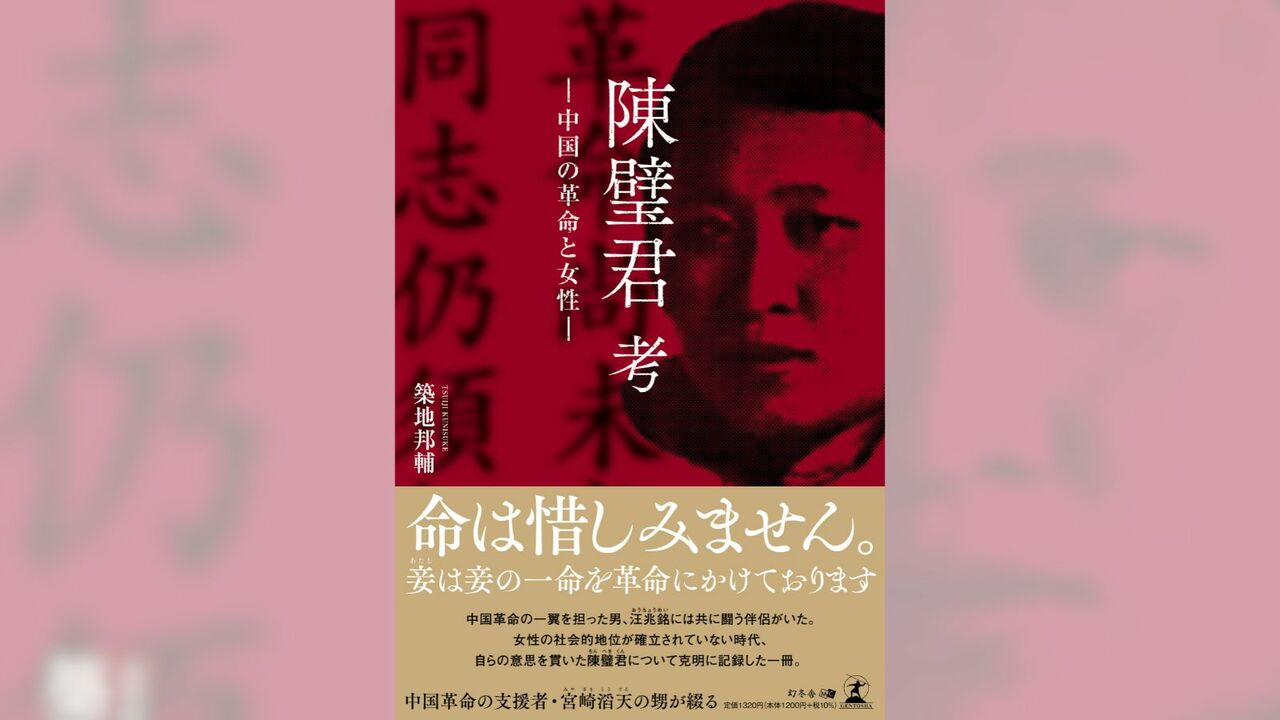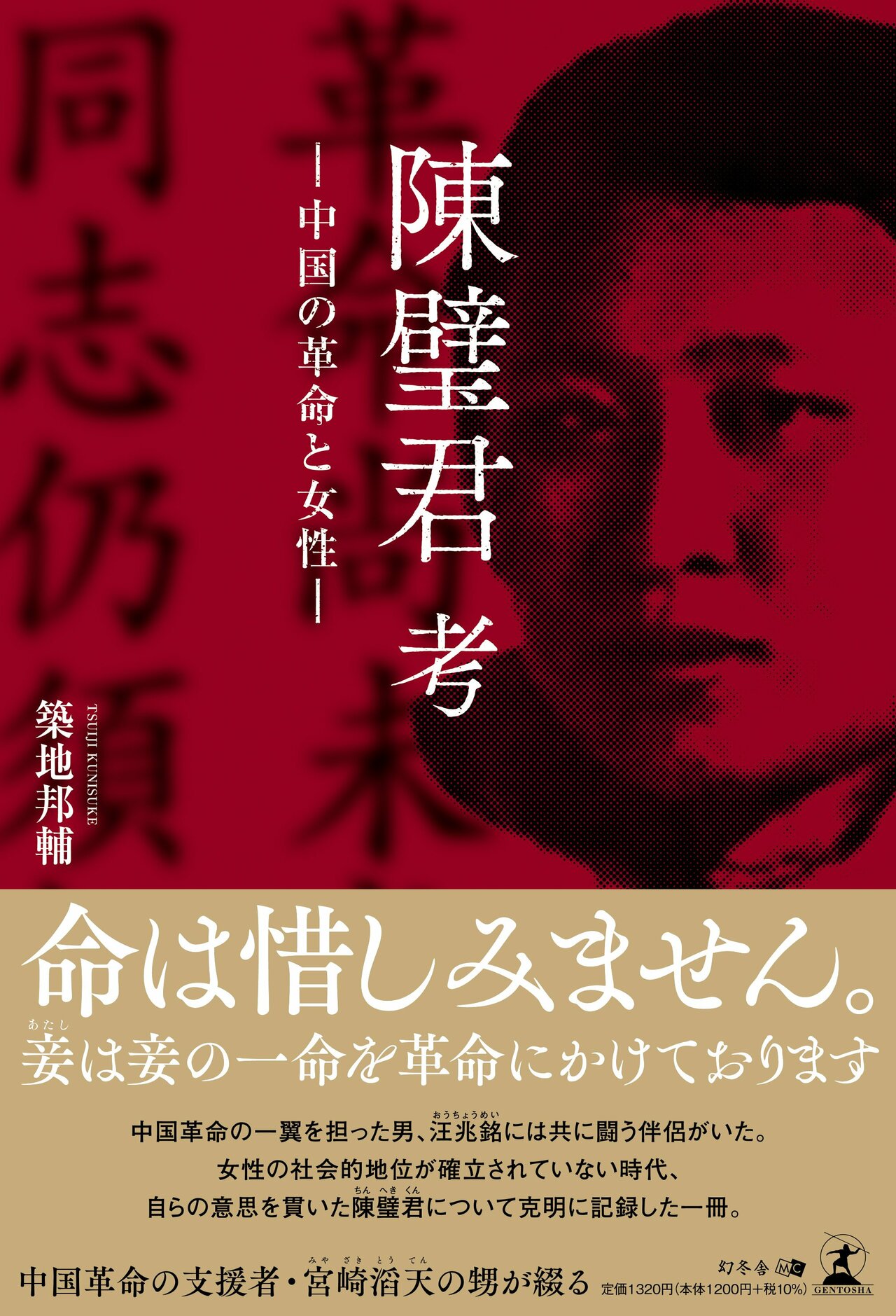【前回の記事を読む】「またか」と笑って東京を離れた孫文――国外追放の裏にあった清朝の圧力、そして日本政府の反応は…
第二章 中国革命の夜明け前
これが孫文の革命第一回の失敗であり、この失敗のため、孫文の首には花紅銀一千元の懸賞金がついた。清朝は孫文の行方を執拗に捜索し続け、清朝手持の刺客は孫文の命につき纏(まと)うことになる。
この時期、日露戦争は満州地域を戦場として、日本軍に有利な展開を示していた。その結果、清国留学生の日本在住者は年々増加する一方であった。そして留学生の殆ど全部の者が、清朝の封建政治打倒の情熱に結ばれていたと言ってよい。
今、その留学生の色分けを考えてみるのも無駄ではないと思う。一九〇四、〇五年(明治三十七、八年)、日露戦争の末期頃から清朝政府を批判する拒露倒清の同志政客は、ぞくぞくと中国を亡命して日本に来た。
その首領等と組織の主な活動は次の通りである。
一、康有爲(こうゆうい)、梁啓超(りょうけいちょう)等の保皇党。この一派は横浜を根城として、機関紙「清議報」、「新民叢報」を発行し、留学生にも大きな影響を与えていた。
二、孫文を領袖(りょうしゅう)とする進歩的革命主義者。廖仲愷(りょうちゅうがい)、その妻の何香凝(かこうぎょう)、汪兆銘、馮欽哉(ふうきんさい)、胡漢民(こかんみん)等がその一派で、孫文がハワイで組織した秘密結社興中会が基盤。その中心地は東京である。
三、黄興、宋教仁(そうきょうじん)等の華興会。黄興は一九〇三年(明治三十六年)、長沙で清朝打倒の兵を挙げたが失敗し、日本に亡命してきていた。東京にて雑誌「二十世紀」を発行し、留学生を指導した。
このように中国革命運動は、日本の東京、横浜を中心として、夫々(それぞれ)が機関紙、雑誌を発行し、夫々の組織の留学生に、進歩的、保守的な影響を与え乍ら、混沌たる革命思想の渦巻きとなり、実際行動への蠢動(しゅんどう)の温床を形作った。留学生の総数一万人にも達していたというから、その活動の如何に激しいものであったかが察せられる。
この混沌たる各派分立の対立抗争を心配し、これらの合作連合に心を配ったのが、日本の同志をもって任ずる犬養毅、宮崎滔天等であった。