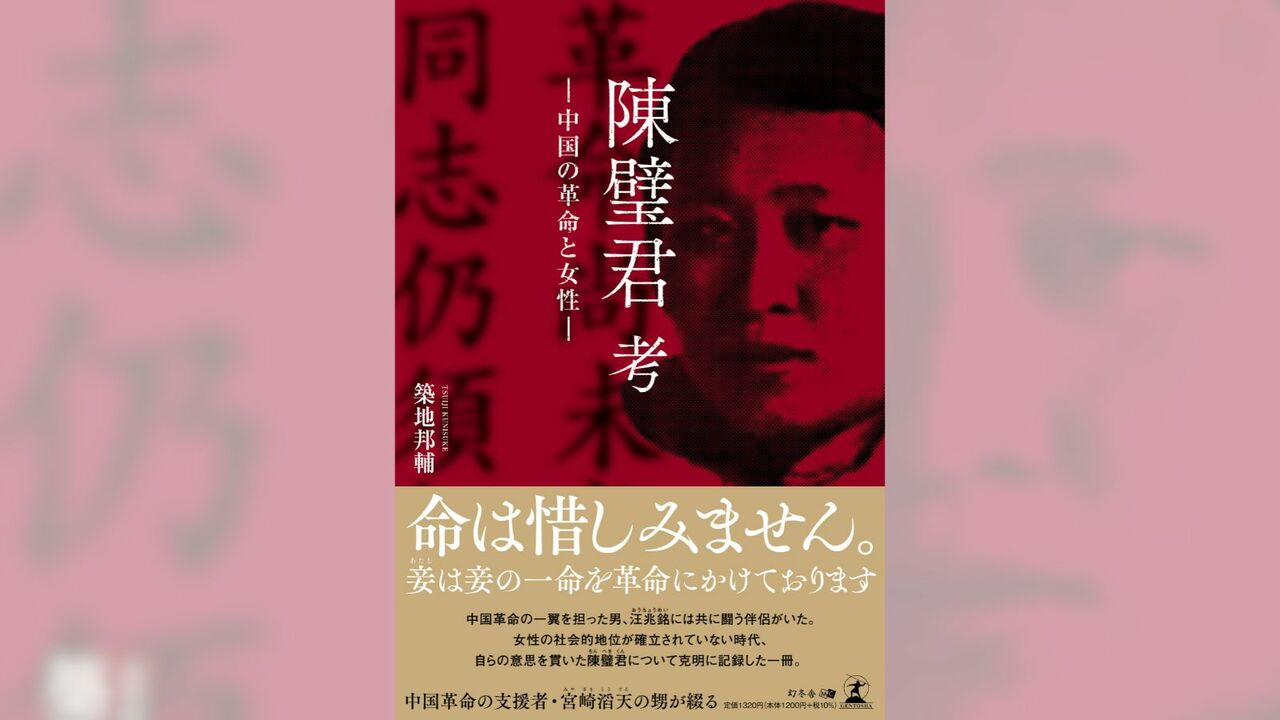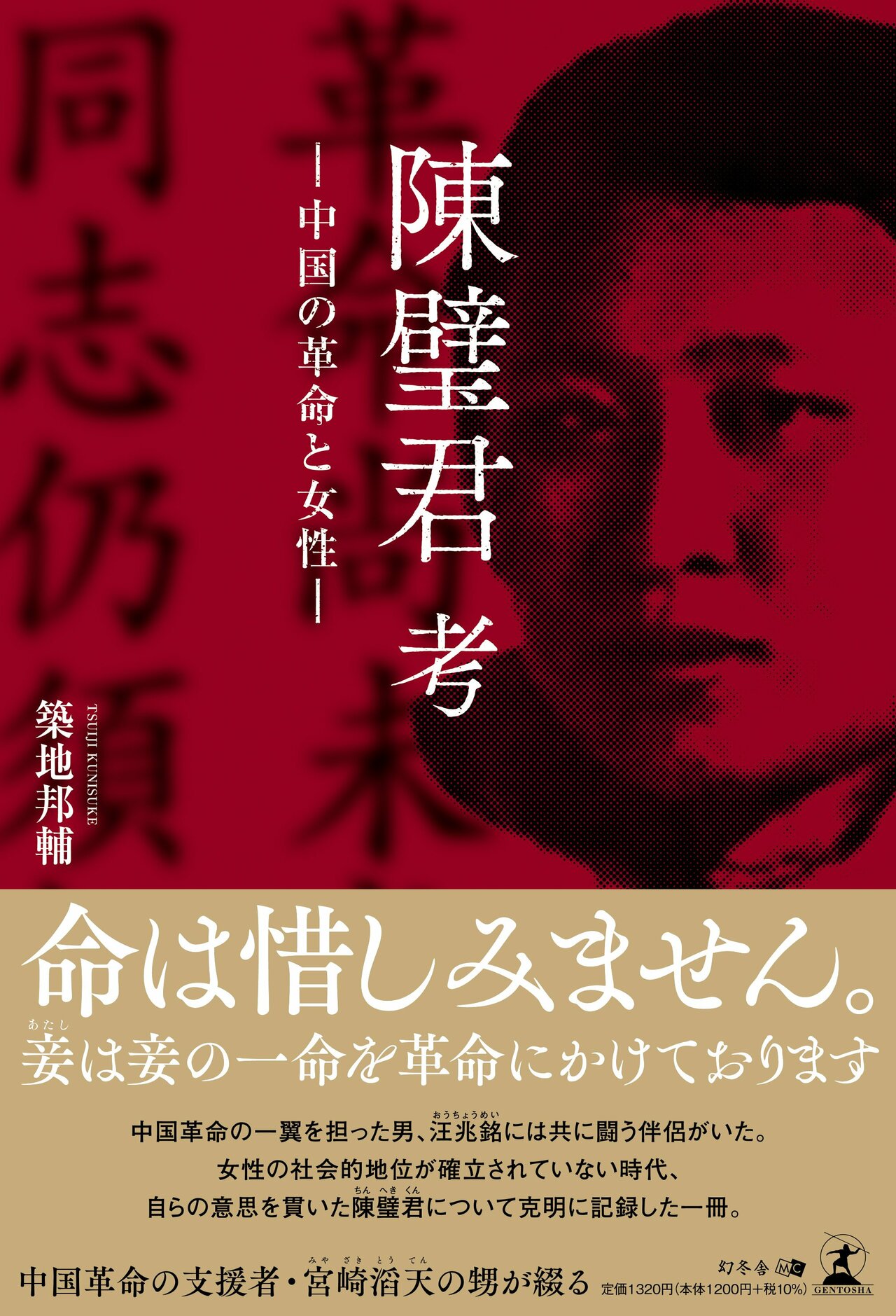まえがき
私(この本の筆者の次男)は二〇〇二年(平成十四年)に定年退職し、翌年から約十年余、世界のあちこち約三十数ヶ国を旅する機会に恵まれた。この本のモチーフ、孫文に関わる中国の広州には二〇一二年(平成二十四年)に、台湾の台北には二〇一三年(平成二十五年)に訪れた。
現在孫文は、中国(中華人民共和国)では「革命の父」として、台湾では「国父」と称されて敬われている。
その象徴として、広州では八角形の塔を載せた中山記念堂が聳え、その前にすくっと前方を見据える孫文の銅像が屹立している。台北には中央に坐する孫文を覆った国立国父記念館が鎮座し、そこでは孫文座像の両脇を衛兵が直立不動で守護し、正午の衛兵の交代が観光客の目玉となっている。
国立国父記念館の受付には、孫文の革命を助けた多くの支援者のうち、孫文が特に心に残ったとされる百人の顔が壁一杯に描かれている。案内してくれた国立国父記念館研究員の劉さんは「この中に日本人が三名います。ここにいるのが宮崎滔天(とうてん)です」と指し示してくれた。そこにはいつもの羽織、袴で髭づら滔天の顔があった。
その滔天の東京の家族の寓居に、辛亥革命勃発直前の、一九一〇年(明治四十三年)五月十九日、孫文が何の前触れもなく、ひそかに訪れる。当時孫文には革命危険分子として、清国政府の強い要請により、日本追放令が出されていた。
そんな孫文の突然の来訪に満面の笑みを浮かべ、大喜びする滔天と妻の槌(つち)子(筆者の叔母)。その一方で歓待するための風呂を炊く薪さえもないことに困惑する叔母。
それを察して走り回って隣の家の庭から薪を拾い、風呂を沸かす滔天の息子の龍介と震作。それを兄弟のように宮崎家に同居していた、当時日本に留学していた黄興(こうこう)の長男黄一欧(こういちおう)が、見様見真似で手伝う。
奇しくもその日は七十五年振りの彗星の出現で、これは何か大事件が起こる前兆かと、世界中が大騒ぎであった。