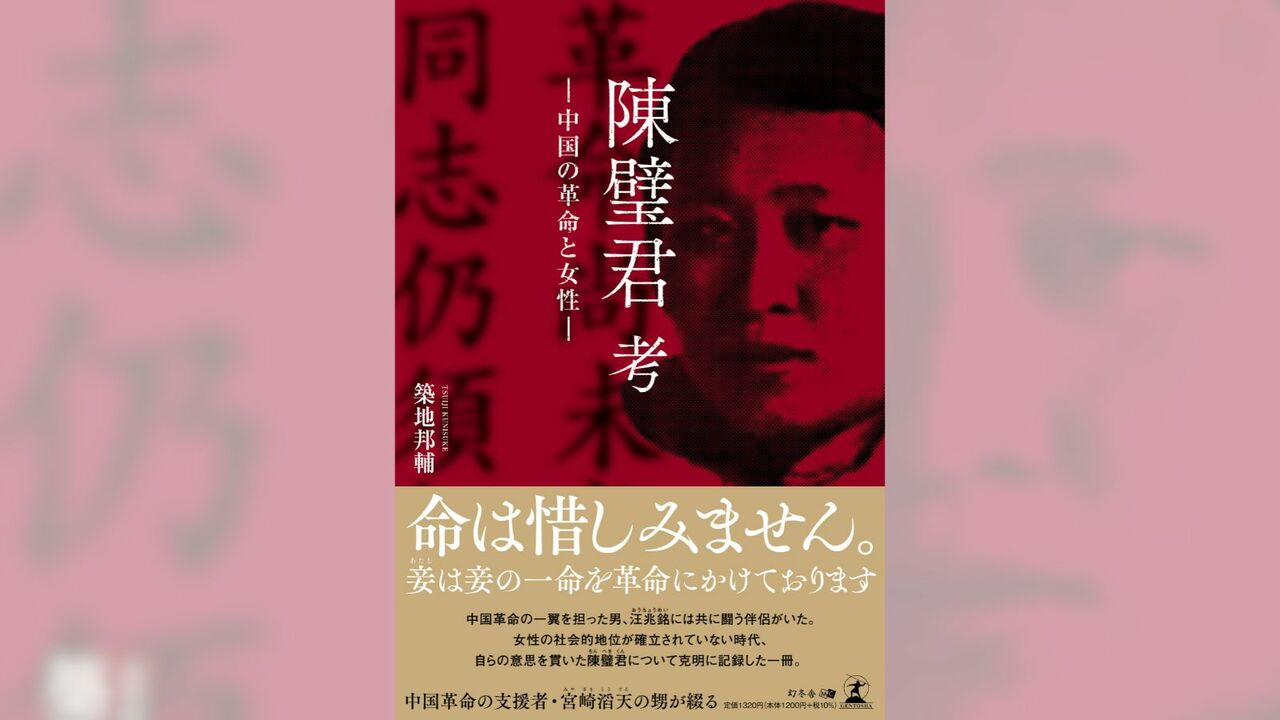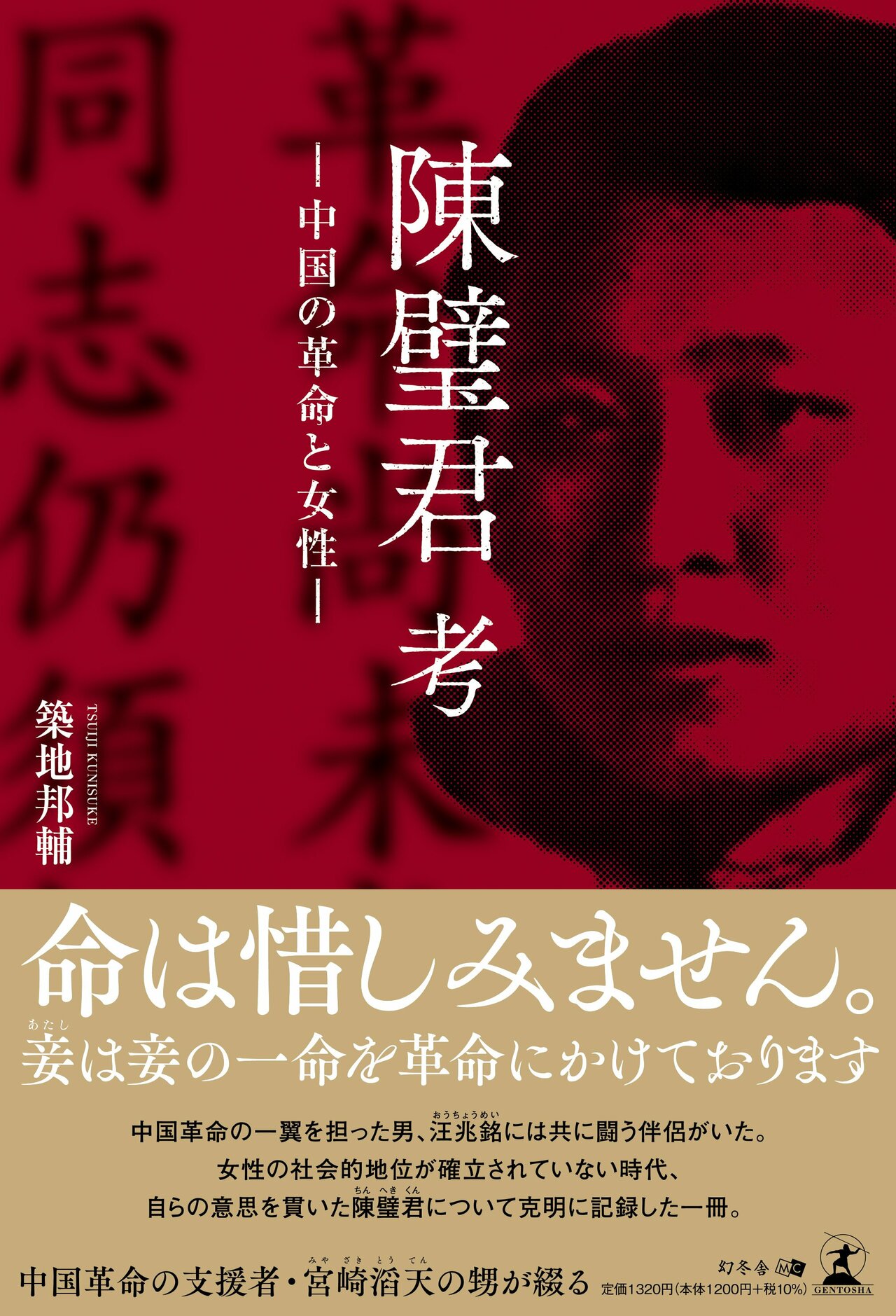【前回の記事を読む】中国革命運動の温床となったのは、東京と横浜だった。日本に亡命してきた思想家が、1万人の中国人留学生に……
第二章 中国革命の夜明け前
同盟会は一九〇六年(明治三十九年)一月、機関紙「民報」(1)を創刊した。初代編集長は張継であり、胡漢民、陳天華(ちんてんか)、章炳麟(しょうへいりん)、朱執信(しゅしっしん)、馬君武(ばくんぶ)、宋教仁等が、論説執筆者であった。
この他に宣伝責任者として第一線に立ったものに、汪兆銘、章炳麟、廖仲愷、及びその夫人何香凝等が当たった。
中国同盟会設立の翌年、一九〇六年(明治三十九年)には、萍郷(ひょうきょう)、瀏陽(りゅうよう)、醴陵(れいりょう)の各地に革命戦争が勃発した。各所に興る革命軍に対し、清政府は四万の軍隊を動員して之を鎮圧、党員を捕らえては片っ端から死刑に処した。
そして、その革命党の策源地が日本の東京にあることを知ると、日本政府に強硬に抗議して、彼等の日本海外追放を要求した。
東京の中国革命党の指導者及び留学生の有志は、学業を放棄して続々と革命戦場の中国に帰り、自国中国の革命戦推進要員となるのである。その頃の現場戦線に於ける革命党の指揮官は、当初黄興であり、後は汪兆銘であった。
しかし革命運動の第一線部隊の度重なる失敗は、辛亥革命により、武昌に於いて勝利を収めるまで続いていた。
これに対して、東京の同盟会本部にあった梁啓超、章炳麟等(保皇党一派)は、現場の戦線に在る孫文、汪兆銘等指導者に対し、その失敗を非難し、猛烈に攻撃の矛先を向けて来た。
章炳麟等の言うところはこうである。
「革命党の首領孫文等は、党員を死に駆り立て、自分は高楼、華屋に安穏としている」
章炳麟はその頃から革命党を離党し、辛亥革命では梟雄(きょうゆう)袁世凱と手を握っていたのである。彼は中国同盟会員の中の策士的人物であった。
一方この非難を身に受けて憤慨したのが汪兆銘である。