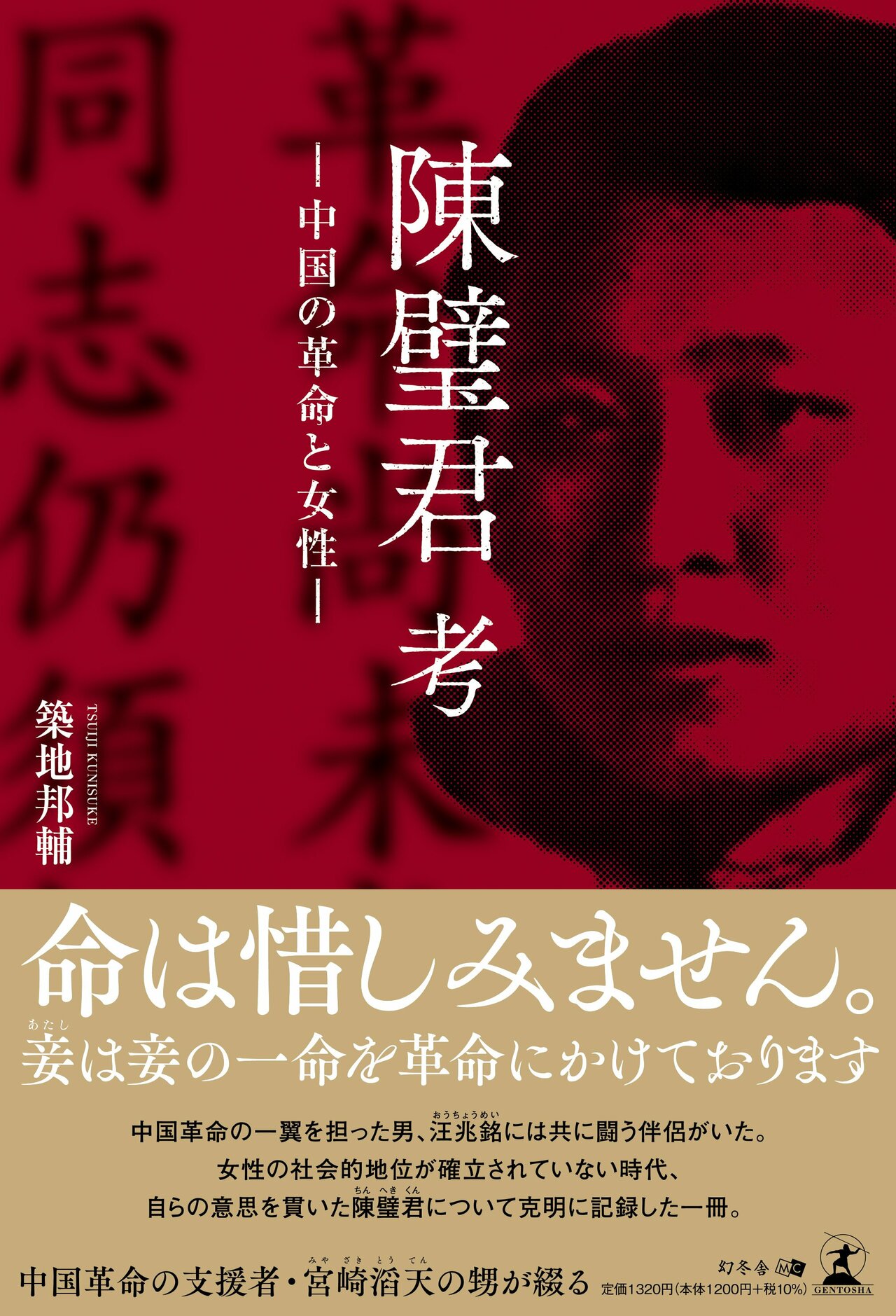その日になった。夕食も済んだ。そろそろ空には星が見える頃である。私は一寸、家から外に出て空を見上げた。空には星が見え出していた。
「星が出とる」と部屋に入るなり、誰に言うともなく叫んでいる私の心の中には、今夜やがて出るであろうハレー彗星に、強く子供心を惹かれていたことが頷(うなず)かれる。それは私が六栄尋常小学校の五年生になった許りの腕白小僧時代のことである。
私が空を見に外に出、部屋に戻り、「星が出とる」と独り言を叫んだのを、特に気をつけて見ていたのは、両親でもなかった。姉でもなかった。まだ尋常小学校の初年級だった弟俊助は、そろそろ眠ることを考えていた頃だったろう。
「オイ!! 邦輔、ハレー彗星を見に行こう」と言い出したのは兄であった。
兄は東京帝国大学理学部をこの三月卒業して、長崎の測候所長として赴任の途中、家に帰っていたのだった。
兄からそう言われて、私は、ハレー彗星という怪物みたいなものに脅かされ乍らも、その正体を見届けたいと思っている自分の心を見られたような気がした。私は黙って立ち上がった。私の心の一隅には、大学を出た兄となら心配はない、という安心感が湧いてきたのだろう。
兄に連れられて家を出ようとする時、二人の後から母1)の声がした。
「寒うならんうち、早よう帰んなはいよ」
母の心の中には、ハレー彗星に対する怯えた気持ちが残っていたものと察せられた。
「どこから見るか?」と兄は歩き乍ら私に呼びかけた。腕白盛りであった私は、遊びの縄張りの中であるこの辺りの地形なら、隅から隅まで知りつくしている。