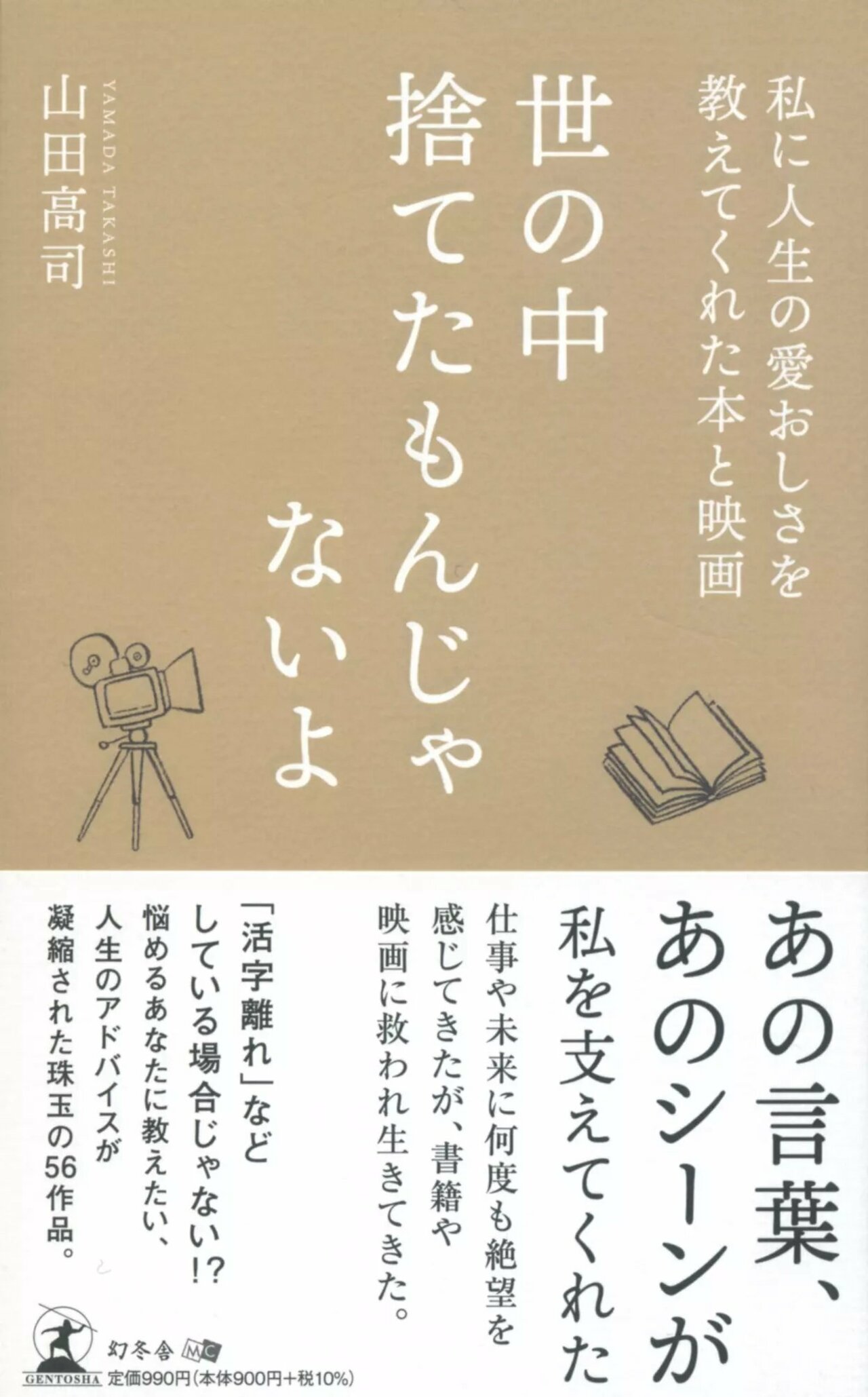毎日出てくる亡霊の父は、実はヒロインの心の中の葛藤の現れであり、亡くなってしまった大好きだった父ならこう言うだろうという、父の言葉に替えて自分自身の進む道を考えている姿なのだ。
自分の心の中の父の言葉と自分自身の思いが激論を交わし、少しずつではあるが、前へ進んでいく。はじめは「自分は、一人静かに生き、早く死にたい。」と思っていた。そんな気持ちが、図書館に現れた青年の言葉と、自分の中の父の言葉で少しずつ変わっていく。
被爆した人々の多くは同じような体験や思いがあったことだろう。この作品はそれを汲み上げ、少しでも前向きに生きていく事を望み、また、忘れてはならない原爆の悲劇を訴えている素晴らしいものである。
ヒロインの美津江を演じていた宮沢りえはとても難しい役をこなしていると思った。「ありがとありました」という、優しい響きの広島弁もヒロインを引き立たせている。
「死ぬことぁない。死ぬまでもない。人を押し退ける勇気がなくても、死ぬ勇気はなくても構わない。私の目の前にあるのが唯一の現実である。死者も含めて現実である。死者を想うのも現実であり、幻想に悩むのも現実である。
そんな、人それぞれ違う現実の中では、正解なんてありゃあしない。悩んでいても時間が過ぎる。何かをしなくては生きては行けない。後悔しなければいいのだと思う。それが、唯一の解答ではないだろうか。」
心にしみる言葉である。