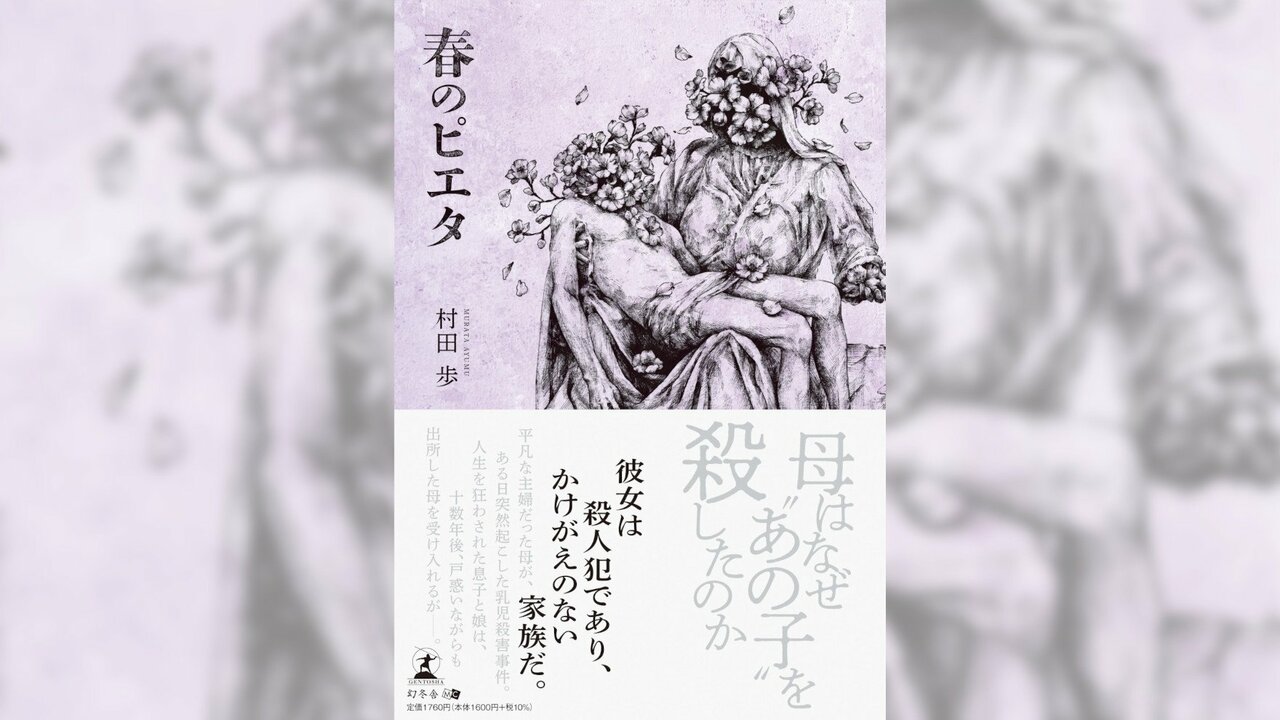劉生 ―春―
「どうみてもゴルフ場のキャディさんの格好じゃない」
ああ、そうか、隣の喫煙所の婆さんのことか。俺は、というより俺たち一家は、ゴルフになどまるで縁がないが、そう言われてみればたしかにそんな格好だよなと納得した。
妙に派手な色合いの上下も、帽子の後ろ側のつばが肩まで垂れてるのも、まさに妹の言う通りだ。女というのはこういうときにも、他人の服装の観察だけはしっかりとするものらしい。
「だけどキャディにしちゃ、年を取りすぎてないか? 六十は過ぎてるよ、どう見ても」と答えたときはもう妹は小屋の外を注視して、俺の言うことなど聞いちゃいない。親父がこちらに戻ってくるのが見えた。
「十一時からだから」
小屋に入るなり親父はいった。優子が眉を顰(ひそ)めて「三人いっしょに入れるの?」と訊いた。
映画やテレビで見る面会室は、椅子を三つ並べても十分な広さがあるように見える。だが、実際はどうなのか。面会人の定員というのがあるのだろうか。
親父は気の利かないところがあるが、定員も確かめずに俺たちを連れてくるようなことはいくらなんでもしないだろう。第一、手続きの書類に面会人の名前を書いたはずだから、それが受理された以上心配するには及ばない。
優子の奴はバカなことを訊くな、と思ったが、じつは道中列車に揺られながら俺も同じことを考えていた。
「たいてい大丈夫だろう」
親父は妹の不安を今ひとつ払拭しない答え方をすると、上着のポケットから煙草を取り出した。