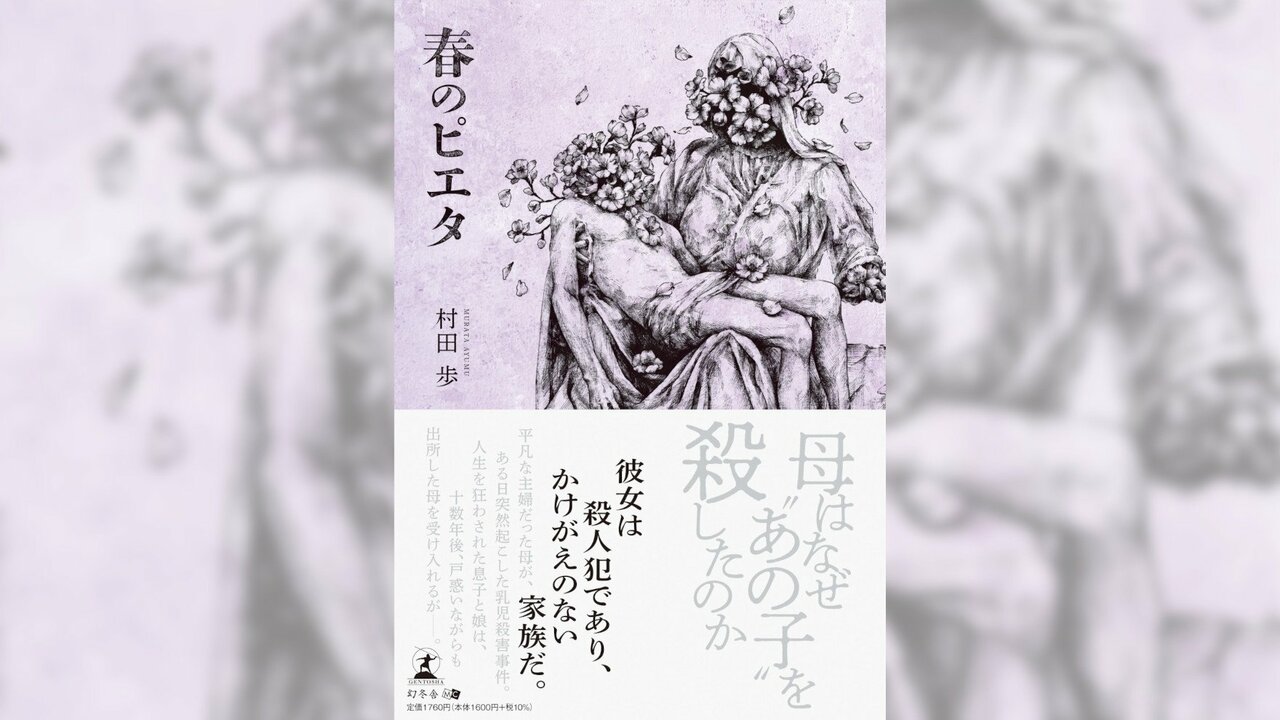劉生 ―春―
俺たちは婆さんより早く呼ばれた。
刑務官に案内されているとき、初めて親父が落ち着かない様子を見せた。首から下は先を行く刑務官に素直に従っているのに、首から上はまるで道を見失ったかのようにあたりをきょろきょろ見回している。勝手が違う、といった顔だ。俺は急に不安になった。
悪い想像が浮かぶ。たとえばお袋は急病で、敷地内の医務室のベッドで身動きできなくなっているのではないか。だからいつもの面会室で会うことができず、親父は不審に思って戸惑っているのではないか。
すぐに、ばかばかしい、と考え直した。そうならば、面会申し込みのときにそうと知らされているだろう。
親父が手続きを取りに行った建物の脇をまわると、保育園を囲っていたのと同じ緑色の板塀があった。刑務官が塀の木戸を鍵を使って開ける。
いきなり、別世界がひらけた。
三方を建物に囲まれた、そう広くもない中庭の中央に桜の木が一本立っている。一昨日の雪に耐えて花は八分咲きだ。その下に四阿(あずまや)がある。地面は枯れ色にほわっと緑が兆した芝だ。よく手入れされている。日当たりがいいのか残雪はほとんど見当たらない。
四阿の中は日陰になってよく見えないが、淡い空色の作業着――これが囚人服なのだろうか――を着た女がぽつんと座っていた。近寄って行っても、規則なのか女は立ち上がったりせず、背筋を伸ばしたまま身じろぎもしない。ただ俺たちの方をじっと見据えている。
こんなに小さな女だったか――。