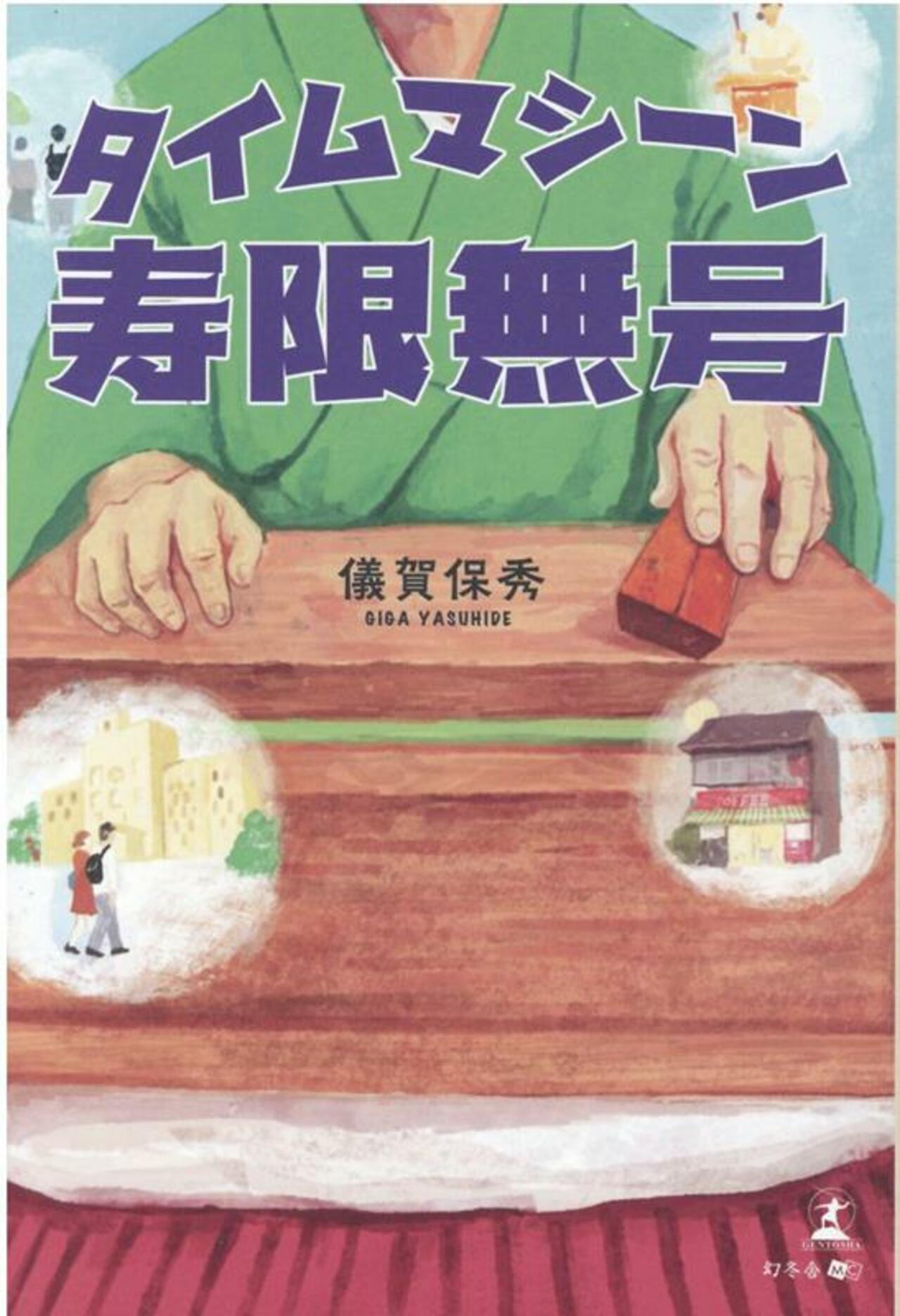入門当時は自分もマスコミの寵児となることを夢見ていた。
町を歩いていると、あちこちから声をかけられる。面倒くさいとは思いつつも愛想の良い会釈。「いつもありがとうございます」そう言って、忙しそうに立ち去る。そんな想像をしていたこともあったが、現実は厳しい。
アッと言う間の二十九年。
未だ浮上せず低空飛行状態。落語家と名乗っているが、町を歩いていて見知らぬ人に声をかけられることは皆無だ。
そんな喜之介だが、落語家として何とか食べていくことはできていた。
マスコミでの露出はほぼ皆無でも色んな仕事はある。定席への出演の他、様々な地域寄席、学校で落語を披露する機会も多い。本業の落語以外ではイベントや企業の催し等での司会進行などなど。実際、まあ何とか生活していけるくらいの収入はある。
子供がたくさんいて、多大な教育費が必要な場合は家計が苦しくなるが、喜之介の場合は幸いというか、気楽な身分というか、独身。だから、自分一人だけが食べていくには今の年収で充分だ。ただ、ずっと独身だったかというとそうではなく、結婚経験はある。つまり世間でいうところのバツイチ。
落語家の妻というものは収入が少なくても夫を支えてくれる人が多いという印象が強い。少なくとも喜之介はそう思っていた。売れなくても落語家の夫を温かい目で見て、「まあ、しゃあないわね」と長い間、寄り添う。実際、周囲を見回しても共働きで妻のほうが収入の多い落語家もよく見かける。
しかし、喜之介の場合は、妻からあっさり見限られた。
ちょっとショックだった。いや、それは強がりで、正直言うとかなりショックだった。
妻に去られた話は思い出すと悲しくなるので、頭の中から追い払う。
これは今、関係ないねん!