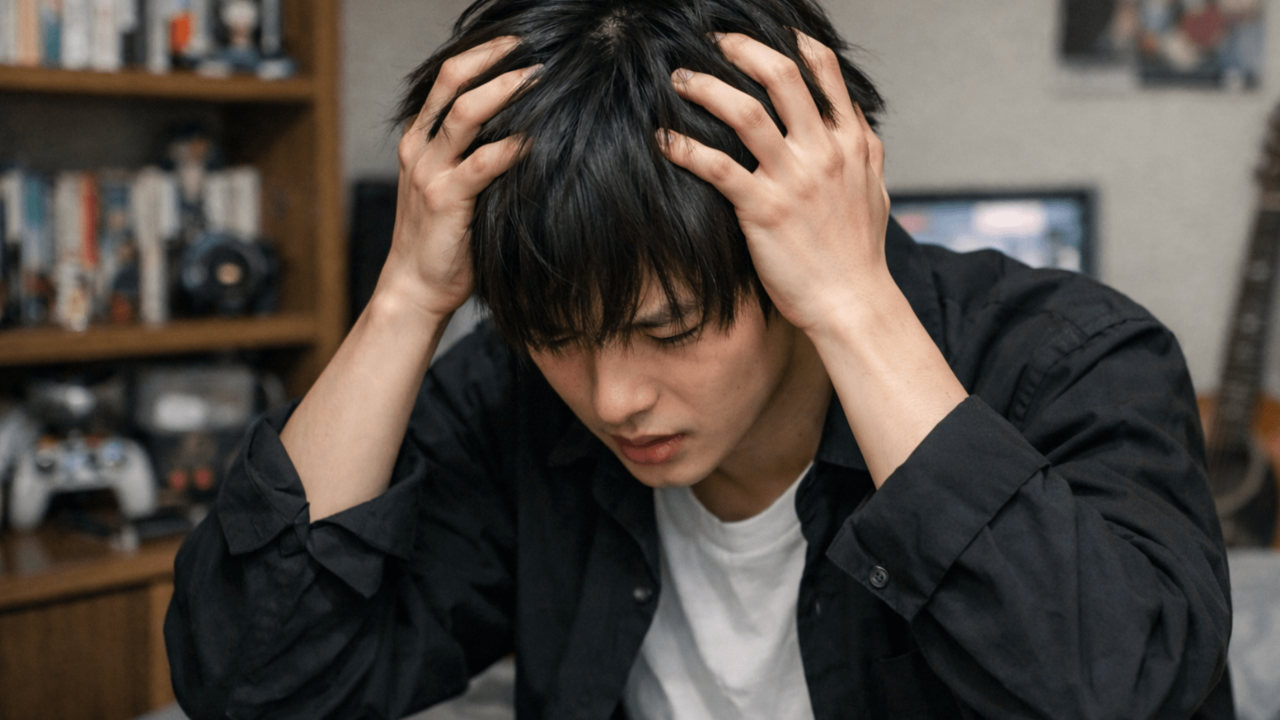「まぁ、事情聴取って言葉が一番近いってだけで、その真琴本人に事情を聞きたいことがあるんだよ。どうも腑に落ちない問題があるのでね。そんなに怯えることはないさ」
あずみが必要以上にびくっとしたので、先輩女子は少し強引すぎたかなと思っているのだろう。それは口調からも分かった。
でも、先輩女子の目を見る限り、真面目に真琴に面会を求めているのだ。何か聞きたいことがあるらしい。しかもそれは、慎重に対応しなければならない事柄なのかもしれない。
だからこそ、一方的に真琴に直撃する無礼はせず、一度クッションを置いてお目通りをさせてもらえばあとはこちらでなんとかする、ということなのだろう。そういう意味では筋が通っている……。
「分かりました」
あずみはそれ以上の追及は諦めてうなずいた。
「でも、その前に、わたし、まだあなたのお名前を聞かせてもらっていません」
「おっと……名前ね」
先輩女子は思いついたように言った。
「わたしは山崎由良。一応、あんたらと同じ看護学部だよ」
「看護学部……」
やはり、同じ学部の先輩だったのだ。
「ただし、わたしは院生だからね。あまり接点はないかもしれない」
あずみがこんな先輩いただろうかと思っているのを見抜いて補足してきた。それで納得がいった。いくら同じ学部内でも、さすがに院生となるとほとんど接点がないのだ。講義を受ける時間も違えば校舎も違う。
「ま、驚かして悪かったよ」
最後に由良は謝ってきた。その口調が柔らかいものに変わっていた。
少々強引だけど、悪い人ではない気がする……。
「真琴に話はしてみます。もし真琴が了解したら、どちらに連絡したらいいですか?」
あずみは由良の連絡先を聞いて、そのままロッカー室をあとにした。彼女との出会いが、またひとつの事件の始まりになるとも知らずに……。
【前回の記事を読む】そこにはひとり、男性なのか女性なのか見分けがつかない人が立っていた。