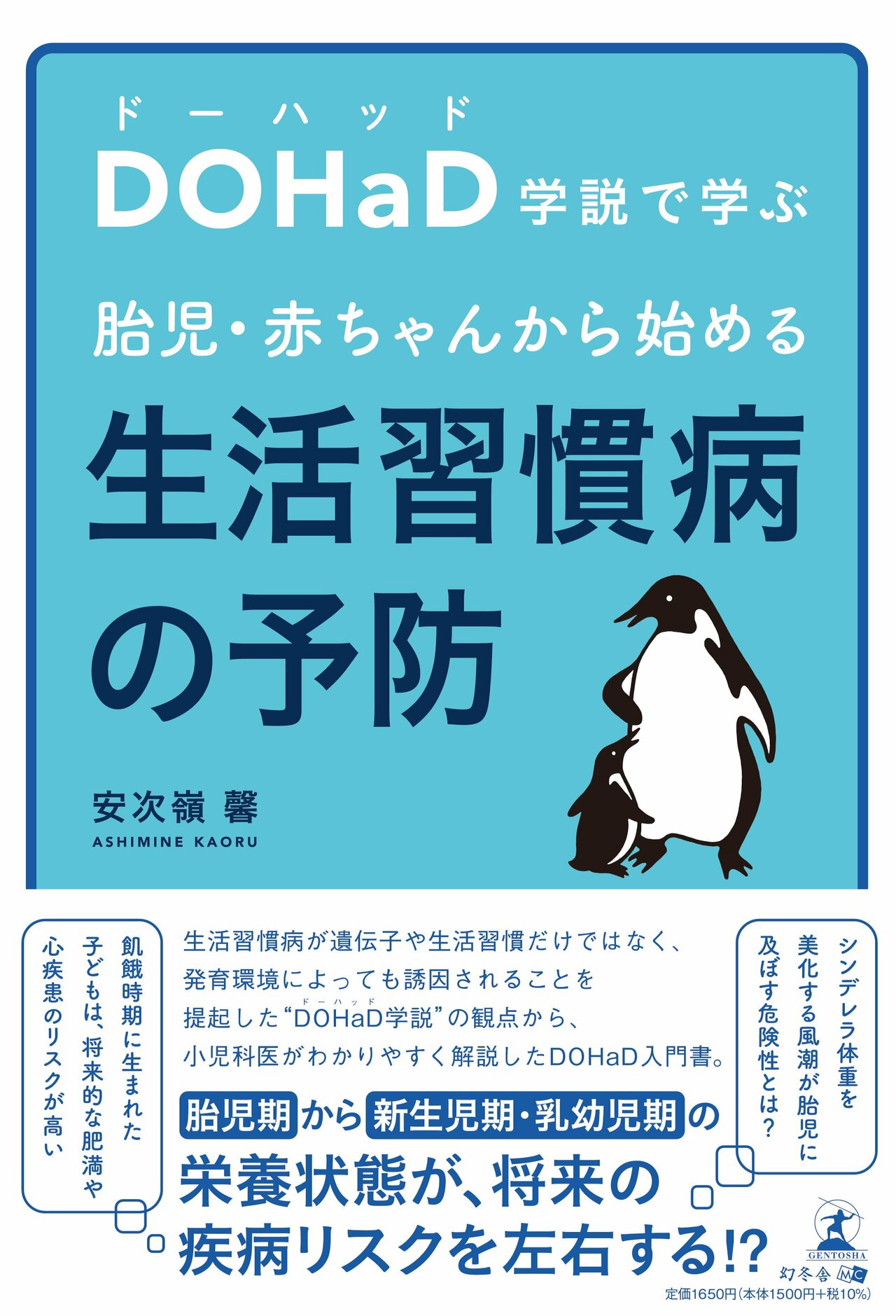第2章 DOHaD学説
1│バーカー仮説からDOHaD学説へ
1│倹約表現型仮説(Thrifty phenotype hypothesis )
1990年以降、バーカーは基礎栄養学、動物生理学などの専門家と交流を深め、彼の学説のさらなる深化を求めました。ヘールズ(Nick Hales)はバーカーとともに、胎児期の低栄養がのちのインスリン抵抗性と2型糖尿病をきたすという「倹約表現型仮説」を提唱しました 1,2。
それによると、まず、母体の栄養障害が事の始まりです。すなわち、母体の栄養不良→胎児の栄養障害(特にアミノ酸)→膵臓β細胞の減少→胎児の臓器発達及び成長の遅滞という流れになります。
少ないエネルギーを倹約して用いるため、児の体格は小さくなります。それでも重要な臓器である脳は栄養障害から守られ、正常な大きさを保ちますが、肝臓や腎臓などの臓器の発達は抑制されます。それゆえ、胎児期の成長障害は、体格と臓器の機能を生涯にわたって変化させます。
出生後は、乳児の栄養障害→成長後の膵臓β細胞の機能低下→2型糖尿病→メタボリックシンドロームという流れで、肥満、高血圧、心疾患などを発症します。
ニール(James Neel)は、すでに1962年に「Thrifty genotype hypothesis(倹約遺伝子型仮説)」3を提唱し、「仮想の倹約遺伝子」が糖尿病を発症させると考えていましたが、ヘールズらの「Thrifty phenotype hypothesis(倹約表現型仮説)」は胎児期、乳児期早期の低栄養こそ、糖尿病発症の主因であると、遺伝子説に真っ向から反論しているのです。
バーカーは、さらにドウズ(Geoffrey Dawesオックスフォードの胎児生理学者)を通して、動物実験によってバーカーの学説を支持した数多くの研究者と交流を続けました。その中には、グラックマン(Peter Gluckman)、ハーディング(Jane Harding)ら、著名なDOHaD研究者たちが含まれます。