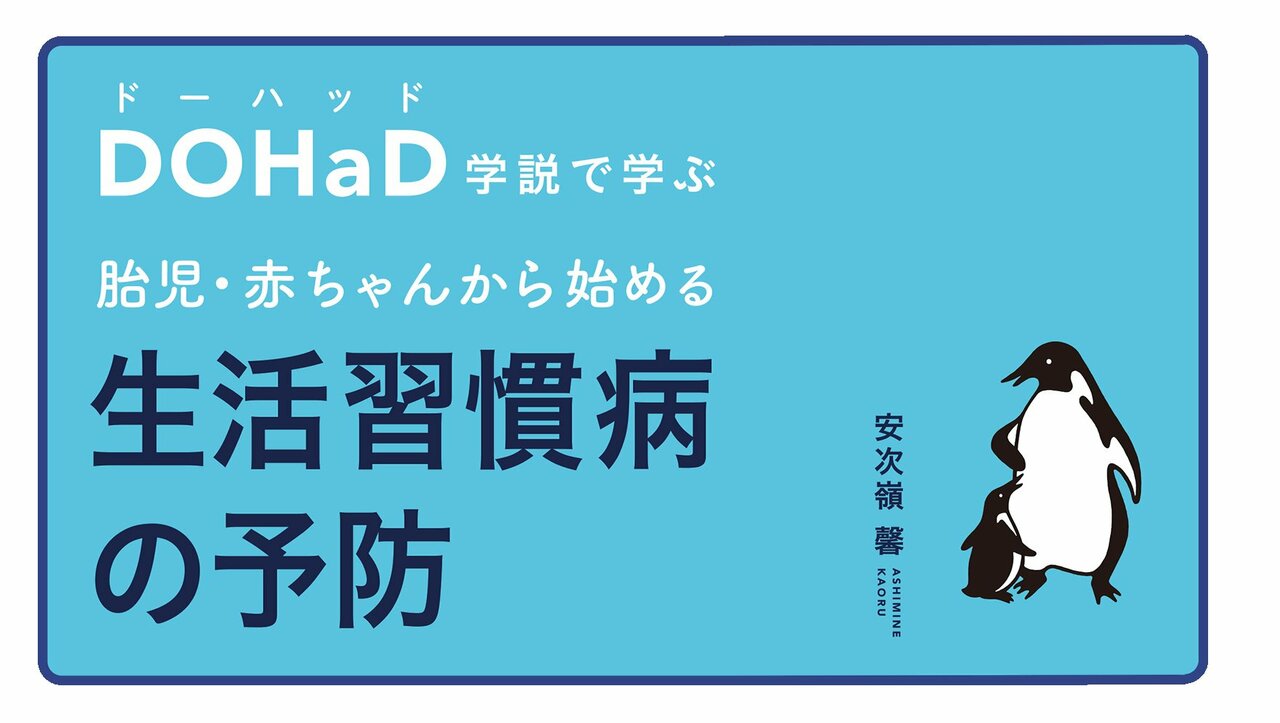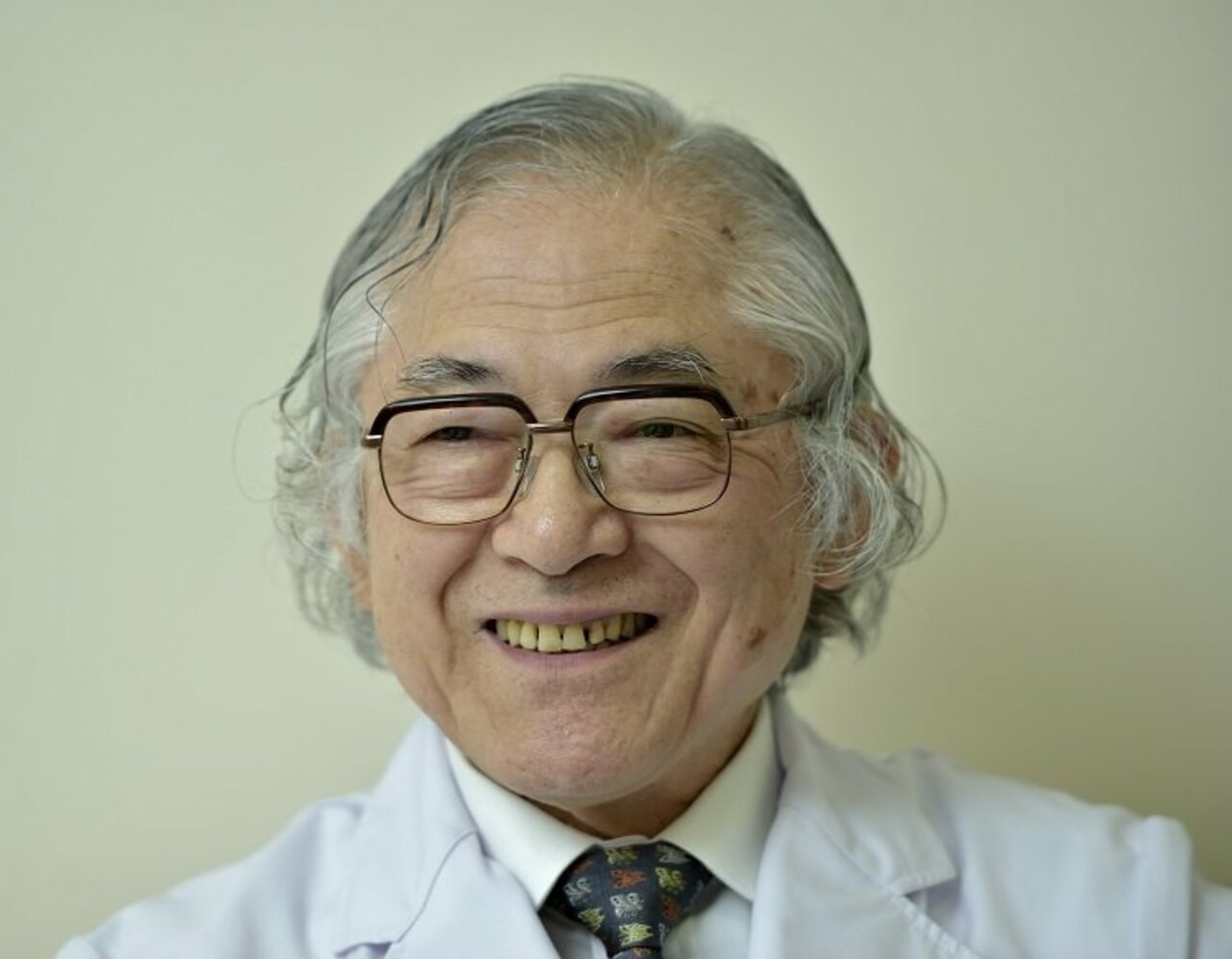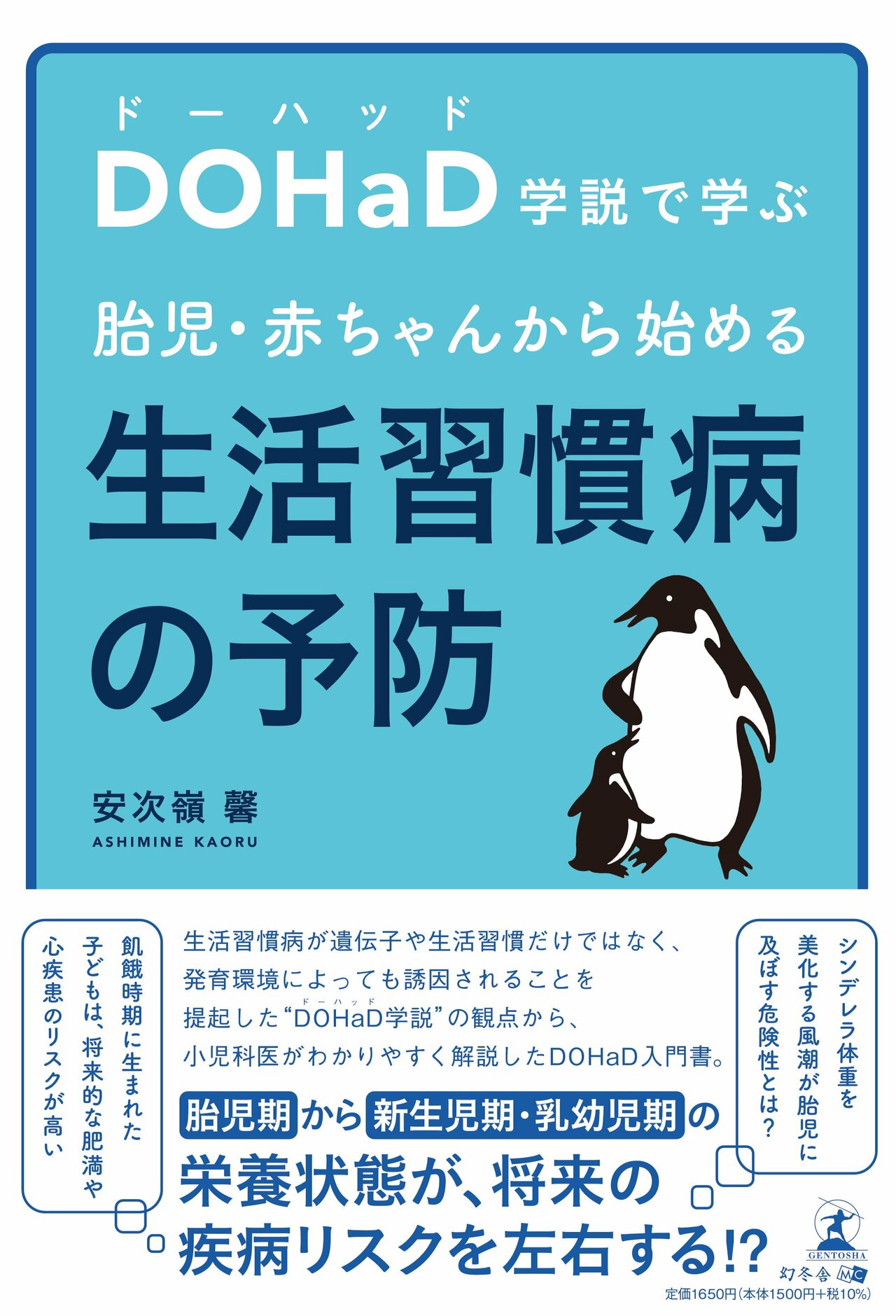第2章 DOHaD学説
4│ 国際DOHaD学会
1│草創期
1999年、国際FOAD会議(International Council on Fetal Origins of Adult Disease)が結成され、2001年、第1回世界FOAD学会(World Congress of Fetal Origins of Adult Disease)がインドのムンバイで502人が参加して開催され、第2回はイギリスのブライトンで531人が参加して開催されました。
この後、胎児期を超えて、出生後早期の環境が将来の健康に影響を及ぼすという概念が確立されました。そして、新組織の名称は 国際DOHaD学会(The International Society for Developmental Origins of Health and Disease)と変更され、学会名も第3回よりFOAD からDOHaDに変更されました。
学会の初代会長はグラックマン(2003–2007)、2代目はハンソン(2007–2017)で、以後、両者がDOHaD学会を牽引しました。
2│発展期
第3回国際DOHaD学会(International Congress of Developmental Origins of Health and Disease)は2005年11 月 にトロントで開催され、それまでの学会の運営に加えて、次のような改革がなされました1。
➊DOHaDの問題を開発途上国にも広げる。
➋若い研究者向けのプログラムを設定する。
➌発達生物学、発達可塑性、社会階級の影響、未熟児の影響、有害環境、データ分析など、新たなる研究領域を広げる。
この学会には50カ国から691人の参加者があり、発表演題は400に達しました。学会では、肥満とその予後も注目を集めました。従来、栄養不良が将来の生活習慣病のリスク因子とされていましたが、肥満もリスク因子であることが論議されました。
すなわち、先進国のみでなく開発途上国でも同様の問題が起こっていることが指摘されています。
以下に、これまでの学会開催年度と開催地を示します。
本学会は、日本DOHaD学会と称し、英文名をJapan Society for Developmental Origins of Health and Disease(DOHaD―Japan)としています。本学会は、国際DOHaD学会の日本支部と位置付けられています。
ホームページに掲載された学会設立の経緯と学術集会の会長、場所について述べます。
2011年12月、研究会設立をめざす有志で、研究会の目的、設立に向けてのロードマップ、発起人、規約、国内のDOHaD研究の状況などに関して意見交換を行いました。参加者は、福岡秀興、板橋家頭央、久保田健夫、佐田文宏、瀧本秀実の5氏です。
その後、2回の幹事会を経て、早くも2012年8月には第1回日本 DOHaD研究会学術集会を開催しました。疫学、小児科学、産婦人科学、内科学、栄養学、生理学、農学、教育学など多岐にわたる分野の研究者106人が参加し、活発な討論が行われました。
2016年11月に、「研究会」の成長とともに「学会」へ名称を変更しました。
年1回の学術会議を重ね、2021年はCOVID-19パンデミックのため、第10回のWeb会議を行い、学会は着実に発展しています。
世界 DOHaD学会の日本国内開催をめざして国際学会本部と交渉を進めていますので、近い将来、世界中のDOHaD研究者が日本に集い、この領域の更なる発展が論議されるでしょう。