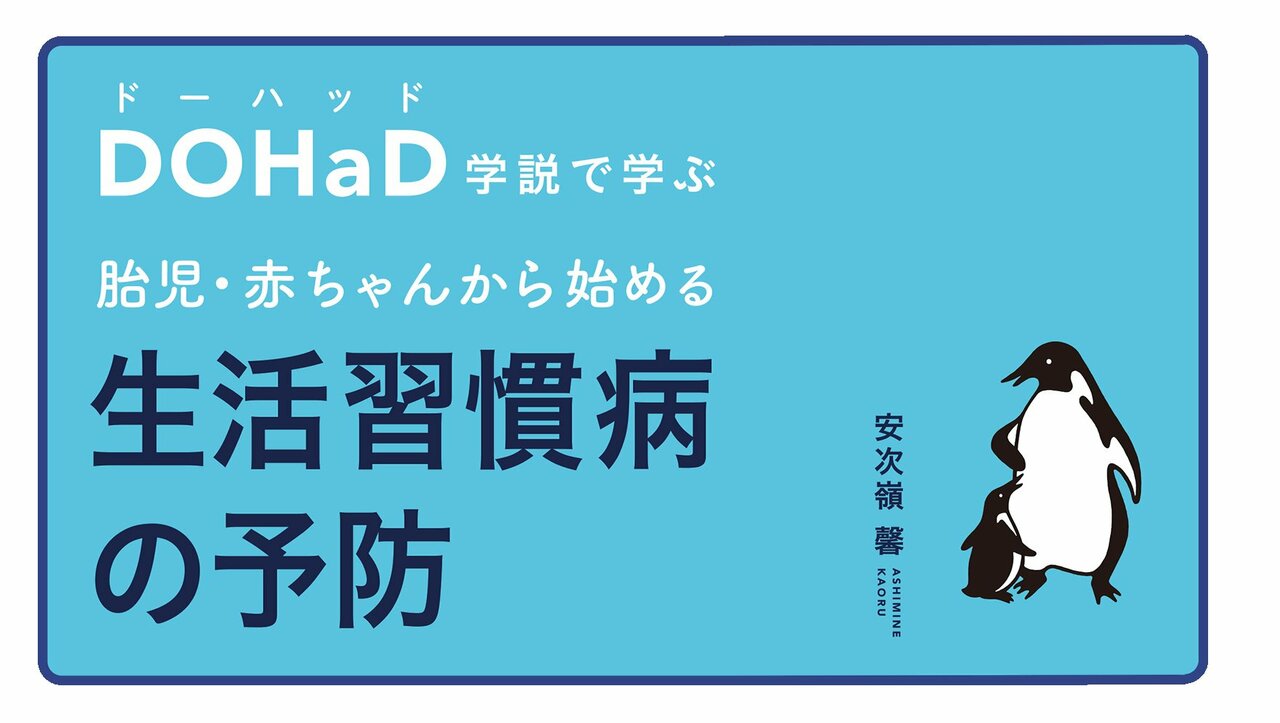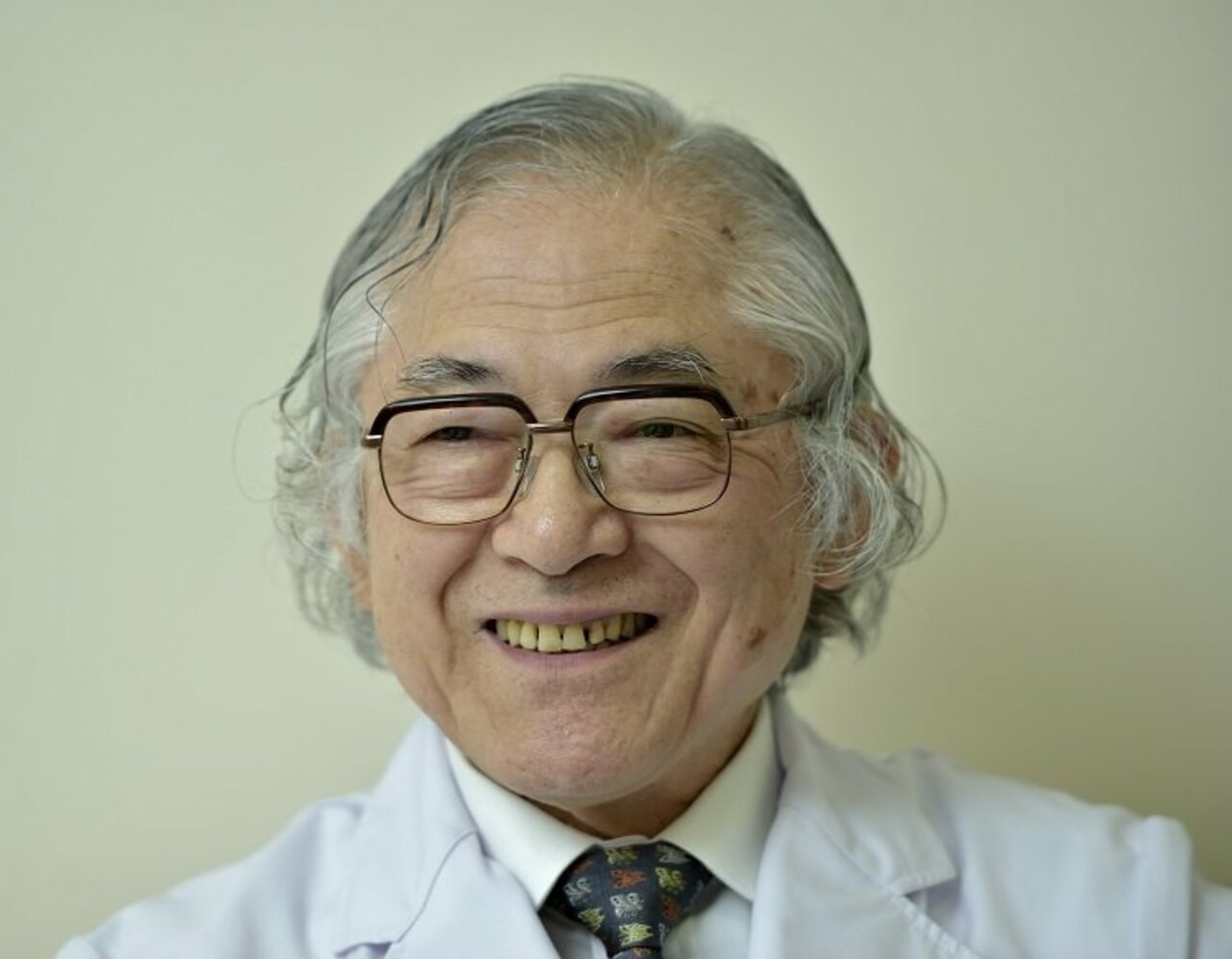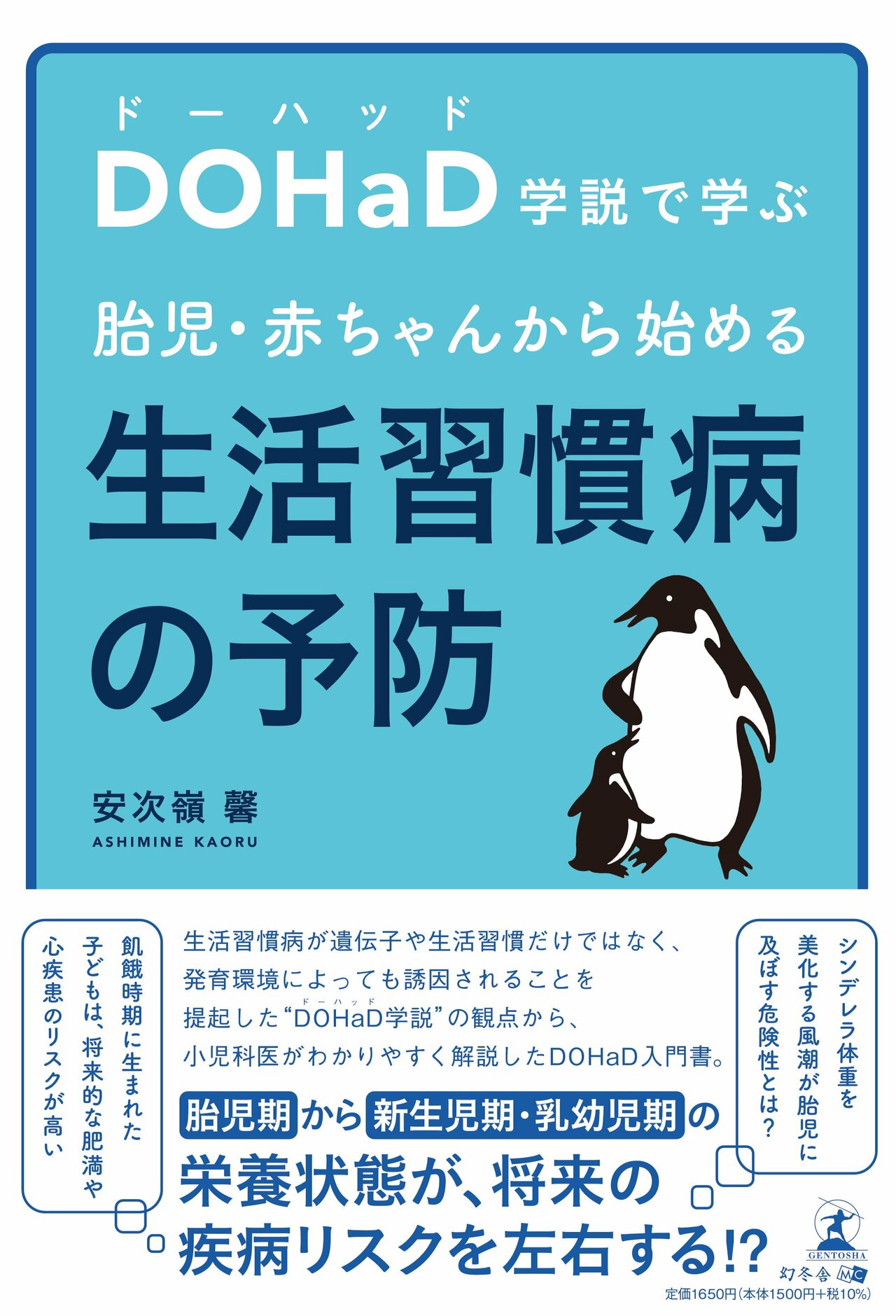【前回の記事を読む】DOHaD学会草創期。栄養不良が将来の生活習慣病のリスク因子とされていたが、肥満もリスク因子であることが論議された。
第2章 DOHaD学説
Column3
DOHaD トリビア
倹約遺伝子仮説 Thrifty genotype hypothesis
1962年、ミシガン大学の遺伝学者ニールは、thrifty genotype hypothesis(倹約遺伝子仮説)を提唱した。狩猟採集時代からの人類の歴史は飢餓との戦いであり、飢餓を乗り切るためにエネルギーを節約して体脂肪として蓄える「倹約遺伝子」は種の存続に有利であった。
しかし、近年は豊かになった食糧事情のため、倹約遺伝子は肥満、糖尿病を発症するという、不利な遺伝子になったと考えた(仮定の遺伝子)。この説は、学会に多くの議論を巻き起こし、批判にもさらされたが、「倹約遺伝子」の研究を促進した。
その中で、thrifty phenotype hypothesis(Hales &Barker), thrifty epigenomic hypothesisなどの仮説が生み出された。しかし、ニールが想定した「倹約遺伝子」はまだ特定されていない。
Neel JV. Diabetes Mellitus: A“thrifty”
genotype rendered detrimental by“progress”
Am J Hum Genet 1962;14:353-362.
プログラミング
ルーカスはプログラミングを次のように規定している。発達早期の出来事で、生涯にわたって影響を与えるのは、次の3つの場合である。
1)直接的なダメージ(例として、血管障害による四肢の切断)、2)感受性期に、種々の刺激を受けることによって身体発達の障害が起こる、3)感受性期に生理学的なインプリンティング(刻印)、あるいはセッティングによって、長期的な機能障害が起こる。
このうち2)と3)をプログラミングという。プログラミングと呼ばれるものは、栄養以外に次のようなものがある。鳥類で感受性期の視覚によるインプリンティングが、その後の行動に影響するのは1世紀以上前から知られている。他にホルモンや薬剤などもプログラミングを起こす。
ルーカスは、出生早期に与えられた栄養によるプログラミングが、将来のタンパク質代謝、糖代謝に影響を与えることを主張している。一方で、胎児期の栄養プログラミングについて、バーカーらの業績を評価している。
Lucas A. Role of nutritional programming
in determining adult morbidity.
Arc Dis Child 1994;71:288-290